恐怖症カウンセリング
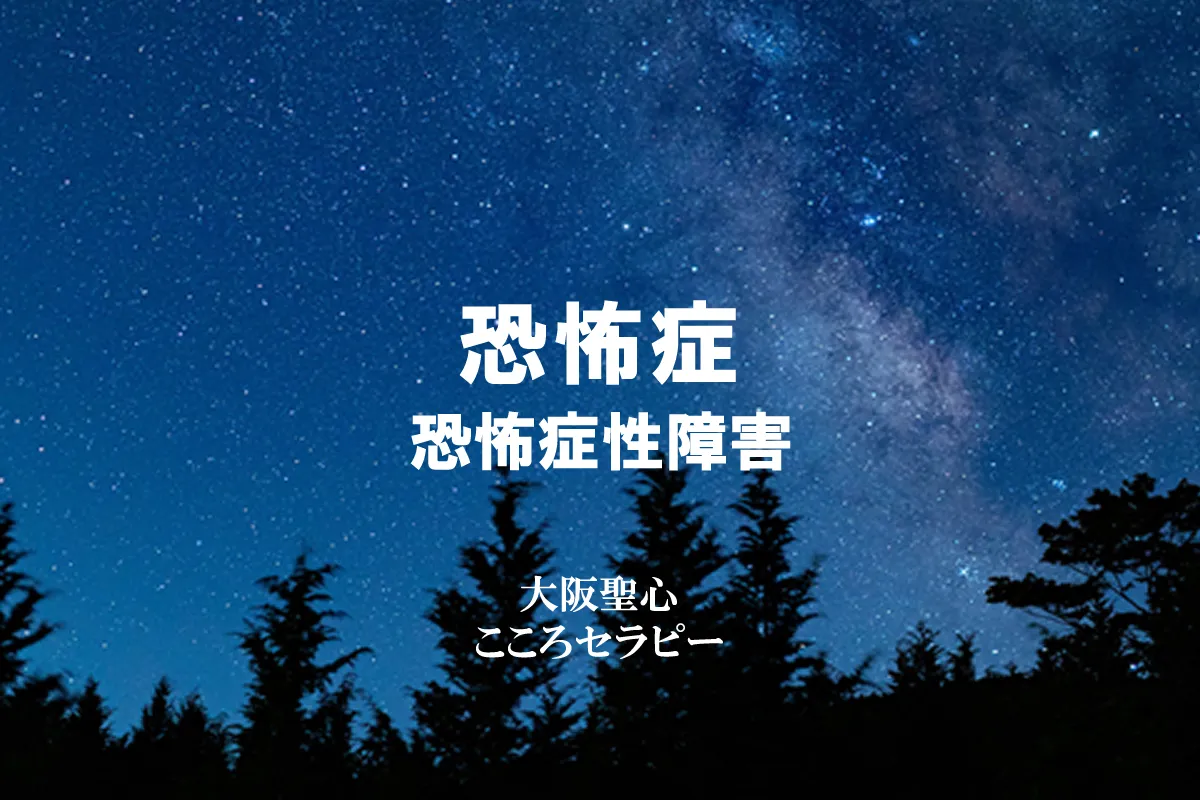
恐怖症の専門カウンセリング|臨床心理士・公認心理師が解決に導きます
恐怖症専門カウンセリング
臨床心理士・公認心理師
が解決に導きます
恐怖症にはさまざまな種類があり、単に「恐怖を感じる」だけでなく、日常生活や社会生活に大きな支障をきたすことが特徴です。克服のためには、認知行動療法などの有効な心理療法を取り入れ、恐怖や不安を生み出す考え方や行動パターンを少しずつ見直していくことが大切です。
関連性のあるテーマ
当カウンセリングは、診断や治療といった医療行為を行うものではありません。臨床心理士や公認心理師といった専門資格を持つカウンセラーが、認知行動療法などの心理療法を用い、様々な問題で悩む方々に対し、ご自身の心と向き合い、不安のメカニズムを理解し、日常生活をより穏やかに過ごすための専門的なサポートを提供します。
本記事は、アメリカ精神医学会(APA)が発行する『DSM-5-TR:精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版 改訂版』に基づき、臨床心理士が専門的知見のもとに執筆・監修しています。本内容は診断や医療行為を目的としたものではなく、カウンセリングにおける理解を深めるための情報提供としてご利用ください。
恐怖症(恐怖症性障害):正しく知ることから始まる克服への道

「不安と孤立感」
「恐怖症」と聞くと、あなたはどんなイメージを持つでしょうか? 高所恐怖症や閉所恐怖症など、特定のものを怖がる病気という漠然としたイメージがあるかもしれません。しかし、恐怖症は単なる「苦手」とは違い、日常生活に大きな支障をきたす心の病気です。
この記事では、多くの人が悩みを抱える「恐怖症(恐怖症性障害)」について、その種類や原因、そして克服へのヒントを詳しく解説していきます。
誰もが抱える「恐怖」と「不安」
恐怖症について理解を深める前に、まず「恐怖」と「不安」の違いについて考えてみましょう。
「恐怖」は、雷や地震、エレベーターのような、特定の対象や状況に対して強く感じる感情です。例えば、目の前にヘビが現れたら、多くの人が恐怖を感じますよね。これは、身の危険を回避しようとする自己防衛本能であり、私たちが生きる上で欠かせない感情です。
一方、「不安」は、いつ、何が起こるか分からない漠然とした不確実性から生じる感情です。たとえば、会社の面接を前に「うまく話せるだろうか」と心配になるのは、不安な感情の一種です。不安な感情もまた、私たちを慎重にさせ、最悪の事態に備えようと促す大切な機能を持っています。
恐怖症(恐怖症性障害)は、この大切な感情が過剰に働き、コントロールできなくなってしまった状態と言えます。本来は身を守るための感情なのに、それがかえって自分を苦しめてしまう。それがこの病気の本質です。
強い恐怖反応が続く場合、その背景には安全基地となる愛着の問題が関係している場合があります。詳しくは大人の愛着障害をご覧ください。
さらに、恐怖体験の捉え方は、幼少期の親子関係が影響することがあります。親子問題・親子関係の視点が恐怖症の理解を深める一助になります。
なぜ恐怖症(恐怖症性障害)は怖いのか
恐怖症(恐怖症性障害)が単なる苦手意識と異なる点は、その症状が激しい身体反応を伴うことにあります。
恐怖の対象に遭遇すると、動悸やめまい、発汗、吐き気などの身体症状が現れ、極度の緊張からパニック発作を引き起こすこともあります。
さらにやっかいなのが、「予期不安」という状態です。これは、実際に恐怖の対象に遭遇していなくても、「またあの状況になったらどうしよう」と想像するだけで、恐怖と全く同じ身体症状が現れてしまう現象です。
この予期不安が強くなると、恐怖の対象を徹底的に避けるようになります。これにより、仕事や人間関係、外出など、社会生活を大きく制限することになり、生活の質が著しく低下してしまうのです。
恐怖症(恐怖症性障害)の4つのタイプ
恐怖症(恐怖症性障害)は、主に4つのタイプに分類されます。それぞれに特徴があり、抱える悩みも人それぞれです。
1.社会恐怖症(社交恐怖症)
人から自分がどう見られているかを過剰に気にし、対人関係を避けてしまう恐怖症です。いわゆる「あがり症」もこれに含まれます。
「失敗したらどうしよう」「恥をかいたらどうしよう」という不安がベースにあり、人に会うことを避けるようになるため、孤立しやすい傾向があります。
社会恐怖症には、さらに細かな種類があります。
- 対人恐怖症: 人と接することに極度の緊張を覚え、手が震えたり、吐き気を催したりします。「自分の発言で相手を傷つけているのではないか」という加害者意識を持つ人もいます。
- 視線恐怖症: 人の視線が気になり、常に緊張した状態が続きます。人と目が合うのを恐れるあまり、電車やバスに乗れなくなることもあります。
- 赤面恐怖症: 人前で話すときなどに顔が赤くなることを極度に恐れます。顔が赤くなることで、自分の感情を見透かされたように感じ、恥ずかしい思いをします。
- 醜形恐怖症(身体醜形障害): 自分の容姿に強い思い込みを抱き、「醜い」と感じてしまう症状です。これは社交不安障害の一部ではなく、強迫症関連障害に分類されますが、対人恐怖と関連して悩みが強くなることもあります。
- 自己臭恐怖症: 自分の体から不快な臭いがしていると思い込む症状です。実際には臭いがなくても、「嫌われているのではないか」という不安に駆られます。
2.広場恐怖症
広い場所が怖いという意味ではなく、パニック発作を起こした経験から、「助けを求められない場所」「すぐに安全な場所に移動できない場所」を避けるようになる恐怖症です。
特に電車やバス、人混みなどに恐怖を抱きやすく、一人で外出できなくなることもあります。ひどい場合は、家に引きこもりがちになり、社会生活が困難になります。
3.特定恐怖症
特定の対象や状況に対して、不合理な恐怖を抱く恐怖症です。女性の発症率は男性の3倍と言われています。
- 高所恐怖症: 高い場所に恐怖を感じる。
- 閉所恐怖症: エレベーターやトンネルなどの狭い空間に恐怖を感じる。
- 動物恐怖症: 特定の動物(ヘビやクモ、犬など)に異常な恐怖を感じる。
- 嘔吐恐怖症: 自分や他人が嘔吐することに極度の恐怖を感じる。
- 先端恐怖症: 注射針やナイフなど、尖ったものに恐怖を感じる。
この他にも、飛行機恐怖症、会食恐怖症、歯科恐怖症など、200種類以上の特定恐怖症が存在すると言われています。
4.疾病不安症(旧称:心気症)
自分が重い病気にかかっているのではないか、または将来かかるのではないかという強い不安を抱く状態です。DSM-5では「不安症群」の中に独立した診断として位置づけられています。
- 細菌恐怖症: 周囲に細菌がうようよいるように感じ、不潔なものに触れることを恐れます。潔癖症と呼ばれる状態に陥ることもあります。
- がん恐怖症: 些細な身体の不調でも「がんではないか」と疑い、病院を転々とします。
- 不潔恐怖症: 公衆トイレや電車のつり革が触れなかったり、何度も手を洗ったりする症状です。
恐怖症(恐怖症性障害)の原因を探る
なぜ、恐怖症(恐怖症性障害)を発症してしまうのでしょうか? その原因は、いくつかの要因が複雑に絡み合っていると考えられています。
1.過去のトラウマ体験
幼少期の強烈な体験が、恐怖症の引き金になることがあります。例えば、犬に追いかけられた経験が、大人になってからの動物恐怖症につながるケースです。脳は強いショックを記憶し、似たような状況に直面すると、過去の恐怖を再現してしまうのです。
2.性格・気質
劣等感が強い、自己主張が苦手、臆病といった性格的な特徴も関係しています。自分に自信が持てない人は、恐怖の対象に立ち向かうことが難しく、余計に恐怖心を増大させてしまいます。
3.育った環境
機能不全家族など、安心感が得られない家庭で育った場合、常に不安を抱えながら生活することになります。このような環境で育つと、「~したらどうしよう」という不安に囚われやすくなり、恐怖症を発症するリスクが高まると言われています。

恐怖症克服への第一歩:正しい捉え方を身につける
恐怖症(恐怖症性障害)は、単なる気の持ちようではありません。しかし、その根底にある「ものの捉え方」を変えることで、症状を和らげ、克服へと向かうことができます。
恐怖症(恐怖症性障害)を抱える人の多くは、「この恐怖心は不合理だ」「こんなことで怯えている自分は恥ずかしい」と自分を責めてしまいがちです。頭では理解しているのに、身体がついてこない。このギャップが、さらなる苦しみを生み出します。
大切なのは、「不安や恐怖は、生きる上で欠かせない自己防衛本能だ」と理解し、「受け入れる」ことです。
恐怖心を感じている自分を否定するのではなく、「今は怖いと感じているんだな」とありのままの感情を認めることが、克服への第一歩となります。
カウンセリングという選択肢

「専門家との対話」
恐怖症(恐怖症性障害)を一人で克服するのは、非常に困難です。そんな時に頼りになるのが、専門家によるカウンセリングです。
大阪聖心こころセラピーでは、あなたの悩みに寄り添い、恐怖症からの脱却をサポートします。
認知行動療法で心の癖を治す
恐怖症(恐怖症性障害)を克服するための効果的なアプローチの一つが、認知行動療法です。
認知行動療法とは、ものの捉え方(認知)と行動パターンに働きかけ、思考の偏りを修正していく心理療法です。「自分がどう思われているか」という不安や、「~したらどうしよう」という予期不安など、恐怖症の根源となる考え方の癖にアプローチすることで、自己肯定感を高め、症状を改善していきます。
催眠療法(ヒプノセラピー)で潜在意識に働きかける
また、当オフィスでは、催眠療法(ヒプノセラピー)も取り入れています。
ヒプノセラピーは、リラックスした状態で潜在意識に働きかけることで、心の奥底にあるトラウマや劣等感、自信のなさといった根本原因を探り、癒していくことを目指します。
恐怖症(恐怖症性障害)は、過去の経験や、無意識のうちに形成された考え方によって引き起こされていることが少なくありません。ヒプノセラピーは、意識の奥深くに潜む問題にアプローチし、根本からの解決を図ります。
悩みを抱えているあなたへ

「心の安らぎ」
恐怖症(恐怖症性障害)は、決して恥ずかしい病気ではありません。多くの人が、知らず知らずのうちにこの病気に苦しんでいます。
「もしかしたら自分も恐怖症かもしれない」
「このままでは社会生活が送れない」
もしあなたがそんな不安を抱えているなら、一人で悩まず、専門家にご相談ください。
「大阪聖心こころセラピー」は、恐怖症(恐怖症性障害)の克服法を心得ています。私たちがあなたの悩みに寄り添い、共に解決の糸口を探していきます。
「大丈夫」と頭で分かっていても、心がついていかない。そのつらい気持ちを、私たちにお聞かせください。
恐怖症(恐怖症性障害)の種類をより深く知る
ここからは、さらに細かく恐怖症(恐怖症性障害)の種類を解説していきます。
社会恐怖症に付随する恐怖症
スピーチ恐怖症
人前で話すことに対して強い不安や恐怖を感じる症状です。声が震えたり、言葉に詰まったりするだけでなく、過剰な発汗や動悸などの身体症状を伴います。
電話恐怖症
電話をかける、あるいは電話に出ることに対して強い不安を抱く症状です。電話口でのやりとりを想像するだけで緊張し、手が震える人もいます。
男性恐怖症・女性恐怖症
特定の性別の人と接することに対して、強い恐怖を感じる症状です。過去のトラウマ体験が原因となることが多いとされています。
広場恐怖症に付随する恐怖症
外出恐怖症
広場恐怖症と似ていますが、外出そのものに強い不安を感じ、家から出られなくなる症状です。買い物や通院など、必要に迫られても外出できず、生活に大きな支障をきたします。
乗り物恐怖症
飛行機や電車、バス、自動車など、特定の乗り物に乗ることに対して強い不安や恐怖を抱く症状です。「飛行機恐怖症」「電車恐怖症」など、細かく分類されることもあります。
特定恐怖症の様々な例
ピエロ恐怖症(道化師恐怖症)
サーカスなどに登場するピエロに対して、極度の恐怖を感じる症状です。厚化粧で表情が読み取れない、予測不能な動きをする、といった点が恐怖の要因とされています。
会食恐怖症
人と一緒に食事をすることに、極度の緊張を感じる症状です。「うまく食べられなかったらどうしよう」「変な食べ方だと思われたらどうしよう」といった不安から、食事が喉を通らなくなってしまいます。
歯科恐怖症
歯医者での治療や麻酔に強い恐怖を感じる症状です。恐怖心から通院を避けてしまい、虫歯や歯周病が悪化してしまうケースも少なくありません。
嘔吐恐怖症
自分だけでなく、他人が嘔吐することに対しても極度の恐怖を抱く症状です。「どこかで誰かが吐くのではないか」という不安から、人混みを避けたり、外食を控えたりするようになります。
音恐怖症
突発的な音や、大きな音に対して極度の恐怖を覚える症状です。例えば、工事現場の音や、サイレンの音などに強い恐怖を感じ、不安を抱えたまま生活することになります。
腹鳴り恐怖症
お腹が鳴ることに強い不安や恐怖を感じる症状です。「お腹が鳴ったら周りに聞かれてしまう」という不安から、静かな場所を避けたり、人と食事をすることを避けたりするようになります。
狭所恐怖症・脇見恐怖症
狭い空間に恐怖を感じる「狭所恐怖症」や、人をちらっと見ることで相手に不快感を与えていると思い込む「脇見恐怖症」も、特定恐怖症の一つです。
疾病恐怖症に付随する恐怖症
細菌恐怖症・不潔恐怖症
自分が細菌に感染することを恐れ、過剰な手洗いや消毒を繰り返す症状です。完璧主義な性格の人に多く、潔癖症を誘発することもあります。
がん恐怖症
がんを極度に恐れ、少しでも体調が悪いと「がんではないか」と疑って病院を転々とします。検査で問題がないと診断されても納得できず、精神的に追い詰められてしまいます。
恐怖症克服の具体的なステップ

「日常の小さな一歩」
1.自己理解を深める
まずは、自分がどんな恐怖症(恐怖症性障害)を抱えているのか、その症状やトリガー(きっかけ)を客観的に観察してみましょう。日記をつけるなどして、自分の心の状態を記録するのも有効です。
2.認知の歪みを修正する
「~だったらどうしよう」というような、現実的でない不安や恐怖を、論理的に見つめ直す練習をします。例えば、「人前で話すときに赤面したらどうしよう」という不安を感じたら、「赤面したからといって、誰もあなたのことを責めたりしない」といった、より現実的な考え方に修正していきます。
3.スモールステップで行動を変える
いきなり恐怖の対象に立ち向かうのは危険です。まずは、ごく小さなことから行動を変えていきましょう。例えば、閉所恐怖症であれば、「エレベーターに1階分だけ乗ってみる」といった、安全な環境で成功体験を積み重ねていきます。
さいごに

「克服への希望」
恐怖症(恐怖症性障害)は、日常生活を苦しくする厄介な病気ですが、適切なサポートとアプローチによって克服できる可能性があります。
恐怖や不安に飲み込まれそうになったとき、思い出してください。あなたは一人ではありません。私たちがあなたの心の支えとなり、克服への道のりを共に歩んでいきたいと願っています。
あなたの悩みに寄り添い、最適なサポートを提案いたします。いつでもお気軽にご相談ください。
恐怖症(恐怖症性障害)のご相談は大阪聖心こころセラピーへ。
◆関連記事 大人の愛着障害 親子問題・親子関係 不安症 パニック障害
参考文献・参考資料
- 笠原敏彦(2005)『対人恐怖と社会不安障害―診断と治療の指針』 金剛出版
- 坂野雄二・丹野義彦・杉浦義典(編)(2006)『不安障害の臨床心理学』 東京大学出版会

