大阪の虐待トラウマ|心の傷の回復支援 幼少期の悲しみを癒し自分の人生を掴む

虐待の専門カウンセリング|臨床心理士・公認心理師が解決に導きます
虐待専門カウンセリング
臨床心理士・公認心理師
が解決に導きます
虐待という言葉には広い意味が含まれています。もっとも注目されやすいのは「親から子への虐待」ですが、それだけではありません。夫婦間におけるドメスティック・バイオレンス(DV)や、言葉や態度による相手の尊厳を傷つける行為も虐待に含まれます。 虐待を行う背景には、強いストレス、未解決のトラウマ、対人関係の不全、社会的孤立など複数の要因が関わることが多いと考えられます。加害者を一概に病理化するのではなく、その行為の背景を理解し、支援の中で改善を目指すことが重要です。
関連性のあるテーマ
当カウンセリングは、診断や治療といった医療行為を行うものではありません。臨床心理士や公認心理師といった専門資格を持つカウンセラーが、認知行動療法などの心理療法を用い、様々な問題で悩む方々に対し、ご自身の心と向き合い、不安のメカニズムを理解し、日常生活をより穏やかに過ごすための専門的なサポートを提供します。
本記事は、アメリカ精神医学会(APA)が発行する『DSM-5-TR:精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版 改訂版』に基づき、臨床心理士が専門的知見のもとに執筆・監修しています。本内容は診断や医療行為を目的としたものではなく、カウンセリングにおける理解を深めるための情報提供としてご利用ください。
あなたも無関係ではない、身近な虐待の問題

「疲労と孤立」
虐待は、私たちの心に深く刻まれる問題です。テレビや新聞で報じられる悲しい事件に、怒りや憤りを感じつつも、どこか遠い世界の話だと感じている方も少なくないかもしれません。しかし、実は虐待はもっと身近なところで起こっている可能性をはらんでいます。特に、子育て中の親御さんが抱えるストレスや悩みは、知らず知らずのうちに「しつけ」の境界を越え、子どもを深く傷つけてしまうことがあります。
この記事では、虐待がなぜ起こるのか、その心理的な背景から、連鎖を断ち切るための具体的なアプローチまで、専門的な知見を交えながら分かりやすく解説します。
虐待とは何か、その多様な形を知る

「親子の微妙な関係性」
誰もが直面しうる「虐待」という名の暴力
虐待とは、自分の保護下にある弱い立場の人や動物に対して、肉体的または精神的な苦痛を与える行為を指します。その対象は子ども、高齢者、動物、そしてパートナー(DV)と多岐にわたります。ニュースで取り上げられるような凄惨な事件だけでなく、私たちの身近な家庭でも、見過ごされがちな「軽度・中度の虐待」が頻繁に起こっている可能性があります。
たとえば、「疲れている時につい子どもにきつく当たってしまう」といった経験は、親であれば誰もが一度は感じたことがあるのではないでしょうか。特に、子育ての大半を担う母親は、そのプレッシャーやストレスから、無意識のうちにしつけの域を超えてしまうことがあります。実は、父親による虐待よりも母親による虐待件数が多いという事実は、こうした背景が深く関係していると考えられます。
しつけと虐待の境界線はどこにある?
日本では、かつて家庭や学校で「しつけと称した体罰」が日常的に行われていた歴史があります。そのため、今なお「どこまでがしつけで、どこからが虐待なのか」という境界線が曖昧になっているのが現状です。しかし、この線引きは非常にシンプルです。もし、子どもやパートナーが耐え難い苦痛を感じているのであれば、それはもはや「虐待」と言えるのです。
たとえば、次のような思いを抱いたことはありませんか?
- 「我が子にしていることは、もしかしたら虐待かもしれない」
- 「虐待とまではいかなくても、子どもの心を傷つけているのではないか」
- 「つい感情的に怒ってしまい、後で激しい自己嫌悪に陥る」
もし一つでも当てはまるなら、それはあなたが子どもを深く愛している証拠です。そして、その苦しみを一人で抱え込まず、専門家に相談することで、健全な親子関係を取り戻す第一歩を踏み出すことができます。
幼少期の虐待経験は、現在の対人関係や心の状態に大きく影響します。関連内容は親子問題・親子関係をご覧ください。
さらに、虐待による心の傷は、大人になってからの生きづらさに深くかかわってきます。詳しくはアダルトチルドレンをご参照ください。
子どもに対する虐待の種類と特徴を理解する
子育て中の親が抱えるストレスが子どもに向けられることで起こる虐待は、殴ったり蹴ったりする身体的暴力だけではありません。虐待は主に次の4つに分類されます。
1. 身体的虐待:見えやすい傷と見過ごされやすい親の思い込み
身体的虐待とは、殴る、蹴る、叩くといった行為で、子どもに肉体的な苦痛や怪我を負わせるものです。この種の虐待は、外傷や子どもの不自然な態度から周囲に気づかれやすいという特徴があります。
しかし、日本で最も多い虐待がこの身体的虐待である一方で、「これは厳しいしつけだ」と親自身が思い込んでいるケースも少なくありません。親は「子どものため」と信じていても、子どもが恐怖を感じ、心が傷ついているのであれば、それはまぎれもなく虐待です。
2. 性的虐待:外からは見えにくい心の闇
性的虐待は、実の親や義理の親、教師など、子どもを守るべき大人たちが性的な行為を行ったり、性的な欲求を満たそうとするものです。身体的虐待と違い、外傷がないため発見が難しく、子どももその事実を口にするのをためらう傾向が強いため、最も発覚しにくい虐待の一つです。
子どもを性的な対象とする行為は、権力関係の乱用や、未解決の問題を背景にした深刻な加害行為であり、子どもの心身に長期的な影響を及ぼします。親は、常に子どもたちの安全を守るために、警戒を怠らないことが重要です。
3. ネグレクト(育児放棄):見えない心の飢餓
ネグレクトとは、食事を与えない、身の回りの世話をしない、会話をしないなど、親としての責任を放棄し、子どもを放置することです。これは、自分の欲求を満たすために子どもを利用する虐待とは異なり、「世話をしなければ」と頭では分かっているのに、精神的な疲労などから育児ができなくなることで起こります。
身体的虐待の次に多いネグレクトは、外からは分かりにくいのが特徴です。たとえば、
- 家庭内で会話が少ない
- 家族で外出することがほとんどない
- 親から愛情を注がれた実感が少ない
といった「準ネグレクト家庭」で育った子どもは、自分が親になった時にも同じような傾向を示し、負の連鎖を繰り返してしまうことがあります。
4. 心理的虐待:言葉の刃が深く突き刺さる
心理的虐待とは、言葉による脅しや、子どもの自尊心を傷つけるような発言、他の兄弟との差別的な扱いなど、精神的な苦痛を与える行為です。家庭内DV(ドメスティックバイオレンス)は、心理的虐待と密接に関係しています。
たとえば、子どもが目の前で両親の激しい口論や暴力を見たり、隣の部屋から聞こえる怒鳴り声を聞くだけでも、子どもは精神的に深い傷を負います。こうした大人のストレスや憎悪が、直接的・間接的に子どもに向けられることで、健全な成長を妨げてしまうのです。
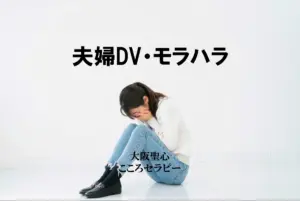
なぜ虐待は起こるのか?その心理的背景

「心理的な苦悩」
ストレスと孤立が引き起こす虐待の連鎖
虐待の発生には、家庭の状況が大きく関係しています。夫婦間の不仲、経済的困難、仕事のストレスなど、様々な要因が家庭内の不安やイライラを増幅させます。
「ゆっくり休みたい時に子どもが泣き出した」「仕事で疲れ果てて、子どもと向き合う余裕がない」といった状況では、つい感情的になったり、ネグレクトに発展してしまうことが多くあります。
また、未だに「夫は仕事、妻は家庭」という性別役割分担の意識が根強く残る日本では、子育ての負担が妻に偏りがちです。夫からの労いがなかったり、シングルマザーの増加、地域社会との関係の希薄化など、母親がストレスを抱え込みやすい社会構造が、子どもへの虐待につながってしまうのです。
親から子へ引き継がれる負の連鎖
「虐待は連鎖する」と言われるように、虐待をする親の多くは、自身も幼少期に虐待を受けてきた経験があります。虐待を当たり前のように見て育つと、それが物事を解決する手段だと無意識に学んでしまい、自分の子どもにも同じことを繰り返してしまうのです。
幼少期に親から十分な愛情を感じられなかった人は、親に対する不満や怒りを抱えたまま大人になります。子育てが始まると、その辛い記憶や感情が刺激され、虐待へ走ってしまうと考えられています。
このような親にとって、子どもは「自分の欲求を満たすための存在」になりがちです。思い通りにならない子どもに対して、過剰な苛立ちや暴力を振るってしまうのは、愛情不足による心の空虚感が原因となっているのです。
虐待が子どもに残す深い傷
虐待という過酷な体験は、子どもの心に重大なダメージを与えます。
- 睡眠障害や無気力、多動といった精神的な問題
- 社会不安障害やうつ病、摂食障害など、大人になってからの様々な心の病気
- 「自分には価値がない」という自己評価の低さ
- 他人への強い不信感
虐待を受けた子どもは、無条件に愛されなかったという思いから、自己肯定感を持つことが難しくなります。その結果、人間関係を築くのが苦手になったり、生きづらさを感じながら生きていくことになるのです。
虐待を防ぐための心理学的なアプローチ
1. 母親が抱える心身のバランスの崩れを自覚する
日々、仕事や家事、育児に追われる母親は、心身ともに疲労困憊していることが多いものです。「なぜこんなにも疲れているんだろう」と感じた時、それは自分のコンディションが悪いサインかもしれません。
無理をして頑張り続けるのではなく、「今日はちょっと体調が悪いから、ごめんね」と子どもに伝え、少し距離を置くことも大切です。母親が心に余裕を持つことが、子どもへの穏やかな接し方につながります。
2. 「自分の時間」を意識的に確保する
子育ては、自分の時間がほとんどないと感じるほど、子どもにつきっきりになりがちです。しかし、疲れている時や、他にもやらなければならないことがある時に、子どもが思い通りに動いてくれないと、つい強く叱ってしまうことがあります。
完璧にこなそうとせず、自分のための時間を意識的に確保しましょう。たとえば、夫や家族に子どもを預けて一人で外出したり、気分転換に好きなことをしたりするだけでも、心の余裕は生まれます。
虐待の連鎖を断ち切るための具体的な方法
1. 完璧を目指さない「ゆるやかな子育て」のすすめ
「母親になったからには頑張らなければ」「子育てはこうあるべき」といった理想論に縛られていませんか?しかし、育児書通りに子どもが育つわけではありません。
子どもは、親の思い通りにならないのが普通です。完璧な親を目指すのではなく、「今日ご飯を食べて元気に過ごしてくれたら100点!」くらいの気持ちで、おおらかに構えることが大切です。
完璧主義を手放し、「テキトー」なくらいがちょうど良いのです。子どもの個性やペースを尊重することで、イライラが減り、親子関係がより良いものになります。
2. 夫婦で子育てに向き合う時間を増やす
子育ては一人で行うものではありません。仕事で忙しいお父さんにも、積極的に育児に参加してもらいましょう。お父さんが子どもと関わる時間が増えれば、母親の負担が減るだけでなく、子どももお父さんとの絆を深めることができます。
その際、お父さんのやり方に口を出しすぎないことも大切です。子育てには様々なやり方があります。お互いの意見を尊重し、コミュニケーションを密に取ることで、夫婦で支え合いながら子育てをしていくことができます。
3. 周囲の助けを求める勇気を持つ
一人で子育ての悩みを抱え込まず、誰かに頼ることも重要です。姉妹や地域の育児サークルなど、悩みを話せる相手を見つけるだけで、気持ちが楽になることがあります。
子どもと二人きりの閉鎖された環境にいると、どうしても気が滅入ってしまいがちです。孤独を感じた時には、「一人で無理をしない」という勇気を持って、行政の育児相談や専門機関を頼るようにしましょう。
虐待の根本にある心理を見つめ直す
「親にされたことを子にしてしまう」という無意識の連鎖
「自分も子どもの頃、親にされてきたことを、いつの間にか自分の子どもにもしている」というケースは少なくありません。これは、虐待を「普通のこと」と無意識のうちに感じてしまっているためです。
しかし、あなたも、そしてあなたの子どもも、本当はもっと愛され、大切にされるべき存在です。自分が受けた虐待の記憶が、無意識の内に自分の行動を支配していることに気づき、その連鎖を断ち切ることが、健全な親子関係を築くための第一歩となります。
「子どものため」は本当に「誰のため」?
「野菜を食べなさい」「お菓子はダメ」といった、子どもの健康を気遣う気持ちは大切です。しかし、あまりにも完璧にやろうとすると、家族との間に摩擦が生じることがあります。
「子どものため」と信じていても、それが自分の完璧主義を満たすためになってしまっていないか、今一度考えてみましょう。少し柔軟に考え、周りの人に子育てのルールを押し付けないことも、家族みんなが笑顔で過ごすために必要なことです。

一人で苦しむ前に、カウンセリングという選択を

「回復と癒し」
虐待をする親が抱える深い苦悩
虐待は、される側だけでなく、する側もまた深い罪悪感と自己嫌悪に苛まれます。「どうしてまた怒ってしまったんだろう」と、夜な夜な子どもの寝顔を見ながら反省する親御さんは、決して少なくありません。
中には、虐待を「しつけの一環」や「当然のこと」と誤って信じてしまう人もいます。そのような方は、自分の行動が間違っていると認識していないため、改善が難しい場合があります。
一方で、「虐待の後に激しい自己嫌悪に陥る」方は、間違いなく改善が可能です。なぜなら、その行為が「本来の自分らしくない行為」だと、心の奥底で感じているからです。
聖心こころセラピーが提供する安心のサポート
幼い頃の体験によって形成された「虐待につながりやすい心の反応」は、カウンセリングを通じて理解し直し、少しずつ変えていくことができます。聖心こころセラピーは、あなたが本来持っている「子どもを大切に育もうとする気持ち」を取り戻すための具体的な方法と対策を熟知しています。
カウンセリングを通じて、辛い記憶や感情を整理し、自分自身を深く理解することで、虐待のスイッチを捨て去り、穏やかな家庭と子どもの明るい未来を取り戻すことができます。
もし、あなたが今、一人で苦しんでいるのなら、どうか勇気を出して一歩踏み出してください。あなたの苦しみを誰かに話すことは、決して恥ずかしいことではありません。私たちは、あなたの辛い気持ちに寄り添い、サポートする準備ができています。
虐待に関するよくある質問と答え
- 子どもを虐待してしまう自分は、やはり母親として失格なのでしょうか?
-
決してそんなことはありません。虐待をしてしまうこと自体が、あなたが心に深い傷を負っている証拠です。母親としての愛情がないわけではなく、むしろ、子育てのプレッシャーや過去のトラウマから、本来の優しさや愛情を発揮できなくなっている状態だと言えます。
自分を責めるのではなく、まずはその苦しみを認めて、専門家に相談することで、心を解放し、本来の自分を取り戻すことができます。
- カウンセリングを受けることで、本当に虐待がなくなりますか?
-
はい、多くのケースで改善が見られます。カウンセリングは、虐待の根本原因となっている過去のトラウマや、現在のストレスを解消するためのサポートを行います。
「虐待のスイッチ」がどこにあるのかを特定し、そのスイッチを無効化することで、感情のコントロールがしやすくなり、子どもとの関係が健全なものへと変わっていくでしょう。
- どのような人がカウンセリングを受けるべきですか?
-
次のような思いがある方は、ぜひカウンセリングを検討してください。
- 「子どもに優しくしたいのに、つい感情的に怒ってしまう」
- 「怒った後に激しい自己嫌悪に陥り、自分を責めてしまう」
- 「子育てに疲れ、孤独を感じている」
- 「子どもの頃に親から虐待を受けていた」
これらの思いは、あなたが変化を求めているサインです。カウンセリングは、自分自身と向き合い、より良い未来を築くための強力なツールとなります。
虐待の連鎖を断ち切るために、今できること

「愛情と希望」
1. 自分の感情を客観的に観察する
怒りや苛立ちを感じた時、その感情にただ任せるのではなく、「なぜ自分は今、こんなに怒っているのだろう?」と一歩引いて考えてみましょう。感情の裏側にある、自分の本当の気持ちや満たされていない欲求に気づくことが、感情のコントロールにつながります。
2. 子どもを「自分の思い通りにならない存在」と受け入れる
子育ては、自分の思い通りにいかないことの連続です。子どもには、子どもなりの感性や考え方があり、それを尊重することが大切です。理想の育児を追い求めるのではなく、子どものペースに合わせ、成長を温かく見守ることで、心に余裕が生まれます。
3. 「完璧な親」という呪縛から解放される
子育てに完璧はありません。完璧主義を目指せば目指すほど、自分を追い詰め、子どもにも過度な期待をかけてしまいます。「今日はこれだけできたからOK」というように、自分を褒める基準を作り、小さな成功を積み重ねていきましょう。
4. 専門家という頼れるパートナーを見つける
もしあなたが、子育ての悩みや虐待の不安を一人で抱え込んでいるなら、どうか私たちにご相談ください。聖心こころセラピーは、あなたの気持ちに寄り添い、共に解決策を探していきます。
「助けて」と声を上げること、そして専門家の力を借りることは、決して弱さではありません。それは、あなた自身と、あなたの子どもの未来を守るための、最高の勇気ある行動なのです。
私たちが、あなたの「虐待のスイッチ」を取り除き、本来の温かい家庭を取り戻すお手伝いをします。
◆関連記事 親子問題・親子関係 アダルトチルドレン トラウマ PTSD
参考文献・参考資料
- 栗林恵美子(2022) 子ども虐待の予防に向けたしつけと虐待の境界に関する考察-養育者の養育行動と心理的要因に着目して-日本子ども虐待防止学会紀要 第41巻 第1号
- 菅野恵(2020) 児童虐待防止とメンタルヘルス-被虐待児と養育者のストレスに着目して- ストレス科学研究35 巻
- 藤野京子(2008) 児童虐待が後年の生活に及ぼす影響について 犯罪心理学研究 第46巻 第1号


