大阪の不眠症・睡眠障害|心理相談室 眠れぬ孤独と焦りを解き朝を迎える心へ
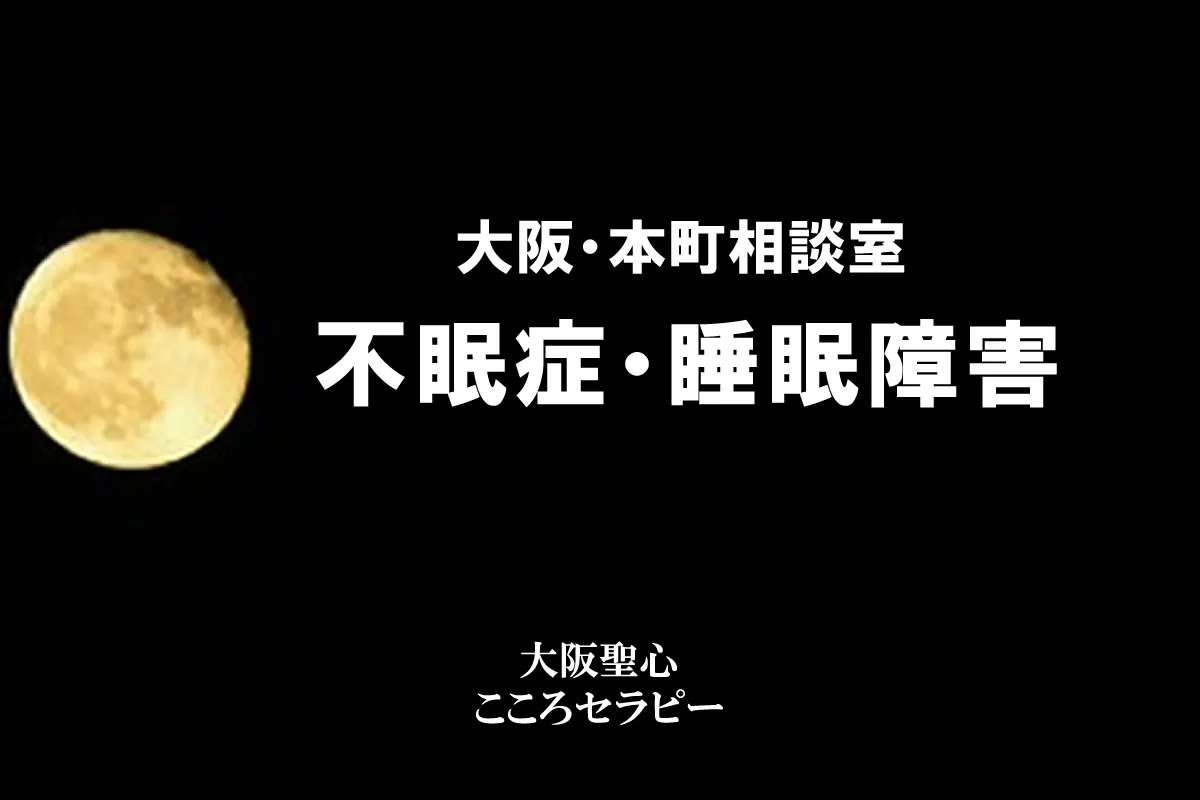
不眠症の専門カウンセリング|臨床心理士・公認心理師が解決に導きます
不眠症専門カウンセリング
臨床心理士・公認心理師
が解決に導きます
不眠症(睡眠障害)は、さまざまな要因が複雑に関わって起こります。心理的な不安やストレスが背景にあることも多いですが、それだけではなく、身体的な健康状態、服薬の影響、生活習慣や睡眠環境の問題などが関与する場合もあります。 「眠れないこと」への不安や焦りが強まると、さらに眠れなくなる悪循環に陥ることも少なくありません。 治療や改善には、環境調整、生活習慣の見直し、心理療法などが効果的であり、適切なサポートを受けることで改善が期待できます。
関連性のあるテーマ
当カウンセリングは、診断や治療といった医療行為を行うものではありません。臨床心理士や公認心理師といった専門資格を持つカウンセラーが、認知行動療法などの心理療法を用い、様々な問題で悩む方々に対し、ご自身の心と向き合い、不安のメカニズムを理解し、日常生活をより穏やかに過ごすための専門的なサポートを提供します。
本記事は、アメリカ精神医学会(APA)が発行する『DSM-5-TR:精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版 改訂版』に基づき、臨床心理士が専門的知見のもとに執筆・監修しています。本内容は診断や医療行為を目的としたものではなく、カウンセリングにおける理解を深めるための情報提供としてご利用ください。
眠れない夜の孤独から解放されませんか?
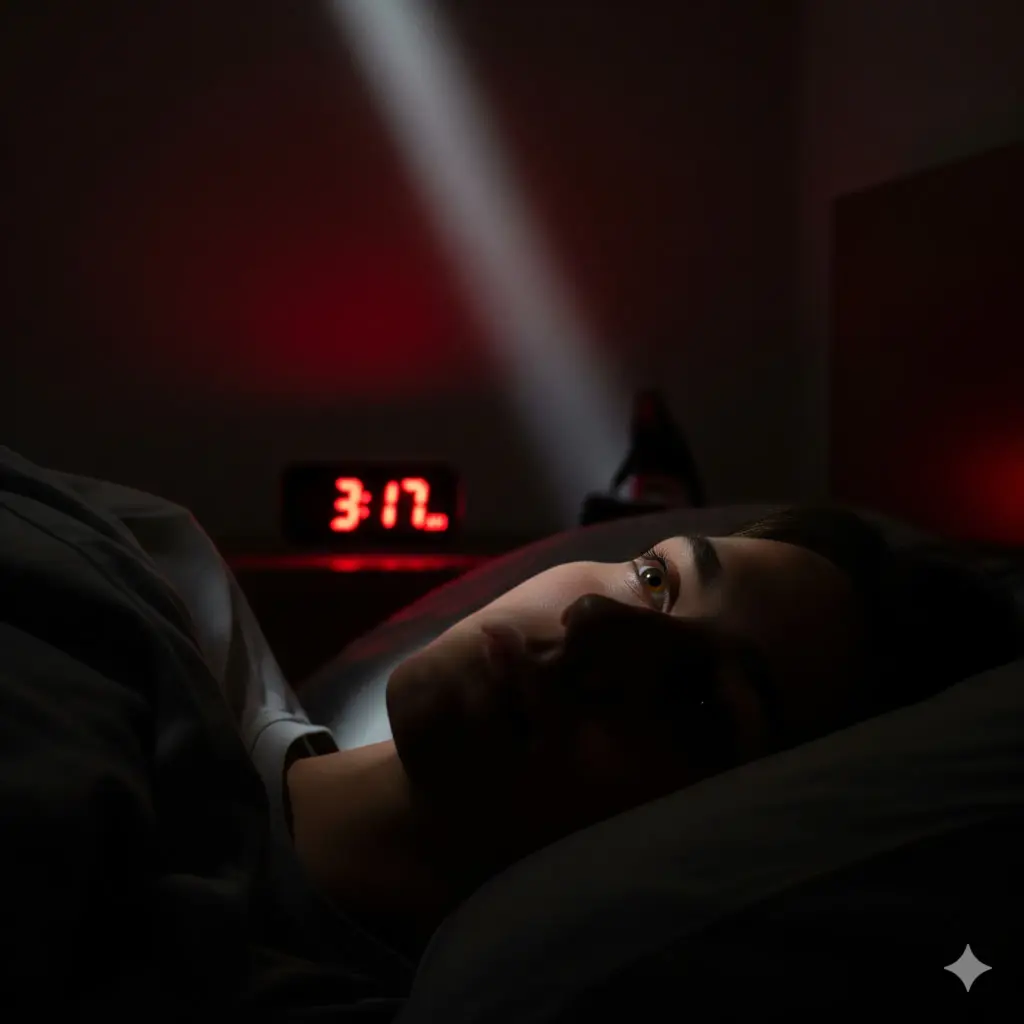
「孤独と不安」
「眠れない夜は何故こんなにも長いのだろう」
そう感じたことはありませんか? 誰もが眠りについているはずなのに、自分だけが世界に取り残されたような、あの恐ろしいほどの孤独感。静まり返った部屋に響く時計の針の音が、やけに神経を刺激する。
「眠りたい…眠れない…本当に朝が来るのだろうか…」
毎夜襲いかかるこうした恐怖は、もはや単なる寝つきの悪さではありません。それは、あなたの心身がSOSを発している証拠です。
不眠は多くの人が抱える悩みであり、決してあなただけが直面している問題ではありません。厚生労働省のデータによると、日本人の約21%、つまり5人に1人が睡眠に何らかの悩みを抱えていると言われています。
睡眠は、脳や身体の疲労を回復させ、免疫機能を強化するために不可欠です。不眠が続けば、日中の集中力が低下したり、倦怠感に襲われたりするだけでなく、居眠り事故や、内臓機能の低下といった深刻な事態につながる可能性もあります。
眠れない・浅い眠りなどの背景には、“安心の土台”となる愛着の問題が関係していることがあります。詳しくは大人の愛着障害をご覧ください。
さらに、慢性的な緊張状態は、幼少期の親子関係や家庭環境が影響していることもあります。親子問題・親子関係をご一読いただくことで、不眠への理解が深まります。
あなたの不眠はどのタイプ?4つの不眠症と原因
不眠症は、ただ「寝つけない」というだけでなく、さまざまなタイプに分けられます。まずは、あなたの不眠がどのタイプに当てはまるかを知ることから始めましょう。
1. 入眠障害:布団に入ってから30分以上眠れない
入眠障害は、不眠症の中で最も多いタイプです。布団に入ってもなかなか寝つけず、眠りにつくまでに30分以上かかる状態が続きます。一度眠ってしまえば朝まで眠り続けられるのが特徴です。
このタイプに陥りがちなのは、「今夜は眠れるだろうか」「眠れなかったらどうしよう」といった不安や焦りから、布団に入る前から緊張状態になってしまうケースです。こうした心理的な要因から引き起こされる不眠を、「精神生理性不眠症」と呼びます。
2. 熟眠障害:眠りが浅く、熟睡感が得られない
十分な睡眠時間を確保しているのに、「熟睡できた」という感覚がなく、朝起きても疲れが取れないタイプです。若い世代によく見られます。
このタイプは、眠りが浅く夢ばかり見ることが多いため、日中の集中力が散漫になったり、身体の倦怠感を抱えたりしやすくなります。周囲からは「やる気がない」「本気を出していない」と誤解されやすく、さらに悩みを深めてしまうケースも少なくありません。
3. 中途覚醒:夜中に何度も目が覚めてしまう
寝つきは良いのに、夜中に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか寝つけないのがこのタイプです。夜中に2回以上目が覚める状態が続きます。
特に女性に多く見られ、一度目が覚めるとその後の睡眠の質が著しく低下し、結果的に慢性的な睡眠不足につながりがちです。
また、「お酒を飲まないと眠れない」と安易にアルコールに頼ると、かえって中途覚醒を引き起こしやすくなるため注意が必要です。
4. 早朝覚醒:必要以上に早く目が覚めてしまう
午前4時や5時など、特に用事がないのに早く目が覚めてしまい、その後眠りにつくのが難しいタイプです。
これは、加齢によって睡眠に必要なホルモンであるメラトニンの分泌が減少することで起こる「加齢に伴う早朝覚醒」の場合と、うつ病やストレスなどの心理的な要因で引き起こされる場合があります。後者の場合、入眠障害や中途覚醒も併発しやすく、睡眠全体の質が低下しがちです。
不眠症の根源にあるのは「不安」という感情

「付きまとう不安感」
不眠の原因は、日々のストレスや不規則な生活、睡眠環境の変化など多岐にわたりますが、その根底にあるのは「不安」という感情です。仕事や将来のこと、家庭の問題など、日々頭の中を駆け巡るさまざまな心配事が、眠りを妨げる大きな要因となります。
しかし、多くの人がその不安に無自覚であったり、無意識に目を背けていたりするため、身体が不眠という形でSOSを出してしまうのです。
睡眠障害を抱える方の多くは、不眠の原因を「仕事が忙しいから」「疲れているから」と表面的な部分で理解しているものの、その根本にある「不安」には気づいていないことが少なくありません。
この不安を解消し、また一つのことを必要以上に思い悩む思考の癖を改善しなければ、根本的な解決にはつながりません。
睡眠薬に頼る前に試してほしい3つのこと

「心身の健康と活動的な生活」
不眠症の症状を訴えて病院を受診すると、多くの場合、睡眠薬が処方されます。しかし、薬だけで根本的な問題が解決するわけではありません。
むしろ、薬への依存や、日中の倦怠感、動作の緩慢さなど、新たな問題を引き起こす可能性もあります。ここでは、睡眠薬に頼る前に試してほしい、不眠症改善のための3つの方法をご紹介します。
1. 身体を動かして心地よい疲労感を
子供の頃は、毎日走り回ったり、身体を動かす時間が自然とありましたが、大人になると、仕事や家事に追われ、運動する機会が減りがちです。
適度な運動は、心地よい疲労感を生み、深い眠りにつながります。週末に家族で公園に出かけたり、軽い散歩を日課にしたり、気分転換を兼ねて身体を動かしてみましょう。特に、ウォーキングは気分を前向きにし、新しいアイデアが浮かぶことも多いため、おすすめです。
2. 就寝1時間前はデジタルデトックスを
スマートフォンやパソコンから発せられるブルーライトは、睡眠を促すメラトニンの分泌を抑制します。就寝前までSNSや動画サイトを見ていると、脳が興奮状態になり、眠りにつきにくくなります。
眠りの質を高めるために、就寝の1時間前にはスマホやパソコンを閉じて、部屋を薄暗くし、リラックスできる環境を整えましょう。
3. 完璧主義を手放して「なるようになるさ」の精神を
不眠症を抱える方の多くは、物事を必要以上に心配したり、完璧を求めたりする傾向があります。仕事や家庭の悩みについてあれこれと考え、眠れない夜を過ごしている方もいるのではないでしょうか。
しかし、夜中にいくら考えても、良い解決策にはたどり着きません。むしろ、ネガティブな思考が堂々巡りし、不安が増幅するだけです。
「なるようになるさ」という気持ちで、良い意味で物事を楽観的に捉えることも大切です。できる限りのことを精一杯やったら、後は自分を信じて「大丈夫」と心の中で唱えてみましょう。
心理療法で不眠症の根本原因を解決する

「カウンセリングや対話による心の解放」
不眠症の根本的な原因が、長年培われた思考の癖や性格にある場合、自己流の改善策だけでは限界があります。
「心配しすぎる」「過剰に不安を感じる」といった思考パターンを変えることは、一人ではなかなか難しいものです。そのような場合、専門家であるカウンセラーの力を借りるのも一つの有効な手段です。
認知行動療法:思考の歪みを修正する
不眠症治療に有効とされる認知行動療法は、不眠に関する考え方の歪みを修正していく心理療法です。
例えば、「一睡もできなかったら明日の仕事に差し支える」という考えを「少しでも眠れたらいい」「疲れているんだから仕方ない」というように、より現実的で建設的な考え方に変えていくことで、睡眠に対する過剰な意識や不安を軽減させることができます。
ヒプノセラピー:潜在意識に眠れる癖を浸透させる
ヒプノセラピー(催眠療法)は、潜在意識に働きかけ、思考や行動のパターンを変えていく心理療法です。
不眠症は、ストレスや不安が引き金となって「眠れない癖」がついてしまった状態とも言えます。ヒプノセラピーでは、深いリラックス状態の中で、潜在意識に「安心して眠れる自分」をイメージさせ、「眠れる癖」を浸透させていきます。
薬のように副作用の心配がなく、ご自身の内なる力を引き出すことで、自然で質の良い睡眠を取り戻すことを目指します。
克服事例:長年続いた不眠症を乗り越えたKさんのケース
仕事の疲労と家庭内のストレスから、不眠に悩んでいたKさんのケースをご紹介します。
Kさんは、日々の仕事に対する責任感や義務感、そして配偶者との関係に大きな精神的負担を感じていました。その結果、「どうにかして眠らなければ」という強迫観念に追い込まれ、不眠症はさらに悪化していました。
Kさんは、大阪聖心こころセラピーでのカウンセリングを経て、仕事や人間関係に対する考え方を根本から見直すことにしました。
認知行動療法で「ストレスを受けやすい思考」を刷新し、さらにヒプノセラピーを組み合わせることで、長年染みついた「不眠の癖」を改善していきました。
また、カウンセラーのアドバイスにより、毎週スポーツで身体を動かす習慣を取り入れ、適度な肉体疲労を得ることで、深く心地よい眠りにつくことができるようになりました。
結果、Kさんは仕事とプライベートの区別をつけられるようになり、それぞれ充実した時間を過ごせるように。不眠を克服しただけでなく、心身ともに健康的な生活を取り戻すことができたのです。
質の高い睡眠は、充実した人生の第一歩

「深い眠りとすがすがしい朝」
睡眠薬を飲み始めると癖になり、眠れないことが怖くなってしまい、さらに飲み続けるという負のサイクルに入る場合もあります。最近の睡眠薬にはホルモンバランスを調整することで身体への負担の少ないものも増えてきていますので、脳のホルモンバランスを調節することにより、自然な入眠に近づけていくことも可能です。
しかし現状は本人の日々の調子もまちまちであり、強過ぎたり足りなかったりと、薬での調整も難しく、朝起きた時の倦怠感を訴える方も多く存在します。そのように薬にも限界がありますので、それ以外にも不安を解消するためにセラピーなどを受けることもいいでしょう。
いろいろな心配が浮かんでくるのは、自分の考えがそのように堂々巡りしてしまう癖を持っていることも原因ですので、そういった思考パターンを変えていくことは有意義な行為です。
しかし、自分一人ではなかなか自分の根本にある考え方を変えることが難しく、不安が拭い切れない場合もありますので、そのような場合には、第三者の手を借りて、考え方を少しずつ不安のなくなる方向に変えていくこともいいでしょう。
◆関連記事 大人の愛着障害 親子問題・親子関係 不安症 パニック障害
参考文献・参考資料
- 田ヶ谷浩邦(2007) 不眠症薬物療法の臨床 日本薬理学雑誌 129巻 1号
- 綾部直子・三島和夫(2019) 睡眠障害と心理社会支援 精神保健研究 第65号
- アメリカ精神医学会(著),日本精神神経学会(監訳)(2023)『DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル テキスト改訂版』 医学書院


