全般性不安症カウンセリング
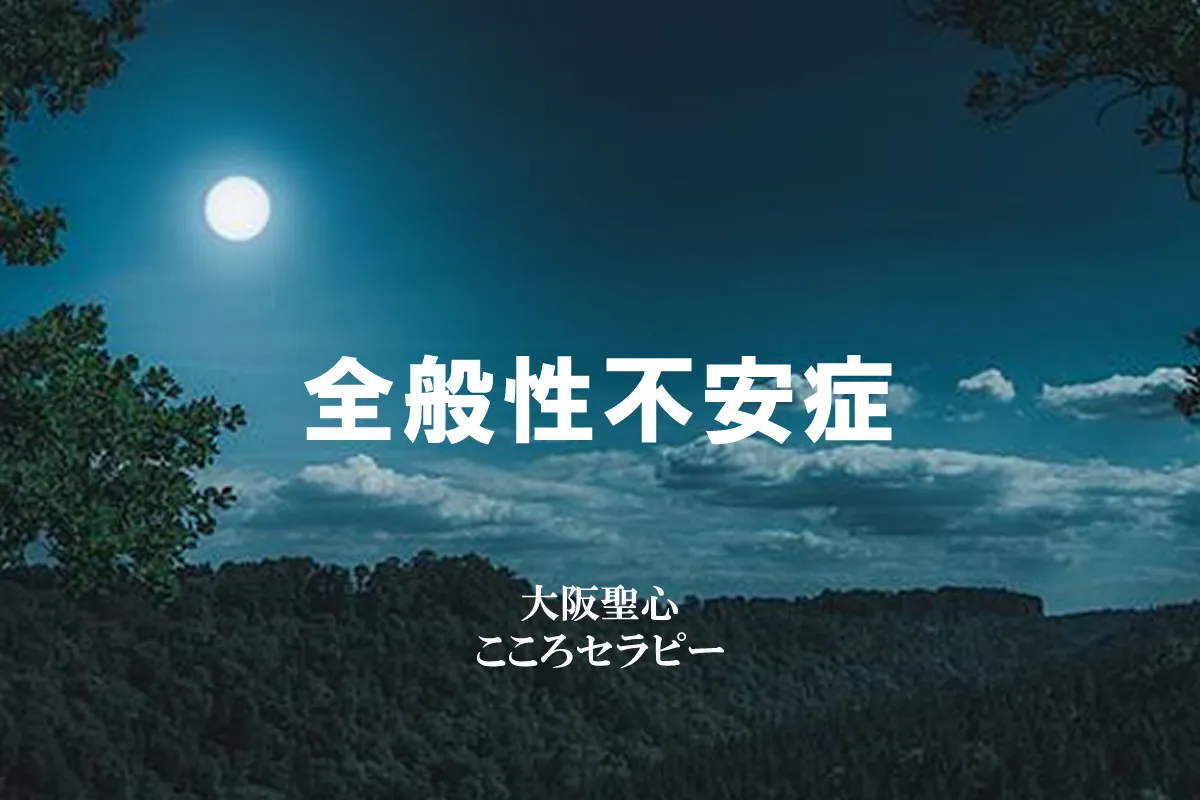
全般性不安症の専門カウンセリング|臨床心理士・公認心理師が解決に導きます
全般性不安症
専門カウンセリング
臨床心理士・公認心理師
が解決に導きます
全般性不安症(GAD)とは、明確な理由がないにもかかわらず、不安や心配が長期間続き、心や体に強い負担をもたらす状態を指します。頭から不安が離れず、リラックスできない状態が慢性的に続き、日常生活や社会生活に支障をきたすことがあります。単なる「心配性」や「考えすぎ」とは異なり、本人も過剰な不安であることを自覚しながらも、気持ちをコントロールできないのが特徴です。睡眠障害や慢性的な疲労感、集中困難、筋肉の緊張、消化器症状など、心身の両面に症状が現れることが少なくありません。
関連性のあるテーマ
当カウンセリングは、診断や治療といった医療行為を行うものではありません。臨床心理士や公認心理師といった専門資格を持つカウンセラーが、認知行動療法などの心理療法を用い、様々な問題で悩む方々に対し、ご自身の心と向き合い、不安のメカニズムを理解し、日常生活をより穏やかに過ごすための専門的なサポートを提供します。
本記事は、アメリカ精神医学会(APA)が発行する『DSM-5-TR:精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版 改訂版』に基づき、臨床心理士が専門的知見のもとに執筆・監修しています。本内容は診断や医療行為を目的としたものではなく、カウンセリングにおける理解を深めるための情報提供としてご利用ください。
終わりなき不安のトンネルを抜けて
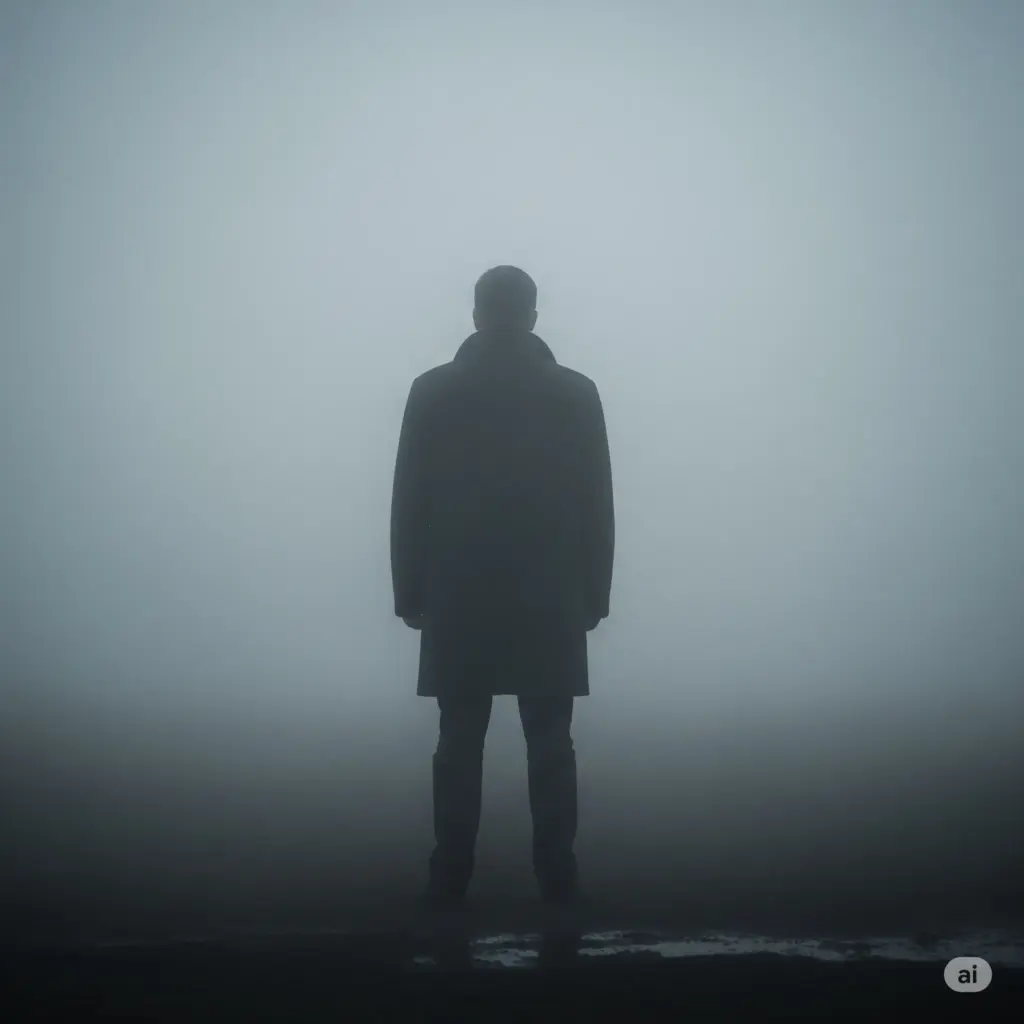
「漠然とした不安」
「不安」は誰もが感じる感情、でもその種類は様々です
私たちは誰でも、多かれ少なかれ不安を感じながら生きています。それは、将来のキャリア、人間関係、健康、経済的な問題など、人生のあらゆる場面で起こり得ます。この不安という感情は、本来、危険を察知し、身の安全を守るための大切なサインです。たとえば、初めての場所に行くときに道に迷わないか不安になったり、プレゼンを控えて緊張したりするような「一時的な不安」は、私たちがより良い準備をするための原動力となります。こうした不安は、問題が解決すれば自然と消えていくものです。
しかし、もしその不安が、特別な原因もないのに毎日続き、いつまでも消えないとしたらどうでしょうか。頭の中から心配事が次から次へと湧いてきて、心が休まる暇がない。常に緊張して、リラックスすることができない。このような状態は、単なる「心配性」とは根本的に異なります。この状態が慢性的に続くことを、私たちは「全般性不安症(Generalized Anxiety Disorder:GAD)」と呼びます。
全般性不安症とは?
全般性不安症は、特定の対象がないのに過剰でコントロール不能な不安や心配が、長期間にわたって続く心の状態です。不安を感じている当事者は、自分の不安が過剰であると理解しているにもかかわらず、その気持ちを止めることができません。
例えば、「明日、会議で失敗したらどうしよう」という不安は誰でも感じることがあります。しかし、全般性不安症を抱えている人は、「明日、会議で失敗したら、きっと会社で評価が下がるだろう」「評価が下がれば、プロジェクトから外されるかもしれない」「そうなれば、昇進もできず、リストラの対象になるかもしれない」「そうなると、家族を路頭に迷わせてしまう」といったように、一つの小さな心配が連鎖的に大きな不安へと膨らんでいき、最終的に最悪の事態を想像してしまいます。
そして、この不安は特定の状況や出来事だけでなく、日常の些細なことに対しても向けられます。たとえば、子どもが友達と遊んでいるだけで「何かトラブルに巻き込まれていないか」「怪我をしていないか」と不安になり、常に子どものことが心配で頭から離れません。この状態が数カ月、時には数年と続き、日常生活に大きな支障をきたすようになります。
補足:以前には「不安神経症」もしくは「全般性不安障害」と呼ばれていましたが、最近では「全般性不安症」が正式名称として使用されるようになりました。
理由のない不安や心配が続く背景には、幼少期の愛着不安が影響している場合があります。関連する内容は大人の愛着障害をご覧ください。
また、過度な心配性は、幼少期の親子関係の影響を色濃く受けていることがあります。親子問題・親子関係について知ることで、全般性不安症を理解する一助となります。
全身に現れる不安のサイン

「不安と孤独」
全般性不安症が厄介なのは、それが単なる「心の状態」にとどまらないことです。過剰な不安は、自律神経に影響を与え、やがて全身に様々なサインとして現れます。これは、脳が常に危険を感じているため、体が「戦闘モード」に入り続けている状態だからです。
- 身体的サイン
- 慢性的な疲労感や倦怠感: ぐっすり眠ったはずなのに疲れが取れない。一日中体がだるく、何もやる気が起きない。
- 筋肉の緊張: 特に首や肩の筋肉が常にこわばっている。その結果、ひどい頭痛や肩こりに悩まされる。
- 睡眠障害: なかなか寝付けない、夜中に何度も目が覚める、眠りが浅いなど、睡眠の質が低下する。
- 消化器系の不調: 便秘や下痢を繰り返す、胃の不快感、腹痛など。
- 自律神経系の症状: 動悸、息切れ、めまい、発汗、手足の震え、胸の圧迫感など。
- その他: 口の渇き、吐き気、頻尿、風邪をひきやすいなど。
- 精神的・行動的サイン
- 集中力の低下: 物事に集中できず、仕事や勉強が手につかない。
- 記憶力の低下: 大切な約束を忘れたり、人の名前が思い出せなくなったりする。
- イライラや落ち着きのなさ: 常にソワソワして、イライラしやすくなる。些細なことで感情が爆発してしまう。
- 回避行動: 不安を感じる状況や場所、人間関係を避けるようになる。
- 物事の継続困難: 何を始めても、途中で投げ出してしまう。
- 他人との交流を避けるようになる: 人に会うのが億劫になり、家に引きこもりがちになる。
これらのサインが複数現れ、6カ月以上続いている場合、全般性不安症である可能性が高いです。もし心当たりのある方は、放置せずに専門家へ相談することを検討しましょう。早期に対処することで、症状の悪化を防ぎ、元の穏やかな日常を取り戻すことができます。
全般性不安症の背景にあるもの

「親子関係や家族関係の影響も」
誰がなりやすい?
全般性不安症は、パニック障害よりも経験者が多いとされています。実は、日本人の約5%がこの症状に悩んでいるという統計もあります。この数字は、およそ100人に5人という計算になります。
性別で見てみると、男性よりも女性に多く見られます。また、発症しやすい年齢は、10代から20代にかけて、そして30代にも少なくありません。
なぜ女性に多いのでしょうか?その背景には、女性特有の身体的、社会的要因が関係していると考えられています。女性は男性に比べて、ホルモンバランスの変化が大きく、それが自律神経の乱れにつながりやすいという特徴があります。また、結婚、出産、育児、介護など、人生の大きな変化が重なりやすく、そのストレスやプレッシャーが不安を増幅させる要因になることがあります。
育ってきた環境も関係する?
性格や気質だけでなく、育ってきた環境も全般性不安症の発症に影響を与えることがあります。
- 過保護・過干渉な家庭環境: * 常に親が先回りして心配し、「もし〇〇になったらどうするの?」と問い続けられた経験。
- 「危ないからやめなさい」「失敗したら大変だから」と、子どもの挑戦を否定し続けた家庭。
- このような環境で育つと、子どもは自分で判断し、行動する機会が奪われ、「自分一人では何もできない」「常に誰かがそばにいてくれないと不安だ」という心理状態に陥りやすくなります。
- 完璧主義を強いられた家庭環境:
- 「失敗は許されない」「常に完璧でなければならない」という強いプレッシャーの中で育った経験。
- 些細なミスでも厳しく叱責されたり、努力を認めてもらえなかったりした経験。
- このような環境で育つと、大人になっても「完璧でなければ価値がない」という強迫観念に囚われ、常に失敗を恐れるようになります。
- 不安定な家庭環境:
- 父親が仕事で不在がちで、母親と二人だけの心細い生活を送っていた経験。
- 家庭内で常に緊張感が漂い、安心感が得られなかった経験。
- このような環境で育つと、心の安全基地を持てず、常に漠然とした不安を抱えやすくなります。
このように、全般性不安症は、生まれ持った気質だけでなく、育ってきた環境やその後のライフイベントが複雑に絡み合って発症することが多いのです。


全般性不安症のセルフチェックリスト
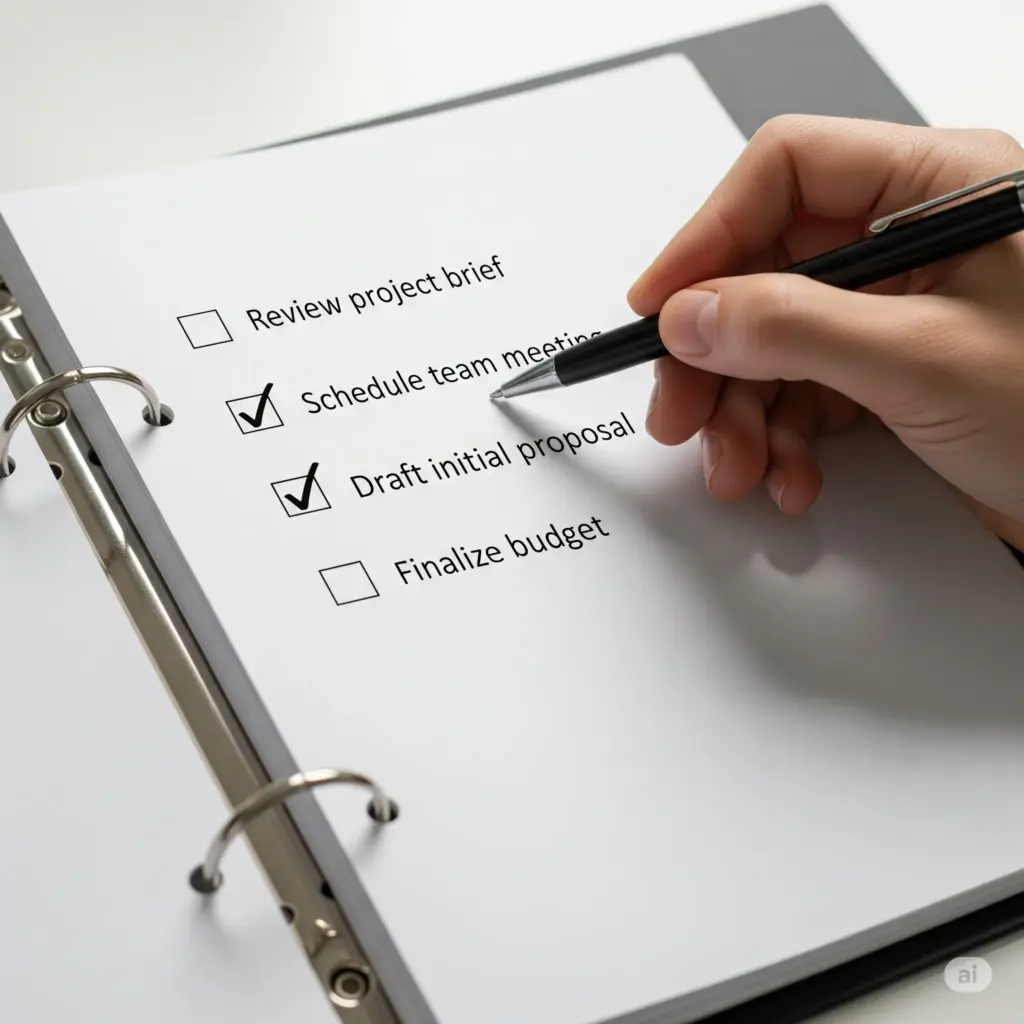
「チェックリスト」
以下の項目に当てはまるものが多い場合、全般性不安症の可能性があります。
- 親が心配性だった、あるいは完璧主義だった。
- 不安や心配な気持ちが1カ月以上続いている。
- 不安や心配を感じない日のほうが少ない。
- 仕事や勉強に集中できず、頭が真っ白になることがある。
- ぐっすり眠れず、朝起きたときから体がだるい。
- 日常生活でやることが増えると、すぐイライラしたり落ち着かなくなったりする。
- 動悸、息切れ、めまいが起きることがある。
- ふわふわと地に足がついていないような感覚になることがある。
- 他人の些細な言動に過剰に反応し、強い不安を感じてしまう。
- 筋肉の緊張から、頭痛や肩こりが頻繁に起きる。
- 自分の不安な気持ちを自分自身でコントロールできないと感じる。
- 誰かに話を聞いてもらわないと、不安が収まらない衝動に駆られる。
- 周囲から「考えすぎ」「気にしすぎ」と言われることが多い。
これらの症状は、ご本人にとっては非常に深刻な問題ですが、周囲からは「ただの心配性な人」「神経質なだけ」と受け取られ、なかなか理解を得られないことが多くあります。
誤解されやすい症状
全般性不安症の症状は、他の病気と間違われることも少なくありません。
- 自律神経失調症: 身体症状(動悸、めまい、発汗など)が前面に出ている場合、自律神経失調症と診断されることがあります。しかし、自律神経失調症は様々な要因で起こる症状の総称であり、その背景に全般性不安症が潜んでいる可能性があります。
- 更年期障害: 40代以降の女性の場合、ほてりや発汗、動悸などの身体症状から、更年期障害と診断されることがあります。しかし、更年期障害の症状は時間の経過とともに落ち着くことが多い一方、全般性不安症による症状は、適切な対処をしないと継続する可能性があります。
- パニック障害: 全般性不安症の人は、パニック発作を併発することも多いため、パニック障害と診断されることもあります。しかし、パニック障害は「いつ発作が起きるかわからない」という不安が中心であるのに対し、全般性不安症は「漠然とした様々なこと」に対する不安が中心です。
もし、あなたがこれらの項目に当てはまるなら、それは単なる「気の持ちよう」ではありません。身体が発するSOSサインだと捉え、専門家への相談を検討しましょう。適切な診断と治療を受けることが、回復への第一歩となります。
不安の悪循環を断ち切るために

「穏やかに過ごす」
なぜ、全般性不安症を克服できるのか?
全般性不安症の根本原因は医学的に完全に解明されているわけではありませんが、心理学的には多くのことがわかっています。私たちは、この症状がなぜ発症し、どのようにすれば克服できるのか、その道筋を熟知しています。
不安の根本には、生まれ育った環境や過去の出来事によって形成された「心のクセ」が潜んでいます。この「心のクセ」は、無意識のうちに私たちの思考や行動に影響を与え、不安を増幅させる悪循環を生み出しているのです。
大阪聖心こころセラピーでは、あなたの不安がどこから来るのか、その根本原因を深く探ることに重点を置いています。そして、その原因を解決するために、一人ひとりの状態に合わせた最適なプログラムを提供します。
聖心こころセラピーのアプローチ
当セラピーでは、医学的なアプローチとは異なる、心理療法を中心としたカウンセリングを行います。
- カウンセリングとコーチング:
- 専門家との対話を通じて、あなたの不安の根本にある感情や思考パターンを明らかにします。
- なぜそのように感じるのか、なぜそのように考えてしまうのか、自己理解を深めます。
- 新しい物の見方や考え方を身につけることで、不安を乗り越えるための心のスキルを習得していきます。
- 認知行動療法:
- 認知行動療法は、不安を増幅させる「思考の歪み」を修正していく科学的なアプローチです。
- 「最悪の事態」を想定してしまう思考パターンを客観的に見つめ、より現実的でバランスの取れた考え方に変えていきます。
- 思考を変えることで、行動も変わり、不安の悪循環を断ち切ることができます。
- ヒプノセラピー(催眠療法):
- 不安の根源が、意識できない「潜在意識」の奥深くにある場合、ヒプノセラピーが有効です。
- 催眠状態に入ることで、リラックスした状態で潜在意識にアクセスし、不安の根源となる過去の出来事や記憶に向き合います。
- そして、「不安を手放そうとしない」潜在意識のパターンを、より健全でポジティブなものへと書き換えていきます。
これらの手法を適切に組み合わせることで、あなたの心の中に深く根付いた「不安の種」を根本から取り除き、本来の自分らしい穏やかな心を取り戻すお手伝いをします。
克服の先にある未来
不安を克服することは、決して簡単なことではありません。しかし、その道のりを一歩ずつ進んでいけば、必ず明るい未来が待っています。
- 心が軽くなり、笑顔が増える: 常に感じていた緊張感から解放され、心からリラックスできるようになります。
- 自分に自信が持てるようになる: 自分の感情をコントロールできるようになったことで、自己肯定感が高まります。
- 人間関係が円滑になる: 過剰な心配から解放され、人との交流を心から楽しめるようになります。
- やりたいことに挑戦できる: 不安に邪魔されることなく、新しい趣味やキャリアに挑戦する勇気が湧いてきます。
「人から理解されにくい全般性不安症はつらいものです。しかし、その苦しみを乗り越えるための方法はあります。」
私たちは、その心のつらさに寄り添い、あなたのペースに合わせて、一緒に克服していくためのノウハウを持っています。もし今、あなたが不安のトンネルから抜け出せず苦しんでいるなら、まずは一度、私たちにご相談ください。あなたの心の声に耳を傾け、より良い未来への第一歩を一緒に踏み出しましょう。
◆関連記事 大人の愛着障害 親子問題・親子関係 不安症 パニック障害
参考文献・参考資料
- 坂野雄二(2006) 不安障害に対する認知行動療法 精神神経学雑誌 第114巻 第9号
- 大坪天平 (2022) わが国の全般不安症の現状と課題 不安症研究 第14巻第1号


