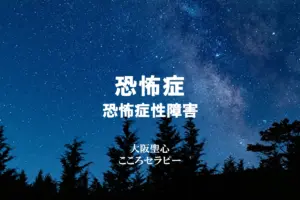不安症カウンセリング

不安症の専門カウンセリング|臨床心理士・公認心理師が解決に導きます
不安症専門カウンセリング
臨床心理士・公認心理師
が解決に導きます
不安は誰もが持ち合わせる自然な感情ですが、その強さや持続が過剰となり、合理的な説明がつかず、自分でコントロールすることが難しい場合には「不安症群」に含まれる状態である可能性があります。こうした不安が続くと、頭から離れず日常生活や社会生活に大きな支障をきたすことがあります。
関連性のあるテーマ
当カウンセリングは、診断や治療といった医療行為を行うものではありません。臨床心理士や公認心理師といった専門資格を持つカウンセラーが、認知行動療法などの心理療法を用い、様々な問題で悩む方々に対し、ご自身の心と向き合い、不安のメカニズムを理解し、日常生活をより穏やかに過ごすための専門的なサポートを提供します。
本記事は、アメリカ精神医学会(APA)が発行する『DSM-5-TR:精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版 改訂版』に基づき、臨床心理士が専門的知見のもとに執筆・監修しています。本内容は診断や医療行為を目的としたものではなく、カウンセリングにおける理解を深めるための情報提供としてご利用ください。
なぜ、あなたは不安に悩まされるのか?

「孤独と内面の葛藤」
私たちは日々、さまざまな感情とともに生きています。嬉しいこと、楽しいこと、悲しいこと、そして「不安」な気持ち。不安は、人生において避けて通れない感情の一つです。たとえば、新しい仕事を始める時、大切なプレゼンテーションを控えている時、愛する人の身を案じる時など、私たちは多かれ少なかれ不安を感じます。この不安があるからこそ、私たちは事前に準備をしたり、注意を払ったりして、危険を回避しようとします。
しかし、その不安が過剰になり、日常生活に支障をきたすほどになると、それは単なる感情ではなく「不安症」という心の病気である可能性があります。
この記事では、不安症とは何か、その種類や原因、そして不安症を克服するための具体的な方法について、精神科医や臨床心理士の専門的な知見を交えながら、わかりやすく解説していきます。あなたの「なぜ?」という疑問に答え、一歩踏み出すためのヒントをお届けできれば幸いです。
慢性的な不安の背景には、幼少期の養育環境による愛着不安が関係することがあります。詳しくは大人の愛着障害をご覧ください。
また、対人不安や過度な緊張は、過去の家庭環境から影響を受ける場合があります。関連内容はアダルトチルドレンをご参照ください。
「正常な不安」と「病的な不安」の違いとは?
冒頭でも触れたように、不安そのものは決して悪いものではありません。むしろ、私たちの安全を守るための重要な防衛システムだと言えます。明確な理由があり、自分でコントロールできる範囲の不安であれば、それは「正常な不安」です。
しかし、以下のような状態になると、それは「病的な不安」のサインかもしれません。
- 漠然とした不安が続く:明確な理由がないのに、常に心が落ち着かず、そわそわする。
- 不快な身体症状を伴う:動悸、発汗、息苦しさ、めまい、震えなどが頻繁に起こる。
- 日常生活に支障をきたす:不安のせいで仕事や学業に集中できない、友人との約束をキャンセルしてしまう、外出が億劫になるなど。
- 長期にわたり不安が持続する:不安な気持ちが数週間、数ヶ月と続き、改善の兆しが見えない。
このような「病的な不安」は、放っておくと生活の質を著しく低下させ、心身の健康を損なうことにつながります。
あなたの不安はどのタイプ? – 不安症の種類と特徴
「不安症」は、特定の疾患を指すのではなく、不安感が中心となるさまざまな病気の総称です。不安症は、その症状や原因によっていくつかのタイプに分けられます。ご自身の状態と照らし合わせながら読んでみてください。
パニック障害:予測不能な発作に襲われる恐怖
パニック障害は、突然、理由もなく強い恐怖やパニックの発作に襲われる病気です。発作中は、心臓がバクバクする、息が苦しい、めまいがする、死んでしまうのではないかというほどの恐怖感に襲われ、コントロールを失ったように感じます。
一度この発作を経験すると、「また発作が起きたらどうしよう」という予期不安が強くなり、発作が起きた場所や、逃げ場がないと感じる場所(電車、バス、人混みなど)を避けるようになる広場恐怖を併発することがあります。これにより、外出が困難になるなど、生活範囲が著しく狭まってしまいます。
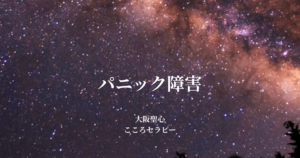
全般性不安症:絶え間なく押し寄せる心配の波
全般性不安症は、特定の対象がないにもかかわらず、仕事、健康、家族など、あらゆることに対して慢性的に強い不安や心配を感じ続ける病気です。心が常に張り詰めた状態になり、些細なことにも過剰に反応してしまいます。
主な症状としては、落ち着かない、イライラする、集中できないといった精神的なものに加え、頭痛、肩こり、不眠などの身体症状も現れやすいのが特徴です。本人は「心配しすぎなのはわかっているけれど、やめられない」というジレンマを抱え、強い苦痛を感じます。
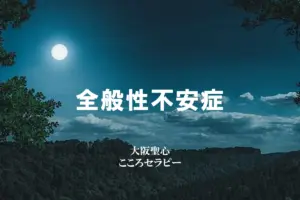
恐怖症:特定の対象に対する異常な恐怖
恐怖症は、通常であれば危険ではない特定の対象や状況に対して、強い恐怖を感じ、それを避けるようになる病気です。
- 広場恐怖症:電車やバス、人混みなど、逃げ場がないと感じる場所や状況を極端に恐れる。
- 対人恐怖症:人前で話すことや、他人の視線、評価を過剰に恐れる。
- 高所恐怖症:高い場所にいることに対して強い不安を感じる。
この恐怖は、単なる「苦手」とは異なり、生活に大きな支障をきたすほど強いものです。たとえば、広場恐怖症の人は電車に乗れなくなり、対人恐怖症の人は人と会うことを避けるようになり、社会生活が困難になることがあります。
強迫症:繰り返される思考と行動のループ
強迫症(強迫性障害)は、自分の意志に反して不合理な考え(強迫観念)が頭に浮かび、その不安を打ち消すために特定の行動(強迫行為)を繰り返してしまう病気です。
たとえば、「手が汚れているのではないか」という強迫観念に囚われ、何度も手を洗い続けてしまう。鍵を閉めたか不安になり、何度も確認に戻ってしまう、といった行動が見られます。これらの行為は、一時的に不安を和らげますが、根本的な解決にはならず、生活の大部分を占めるようになります。本人は「ばかばかしい」とわかっているのにやめられず、強い苦痛を感じます。

社交不安症:人前での自分に過剰な恐怖
社交不安症は、人から注目を浴びる状況や、人前で何かをすることに対して、極度の不安や恐怖を感じる病気です。たとえば、人前で話す、食事をする、文字を書く、電話をかけるといった日常的な行為が困難になります。
症状が重い場合は、手が震える、汗が止まらない、顔が赤くなる、声が上ずるといった身体症状を伴うこともあります。この恐怖から、そのような場面を避けるようになり、社会的な孤立を招くことがあります。

適応障害:環境の変化についていけない心と体
適応障害は、仕事、学校、家庭など、環境の変化やストレスが原因で、心身に様々な症状が現れ、日常生活に支障をきたす病気です。
ストレス源から離れると症状が改善することが特徴ですが、ストレスを抱え続けると、うつ状態や不安感が強くなり、不登校、ひきこもり、欠勤といった問題につながることがあります。

PTSD(心的外傷後ストレス障害):過去の出来事にとらわれる
PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、生命の危険を感じるような強烈な体験(大災害、犯罪被害、事故など)が原因で、精神的なショックがトラウマとなり、様々な症状が現れる病気です。
主な症状には、
- フラッシュバック:トラウマ体験が、まるで今起きているかのように鮮明に蘇る。
- 回避:トラウマを思い出させるような場所、人物、状況を避ける。
- 過覚醒:常に神経が張り詰めた状態で、些細な物音にも驚く、眠れないなど。
といったものがあります。

分離不安症:愛着対象から離れることへの恐怖
分離不安症は、家族や愛着を持つ人、場所から離れることに、過剰な不安を感じる病気です。特に幼少期によく見られ、腹痛や頭痛、悪夢といった身体症状や、登校を嫌がるなどの行動につながることがあります。
大人になってからも、ホームシックが異常にひどく、実家に戻ってしまう、恋人と離れることに耐えられないといった形で症状が現れることもあります。
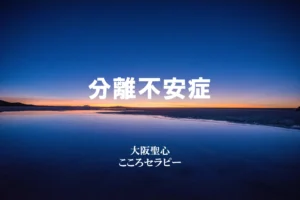
病気不安症:重い病気への過剰な心配
病気不安症は、「自分は重い病気にかかっているのではないか」という考えに囚われ、必要以上に心配し続ける病気です。医師から「異常なし」と診断されても安心できず、次々と別の病院を受診するドクターショッピングを繰り返す傾向があります。
本人は、強い不安や恐怖に苦しんでおり、日常生活にも支障をきたしています。うつ病や他の不安症を併発することもあります。

なぜ、現代社会では不安症が増えているのか? – 現代病としての側面

「日常に潜む不安」
不安症は、特に1990年代後半から増加傾向にあると言われています。その背景には、現代社会が抱える様々な問題が関係しています。
- ストレス社会:仕事や人間関係、情報過多の社会において、私たちは常にストレスにさらされています。ストレスをうまく発散できないと、心身に溜まり、不安症を引き起こす可能性が高まります。
- 変化のスピード:技術革新や社会の変化が速く、私たちは常に新しい環境への適応を求められます。この変化についていけないことが、大きな不安につながることがあります。
- 情報過多:テレビやインターネットを通じて、世界中の悲惨な出来事や事故、病気の情報が日々流れ込んできます。感受性の強い人は、これらの情報に過剰に反応し、不安を増幅させてしまうことがあります。
現代社会は、私たちに常に「頑張れ」「完璧であれ」と無言のプレッシャーをかけてきます。このプレッシャーにうまく対処できない時、心は悲鳴を上げ、不安という形で現れるのです。
あなたの性格や生育環境が不安症を引き起こす? – 心の基盤を考える
不安症は、社会的な要因だけでなく、個人の性格やこれまでの経験も大きく影響します。
常に最悪のシナリオを想像する「心配性の罠」
不安症になりやすい人は、常に多くのことを心配し、未来に対してネガティブなイメージを抱きやすい傾向があります。これは、過去の嫌な経験や失敗が忘れられず、「また同じことが起こるのではないか」という不安に囚われてしまうためです。
このような「心配性の罠」にはまると、不安が不安を呼び、自分を追い込む悪循環に陥ってしまいます。
完璧主義と自己肯定感の低さ
「完璧でなければ愛されない」「失敗する自分は価値がない」と感じる完璧主義や、自分に自信が持てない自己肯定感の低さも、不安症の大きな要因となります。
このような考え方は、他人からの評価を過剰に気にしたり、失敗を恐れて新しい行動を起こせなくなったりするため、日常生活の様々な場面で不安を感じやすくなります。
育ちの環境がもたらす影響 – 親子関係の重要性
意外に思われるかもしれませんが、不安症の傾向は、子供の頃の家庭環境が大きく影響している場合があります。
- 過保護・過干渉な親:子供の一挙手一投足に口を出し、先回りして何でもしてしまう親に育てられると、子供は自分で考えて行動する機会を失い、自分の力で問題を解決する自信が持てなくなります。
- 支配的・否定的な親:「そんなんじゃダメだ」「どうしてそんなことしたの?」といった否定的な言葉を浴びせられると、子供は自己肯定感を育むことができず、「自分はダメな人間だ」という考えを持つようになります。
- 不安定な家庭環境:両親の不仲や虐待、DVなど、家庭が安心できる場所でなかった場合、子供は常に緊張を強いられ、漠然とした不安感を抱えやすくなります。
このような環境で育った人は、大人になっても人や物事に対して過剰に反応し、些細なことで不安に襲われやすくなる傾向があります。
誰にも理解されない辛さ – 「そんなことぐらい」と言われても
不安症の辛さは、周りの人に理解されにくいという点にもあります。本人にとっては耐えがたいほどの不安や恐怖でも、周りから見れば「そんなことで?」と思われてしまうことも少なくありません。
「気にしすぎだよ」「大丈夫だって」といった言葉は、励ましのつもりでも、本人にとっては「自分の辛さは理解してもらえない」という孤立感を深めることにつながります。
不安症を抱える人は、自分自身を責め、「こんなことで悩むなんて情けない」と自己嫌悪に陥ることも多いです。しかし、不安症は決してあなたの性格や気の弱さからくるものではありません。脳の神経伝達物質のバランスの乱れなど、生物学的な要因も関係していることが分かってきています。
一人で悩まないで – 不安症を克服するための具体的なステップ

「光の象徴」
不安症は、適切な対処や治療によって改善できる心の病気です。一人で抱え込まず、まずはできることから始めてみましょう。
1.自分の不安と向き合う「認知行動療法」
認知行動療法は、不安症の治療法として世界的に効果が認められている心理療法です。これは、「ものの考え方(認知)」や「行動」に働きかけ、気持ちを楽にする方法を身につけることを目的とします。
不安症の人は、物事をネガティブに捉えがちな認知の歪みを持っていることが多くあります。たとえば、人前で失敗すると「私は完璧にダメな人間だ」と思い込んでしまう、といった考え方です。認知行動療法では、この考え方の癖を見つけ、よりバランスの取れた、現実的な考え方へと修正していきます。
ステップの例
- 不安な気持ちを記録する:どんな時に、どんなことで、どんな不安を感じたかを書き出す。
- 自動思考を見つける:「こうなったらどうしよう」という、瞬時に浮かんだネガティブな考えを見つける。
- 根拠を探す:その考えが正しいのか、根拠を冷静に探す。
- 新しい考え方を探す:「別の見方をすると、どうだろう?」と、より現実的で柔軟な考え方を探す。
このように、自分の思考パターンを客観的に見つめ直し、建設的な考え方に変えていく練習を重ねることで、不安にうまく対処できるようになります。
2.不安を克服する「行動」の練習
不安を克服するためには、実際に不安な状況に少しずつ身を慣らしていく暴露療法も効果的です。たとえば、電車に乗るのが怖い広場恐怖症の人であれば、以下のようなステップを踏みます。
- 最寄り駅のホームに立つ
- 一駅だけ電車に乗ってみる
- 乗車時間を徐々に延ばしていく
- 混雑する時間帯に乗ってみる
このように、無理のない範囲で不安な状況に直面し、「不安に思っても、意外と何も起こらない」という成功体験を積み重ねていくことで、不安を乗り越える自信が育っていきます。
家庭でできる不安症へのアプローチ – 周りのサポートも不可欠
もし、あなたの家族や大切な人が不安症で悩んでいるなら、ぜひ理解し、サポートしてあげてください。不安症の克服には、周りの人の支えが不可欠です。
- 「そんなことぐらい」は言わない:本人の苦痛を否定せず、「辛いんだね」と共感し、受け止めてあげることが大切です。
- 完璧を求めすぎない:完璧主義的な考えは、不安を増幅させます。「失敗しても大丈夫」「あなたのままでいい」というメッセージを伝えましょう。
- 良い行動を褒める:ほんの些細なことでも、できたことを褒め、自己肯定感を高めてあげましょう。
- 一緒に専門家を頼る:カウンセリングは本人だけでなく、家族も一緒に受けることで、互いの理解を深め、より良いサポートの方法を学ぶことができます。
聖心こころセラピーが提供する不安症カウンセリング
-1024x1024.webp)
「カウンセリングの風景(イメージ)」
大阪聖心こころセラピーでは、不安症に悩むあなたの心に寄り添い、根本的な原因から解決に導くためのカウンセリングを提供しています。
- 専門的な知識と経験を持つカウンセラー:多岐にわたる不安症の種類や症状、そしてその背景にある心理的な要因を深く理解したカウンセラーが、あなたの心の問題を丁寧にひも解きます。
- 一人ひとりに合わせたパーソナライズされたアプローチ:決まった型にはめるのではなく、あなたの性格や生育環境、現在の状況などを踏まえ、認知行動療法をはじめとする最適な心理療法を組み合わせたアプローチをご提案します。
- 心の深い部分にアプローチ:顕在意識だけでなく、自分では気づきにくい潜在意識に隠された不安の根源にもアプローチし、根本からの改善を目指します。
漠然とした不安、人には言えない恐怖、誰にも理解されない孤独…どんなお悩みでも、どうぞ私たちにご相談ください。あなたの人生を蝕む不安から脱却し、本来のあなたらしい輝きを取り戻すための一歩を、私たちと一緒に踏み出しましょう。
不安症から抜け出し、自分らしい人生を歩むために

「心の解放」
不安症は、単なる気の持ちようではありません。しかし、正しい知識を持ち、専門家の力を借りることで、必ず乗り越えることができます。
- 自分の不安を知る:まずは、自分がどんな不安を抱えているのか、それがなぜ生まれるのかを知ることから始めましょう。
- 適切な対処法を学ぶ:不安を一時的に和らげるだけでなく、根本的に解決するための方法を学び、実践しましょう。
- 一人で抱え込まない:家族や友人、そして私たちのような専門家を頼ることを恐れないでください。
不安は、あなたの人生を停滞させるものではありません。それは、あなたが本当に望む生き方へと導くための「道しるべ」です。この機会に、ご自身の不安と向き合い、新しい自分と出会う旅に出てみませんか。
ご質問やご相談は、いつでもお気軽にお問い合わせください。
◆関連記事 大人の愛着障害 アダルトチルドレン 全般性不安症 パニック障害
参考文献・参考資料
- 樋口輝彦・大野裕(編著)(2006) 『不安障害のすべてがわかる本』 講談社
- 大野裕(2003) 不安障害の認知行動療法 精神科治療学 第18巻 7号
- アメリカ精神医学会(著),日本精神神経学会(監訳)(2023) 『DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアルテキスト改訂版』 医学書院