大阪の病気不安症|深刻な健康不安相談 病や死への恐怖を鎮め、健やかに生きる
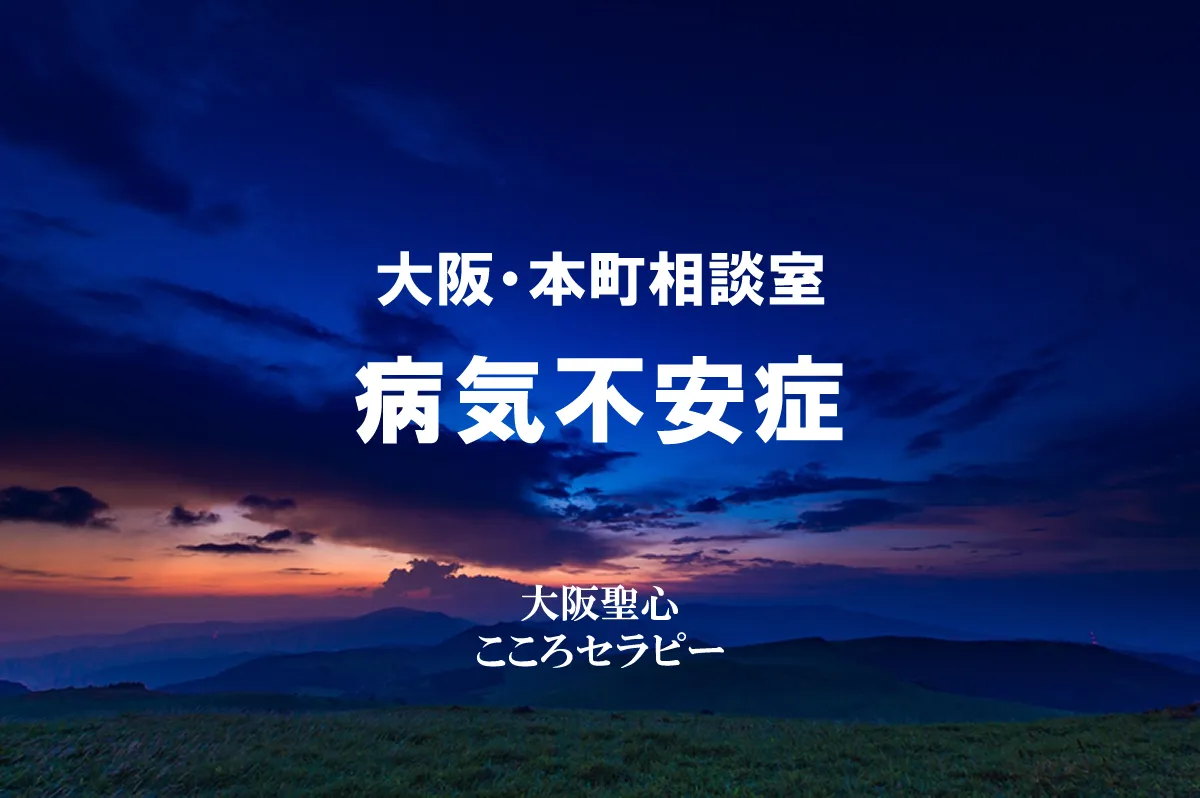
病気不安症の専門カウンセリング|臨床心理士・公認心理師が解決に導きます
病気不安症専門カウンセリング
臨床心理士・公認心理師
が解決に導きます
病気不安症(心気症)は、実際には重大な身体症状がほとんどないにもかかわらず、「自分は重い病気にかかっているのではないか」と強く思い込み、その不安が持続することが特徴です。 周囲から「心配しすぎだよ」と声をかけられても安心できず、何度も医療機関を受診したり、インターネットや本で病気の情報を探し続けたりすることがあります。その結果、不安がさらに強まり、生活に大きな支障をきたすことがあります。
関連性のあるテーマ
当カウンセリングは、診断や治療といった医療行為を行うものではありません。臨床心理士や公認心理師といった専門資格を持つカウンセラーが、認知行動療法などの心理療法を用い、様々な問題で悩む方々に対し、ご自身の心と向き合い、不安のメカニズムを理解し、日常生活をより穏やかに過ごすための専門的なサポートを提供します。
本記事は、アメリカ精神医学会(APA)が発行する『DSM-5-TR:精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版 改訂版』に基づき、臨床心理士が専門的知見のもとに執筆・監修しています。本内容は診断や医療行為を目的としたものではなく、カウンセリングにおける理解を深めるための情報提供としてご利用ください。
終わりなき不安のループから抜け出すために

「心配や不安」
「もしかして、自分は重い病気なんじゃないか?」
体調が少しでも優れないと、そう考えてしまうことはありませんか? 咳が出たら肺がんかもしれない、頭痛がしたら脳腫瘍かもしれない。インターネットで症状を検索しては、最悪のシナリオばかりを思い浮かべてしまう。
そして、病院で「異常なし」と言われても、「見落としがあったのでは?」「もっと詳しい検査が必要なのでは?」と、別の病院を次々と受診してしまう。
このような、健康に対する過剰な不安に囚われ、日常生活に支障をきたしてしまう状態を「病気不安症(ひょうきふあんしょう)」、または旧称である「心気症(しんきしょう)」といいます。これは、単なる心配性とは違い、心の健康を蝕んでいく深刻な状態です。
“病気かもしれない”という強い不安の背景には、安心感の土台である愛着が揺らいでいることがあります。詳しくは大人の愛着障害をご覧ください。
また、心配性が強くなる背景には、幼少期の親子関係の影響が見られる場合もあります。関連内容は親子問題・親子関係をご一読ください。
本記事では、病気不安症のメカニズムから、その症状、そして克服への道筋までを、専門的な視点と分かりやすい言葉で解説します。あなたが抱える不安の正体を理解し、前に進むためのヒントを見つけてください。
なぜ病気不安症は起こるのか:その根本原因に迫る

「終わらない検索のループ」
病気不安症に陥る原因は、人によってさまざまです。しかし、そこには共通するいくつかの要因が見られます。
過去の経験が不安の引き金になる
過去に自分自身が重い病気を経験したり、家族や友人が病気で苦しむ姿を目の当たりにしたりした経験は、強いトラウマとなり得ます。そのときの「辛かった」「怖かった」という感情が心に深く刻まれ、ちょっとした体調の変化に対しても、過剰な警戒心や恐怖心を生み出すことがあります。これは、心が自分を守ろうとする防衛反応の一種ですが、それが過剰になると、日常的な不安となって現れます。
情報過多社会が生む落とし穴
現代社会は、インターネットやテレビ、雑誌などから、医療や健康に関する情報が洪水のように押し寄せています。これらの情報の中には、病気の恐ろしさを煽るようなものも少なくありません。
例えば、「○○の症状は、実は××という病気のサインかもしれません」といった内容の特集記事やテレビ番組を見て、自分のわずかな体調不良と重ね合わせてしまうことがあります。これは、不安を抱えやすい人が陥りやすい落とし穴と言えるでしょう。
性格や育った環境が影響することも
一般的に、物事を深く考え込みやすい人、心配性な人、内向的な人は、病気不安症に陥りやすい傾向があります。これは、自分の内面にある感情や感覚に意識が向きやすく、身体的な変化を過大に捉えてしまうためです。
また、幼少期の家庭環境も影響することがあります。例えば、過度に健康を気遣う親に育てられたり、病気になったときに過剰な心配をされたりすると、「病気になることは怖いことだ」「身体はいつか壊れてしまうものだ」といった考え方が無意識のうちに刷り込まれてしまうことがあります。
日常生活のストレスとの関連
病気不安症の背景には、仕事や人間関係、家庭の悩みなど、日常生活のストレスが隠れていることが多々あります。これらのストレスは、心のエネルギーを消耗させ、不安や恐怖を感じやすい状態を作り出します。
ストレスを抱えると、身体的にも肩こりや頭痛、胃の不調など、さまざまな不調が現れることがあります。しかし、心の不調に気づかないまま、これらの身体的な不調を「何か大きな病気のサインではないか」と勘違いし、病気不安症へと発展してしまうケースも少なくありません。
病気不安症の主な症状:あなたはいくつ当てはまりますか?

「ドクターショッピングの繰り返し」
病気不安症は、単に「健康が心配」というレベルを超え、日常生活に深刻な影響を及ぼします。以下に挙げる症状に心当たりがないか、チェックしてみてください。
終わらない「ドクターショッピング」
病院で精密検査を受けても「異常なし」と診断されたのに、医師の言葉を信じることができず、「見落としがあるに違いない」と、次から次へと別の病院を受診する「ドクターショッピング」を繰り返します。
これは、医師に「病気ではない」と保証されても、心の奥底にある不安が解消されないために起こる行動です。医師の診断は、一時的な安心しかもたらさず、すぐにまた別の不安が頭をもたげてきます。
わずかな身体反応への過剰な反応
誰でも、時々お腹が鳴ったり、発汗したり、めまいを感じたりすることはあります。しかし、病気不安症の人は、こうした身体の自然な生理反応を、何か重い病気の兆候だと捉え、過剰に恐怖を感じます。
例えば、少し動悸がしただけで「心臓病かもしれない」、頭が重いと感じただけで「脳腫瘍かもしれない」といったように、あり得ないような病名を自分で勝手に診断し、不安を増幅させてしまいます。
日常生活への支障
病気への恐怖が強くなると、仕事や学業、家事など、日常生活が手につかなくなります。朝起きるのが辛くなり、欠勤や不登校、家事放棄をしてしまうこともあります。これは、病気への恐怖が、心だけでなく、身体のエネルギーも奪ってしまうためです。
また、友人と食事をする際も、「この食べ物は身体に悪いかもしれない」と過度に心配したり、運動をしようと思っても「無理をすると病気になるかもしれない」と行動を制限したりするなど、健康への不安が生活のあらゆる場面に影響を及ぼします。
病気不安症と似て非なる症状:混同しやすいケース
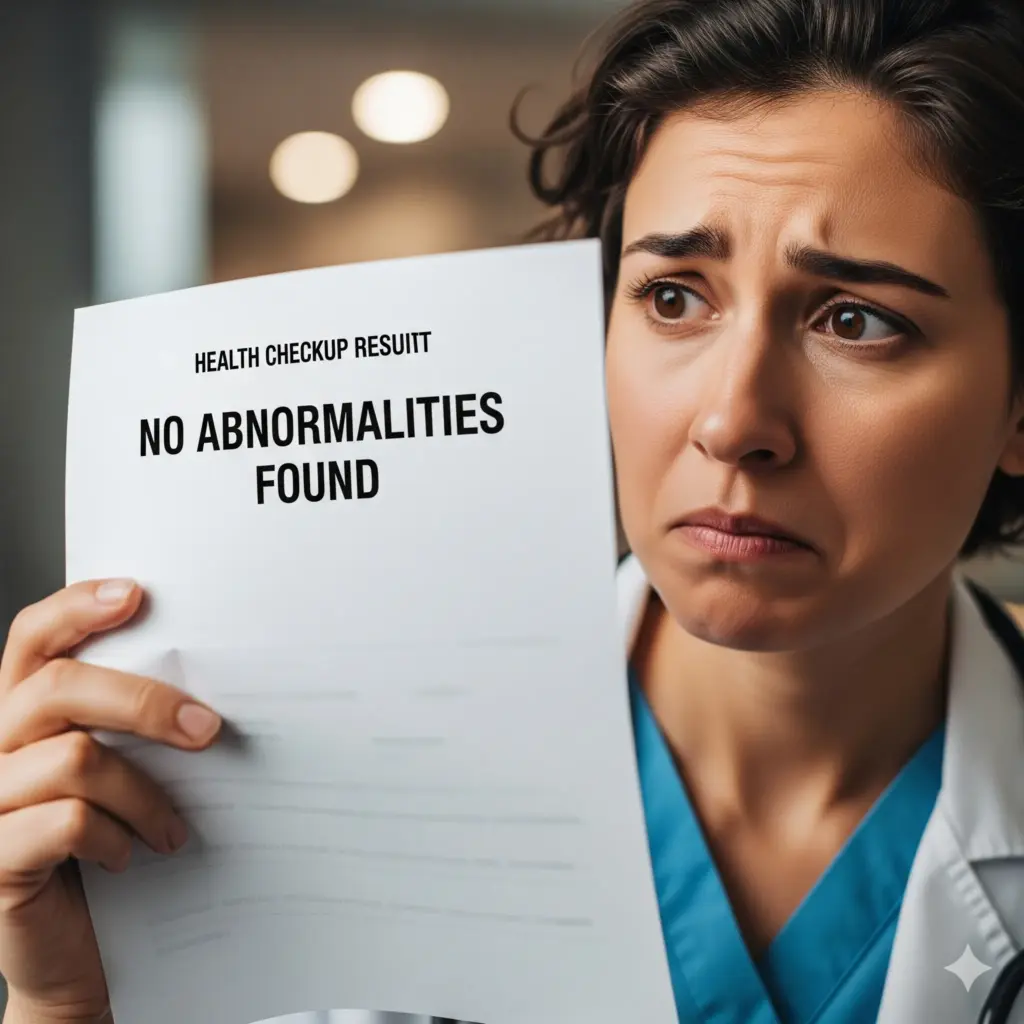
「心と体のギャップ」
病気不安症は、他の精神疾患や、実際に身体的な病気を抱えている状態と混同されやすいことがあります。正確な診断のためにも、その違いを理解しておくことが重要です。
精神的な病との違い:心気妄想との区別
病気不安症は「もしかしたら病気かもしれない」という「不安」が中心となります。一方、統合失調症などの精神疾患でみられる「心気妄想(しんきもうそう)」は、「自分は病気だ」という強い「確信」が中心となります。
心気妄想を持つ人は、医師に「病気ではない」と診断されても、その診断を信じることができず、むしろ医師を信用できなくなります。病気不安症が、不安を解消するために病院を転々とするのに対し、心気妄想は、自分の確信を否定されることへの抵抗から、医師との関係がこじれることもあります。
パニック障害と病気不安症
パニック障害は、突然激しい動悸や呼吸困難、めまいなどの身体症状が現れる発作(パニック発作)を特徴とする不安障害です。この発作が、病気不安症と混同されることがあります。
パニック発作を初めて経験した人は、「心臓発作ではないか?」「死んでしまうのではないか?」という強い恐怖を感じます。この発作は、命に関わるものではありませんが、その恐怖から「また発作が起きたらどうしよう」という予期不安が生じ、病気不安症のように、身体のわずかな変化を過剰に気にするようになることがあります。このように、パニック障害が引き金となって病気不安症の症状が現れることも少なくありません。

実際に身体的な病気がある場合
病気不安症は、医師の診察や検査で異常が見つからない場合に診断されますが、実際に病気を抱えている場合でも、病気不安症のような症状が現れることがあります。
特に、外科手術を受けた後や、慢性的な病気を抱えている人は、後遺症や再発への不安から、病気不安症のような心理状態に陥りやすくなります。また、うつ病や他の不安障害の副次的な症状として、病気への不安が強くなることもあります。このようなケースを「二次性病気不安症」と呼ぶこともあります。
終わりなき不安のループを断ち切るために
病気不安症は、単なる気の持ちようではありません。それは心の病であり、適切な診断と治療が必要です。
まずは専門家への相談を
「もしかして、自分は病気不安症かもしれない」と感じたら、まずは心療内科や精神科、または専門のカウンセリング機関に相談することをお勧めします。
専門家は、あなたの症状や悩みを丁寧に聞き、それが病気不安症なのか、他の病気からくるものなのかを正確に診断します。また、一人で悩むのではなく、専門家と話すこと自体が、不安の軽減につながることもあります。
治療の柱となる心理療法:認知行動療法
病気不安症の治療法として、特に有効性が認められているのが「認知行動療法(にんちこうどうりょうほう)」です。この治療法は、「自分が病気かもしれない」という考え方(認知)と、それによって引き起こされる行動(ドクターショッピングなど)を変えていくことを目的としています。
具体的には、以下のようなプロセスで進められます。
- 考え方のクセに気づく
「ちょっとしためまいは、脳腫瘍のサインに違いない」といった、非合理的な考え方や、不安を増幅させる思考パターンに気づき、それを客観的に捉える練習をします。
- 考え方を修正する
「めまいは、睡眠不足や疲労からくるものかもしれない」「一時的なもので、すぐに治まるはずだ」といった、より現実的でバランスの取れた考え方に変えていく練習をします。
- 行動を変える
不安を感じるたびにインターネットで症状を検索したり、病院を転々としたりする行動を少しずつ減らし、代わりに、不安な気持ちを話す、リラックスできる活動をするなど、建設的な行動へとシフトしていく練習をします。
認知行動療法は、単に不安を抑えるだけでなく、不安を感じやすい根本的な原因にもアプローチすることで、同じような悩みを繰り返さないようにすることを目的としています。
薬物療法との併用
症状が重く、日常生活に大きな支障が出ている場合には、薬物療法が用いられることもあります。特に、不安や抑うつ症状が強い場合には、抗不安薬や抗うつ薬などが処方されることがあります。
ただし、病気不安症に特化した特効薬というものは存在しません。薬はあくまで、心理療法をより効果的に進めるための補助的な役割を果たすものだと考えましょう。
自分自身でできるセルフケア:不安と向き合うための実践

「希望と癒し」
専門家のサポートを受けながら、日常生活で自分自身ができるセルフケアも大切です。
生活習慣を見直す
不規則な食事や睡眠不足は、身体的な不調を引き起こし、それが不安を増幅させる原因になります。規則正しい生活リズムを心がけ、十分な睡眠とバランスの取れた食事を意識しましょう。
また、適度な運動は、ストレスの軽減に役立ちます。ウォーキングやストレッチなど、無理のない範囲で身体を動かす習慣を取り入れてみましょう。
感情を言語化する
「何か重い病気ではないか」という不安な気持ちは、一人で抱え込まず、誰かに話してみることが大切です。家族や友人に話すのが難しい場合は、カウンセラーに相談してみるのも良いでしょう。
自分の心に感じていることを言葉にすることで、感情が整理され、不安が和らぐことがあります。
健全な知識を身につける
インターネットで無闇に症状を検索するのではなく、信頼できる情報源(厚生労働省や専門学会のサイトなど)から、病気や健康に関する正しい知識を身につけましょう。これにより、根拠のない不安に振り回されることを減らすことができます。
「気の持ちよう」を超えて
「病は気から」という言葉は、確かに心の状態が身体に影響を与えることを示唆しています。しかし、病気不安症は単なる「気の持ちよう」で解決できるものではありません。それは、あなたが抱えている心の痛みのサインなのです。
自分は病気かもしれないという不安に囚われるのではなく、まずは「なぜこんなに不安なんだろう?」という心の声に耳を傾けてみませんか? その答えは、もしかしたら、あなたが本当に抱えている悩みやストレスの中にあるかもしれません。
あなたの心と身体が、穏やかで健康な状態を取り戻せるよう、私たち聖心こころセラピーがお手伝いします。一人で悩まず、まずは一歩踏み出してみませんか?
◆関連記事 大人の愛着障害 親子問題・親子関係 不安症 全般性不安症
参考文献・参考資料
- 高橋 徹(1993)『心気症—近年の精神医学疾病誌にみられる病像』 精神医学 第35巻 第6号
- アメリカ精神医学会(著),日本精神神経学会(監訳)(2023)『DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル テキスト改訂版』 医学書院


