「ASD」自閉スペクトラム症カウンセリング
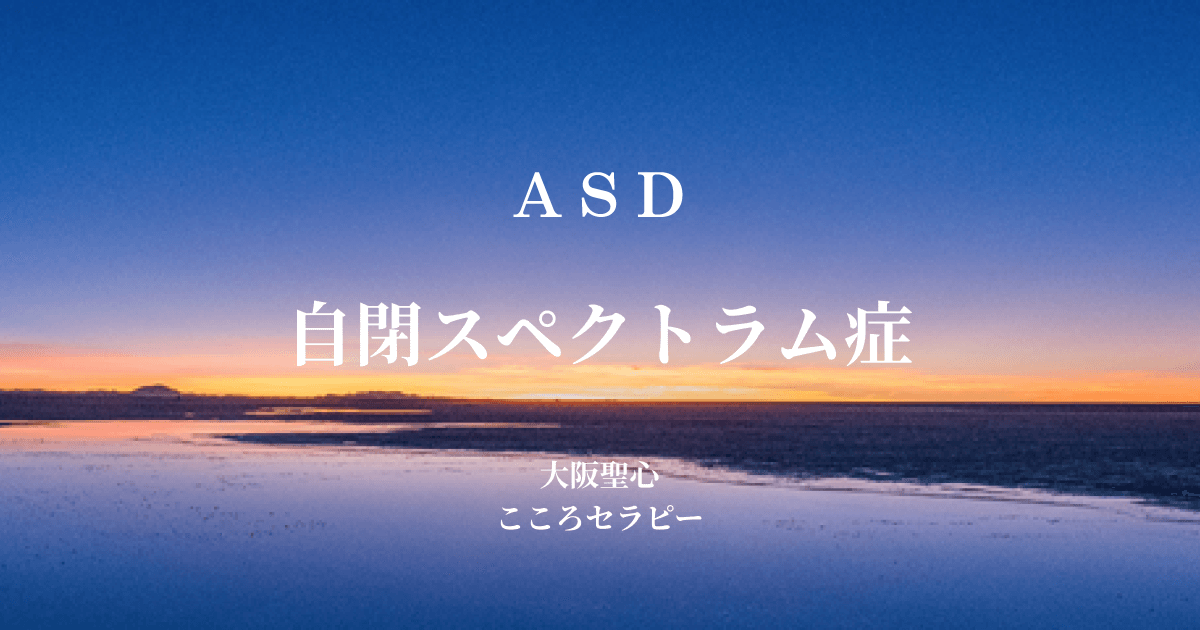
自閉スペクトラム症の専門カウンセリング
臨床心理士・公認心理師が解決に導きます
自閉スペクトラム症
専門カウンセリング
臨床心理士・公認心理師
が解決に導きます
「ASD」自閉スペクトラム症とは、心の病気ではなく、生まれつきの脳の働き方の違いによって現れる発達の特性です。社会生活の中で様々な困難や課題が生じることがあります。ご本人だけでなく、養育者や保護者が日常生活で大きな負担を感じることもあるため、周囲の理解と支援が重要です。
関連性のあるテーマ
当カウンセリングは、診断や治療といった医療行為を行うものではありません。臨床心理士や公認心理師といった専門資格を持つカウンセラーが、認知行動療法などの心理療法を用い、様々な問題で悩む方々に対し、ご自身の心と向き合い、不安のメカニズムを理解し、日常生活をより穏やかに過ごすための専門的なサポートを提供します。
本記事は、アメリカ精神医学会(APA)が発行する『DSM-5-TR:精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版 改訂版』に基づき、臨床心理士が専門的知見のもとに執筆・監修しています。本内容は診断や医療行為を目的としたものではなく、カウンセリングにおける理解を深めるための情報提供としてご利用ください。
ASD(自閉スペクトラム症)の特性を理解する

「自分だけの世界」
「もしかして、自分は普通と違う?」「なぜか周りの人とうまく話せない」「いつも空回りしてしまう」
もしあなたがそう感じているなら、それは決してあなたの心が弱いからではありません。生まれつきの特性によって、世界が少し違った見え方をしているだけかもしれません。
近年、テレビやインターネットでも見聞きするようになったASD(自閉スペクトラム症)。もしかしたら「心を閉ざしている人」「殻に閉じこもっている人」というイメージを持っている方もいるかもしれません。しかし、それはまったく違います。
ASDは、先天的な脳の機能の違いから生じる、発達の特性です。決して心の病気ではありません。
「自閉」という言葉から、引きこもりや対人恐怖症を連想するかもしれませんが、ASDは遺伝的な要因が複雑に絡み合って生じると考えられています。
一見、ASDと診断されるような典型的な症状がなくても、特性を持つ人は意外と多く、軽度な人を含めると100人に1人いるとも言われています。
ASDの人は、目や耳から入ってくる情報の処理や整理に特徴があるため、その場の状況に合った発言や行動が難しかったり、相手の気持ちを推測したり、自分の行動を振り返ることが苦手に感じられる場合があります。ただし、現れ方には個人差があります。
しかし、その特性を理解し、配慮することで、ご本人が生きやすくなるだけでなく、周囲の人との関係もより良いものに変わっていくはずです。
コミュニケーションの難しさがある場合、幼少期の親子関係のサポートが特に重要になります。関連内容は親子問題・親子関係をご覧ください。
また、ASD特性の方が抱えやすい“対人不安”や“距離感のつかみにくさ”には、愛着の問題が重なる場合もあります。詳しくは大人の愛着障害をご一読ください。
ASDとは? 発達障害の考え方とスペクトラムという概念
「そもそも、ASDって何だろう?」
そう思われる方も少なくないでしょう。
かつて、発達障害は「自閉症」「広汎性発達障害」「アスペルガー症候群」など、細かく分類されていました。1970年代以降、自閉症が注目され、その親戚のような症状がいくつか存在することがわかってきたため、発達障害の細分化が進んだとされています。
しかし、これらの症状をすべて併せ持っている人が少数であること、そして個人によって現れ方が多様であることがわかってきました。
そこで、一つひとつの障害として捉えるのではなく、それぞれの特性を連続した一つの集合体として捉えよう、という考え方が生まれました。これが「ASD(自閉スペクトラム症)」という概念です。
「スペクトラム」とは「連続している」という意味です。症状名に固執するのではなく、一人ひとりの持つ多様な特性を理解し、柔軟にサポートすることの重要性が注目されるようになったのです。
発達の特性は、ちょうど色のグラデーションのように、人によって濃さも重なり方も異なります。「ASD」という大枠でくくられても、症状の現れ方や困難さの程度は人それぞれです。
自分の特性を理解したい、どうすれば生きやすくなるのか知りたい、という思いからカウンセリングを訪れる方も増えています。
「変わった人」じゃない:ASDの代表的な5つの特性

「感覚の過敏さ」
ASDには、いくつかの共通した特性が見られます。これらは、決して「おかしいこと」ではなく、その人独自の個性として現れるものです。
1. 人との関わりが苦手な「社会性の特性」
乳幼児期には、親が呼んでも目を合わせなかったり、周りの子に関心を示さなかったりすることがあります。この時期は「おとなしい子」と見過ごされがちです。
成長するにつれて、人との関わりを避けたり、逆に積極的に関わりすぎて、相手との適切な距離感がわからなくなったりすることがあります。
「目が合わない」「興味のあることしか話さない」といった行動は、「人の気持ちが読めない」「他人に対して無関心」といった、社会性の特性として見られることがあります。
2. コミュニケーションが難しい「相互の特性」
言葉の発達がゆっくりなこともあります。
話せるようになっても、場面にそぐわない独り言を言ったり、人から話しかけられた言葉をオウム返しにしたりすることがあります。
大人になっても、相手の意図を汲み取った会話が苦手で、ユーモアや皮肉、比喩表現を言葉通りに受け取ってしまい、人間関係でトラブルになることもあります。特に日本語は「察する」「空気を読む」といった、曖昧な表現が多いため、こうした困難さがより際立つことがあります。
3. 「空気が読めない」のはなぜ?:想像力の特性
私たちは通常、相手の表情や声のトーン、姿勢などから、その人が何を考えているのか無意識的に察しようとします。しかし、ASDの人はそれが非常に困難です。
「相手が何を考えているかわからない」「その場の空気が読めない」といったことは、この想像力の特性から起こります。
4. 譲れないこだわりを持つ「反復行動の特性」
特定の物事に著しい興味を示し、熱中することがあります。
たとえば、同じおもちゃを回し続けたり、道路標識や数字をすべて覚えてしまったり。周りから見ると「意味のないこと」に思えても、本人は飽きることなく集中し続けます。
また、物事の順序や位置に強いこだわりを持つこともあります。
家具の位置や日々のルーティンが変わると、強い不安や動揺を感じ、元の状態に戻そうとする傾向があります。
5. 感覚が極端な「感覚過敏・鈍麻の特性」
音、匂い、痛みなどの感覚を脳がうまく処理できないため、普通の人とは異なる反応を示すことがあります。
例えば、味覚や嗅覚が人と極端に違うため、極端な偏食につながることがあります。特定の音に過剰に反応して耳をふさいでしまったり、逆に痛みや温度に鈍感で、ケガをしていても気づかなかったりすることもあります。
ASDの人が抱えがちな「生きづらさ」と二次的な問題

「生きづらさ」
ASDの特性は、日常生活でさまざまな「生きづらさ」を引き起こすことがあります。また、特性が原因となって、別の問題を引き起こしてしまうことも少なくありません。
併発しやすいさまざまな問題
ASDの方のおよそ30〜40%には知的障害が併存するといわれています。また、児童期や青年期には、注意欠如・多動症(ADHD)、てんかん、限局性学習症(SLD)などを併せ持つこともあります。
さらに、ASDの子どもの約80~90%が睡眠障害を持つと言われています。寝つきが悪く、夜中に何度も目が覚めてしまうため、生活リズムが不健康になりがちです。
誤解と孤立が招く「二次障害」
「目に見えない障害」である発達障害は、周囲から理解されにくいという現実があります。
「変わった人」「空気が読めない人」と誤解され、いじめや孤立を経験することも少なくありません。
こうした経験から、自己肯定感が低くなり、「自分はダメな人間だ」と自己嫌悪に陥ったり、うつ病や適応障害などの精神疾患を二次的に発症したりすることがあります。
家族が抱える悩みと孤立
子育てにおいて、わが子の言動が理解できず、どう接したらいいか分からなくなる親御さんも少なくありません。
「私の育て方が悪かったせいだ」と自分を責めたり、周囲の理解が得られず、夫婦や親族との関係が悪化してしまったりすることもあります。
「普通の子ども」との違いに戸惑い、人目を気にして子どもの特性を隠そうとしてしまう親御さんもいます。その結果、強い孤独感や疲労を抱え、心身の不調につながる場合もあります。
親子で育む:ASDの子どもと向き合うためのヒント
ASDの子どもは、独特な感覚を持ち、思わぬことで動揺したり、周囲の空気を読むのが苦手だったりします。そのため、コミュニケーションが難しく、親御さんは疲弊してしまうことも少なくありません。
しかし、子どもの特性を理解し、適切な対応をすることで、子育ての負担を軽減し、親子関係をより良いものにすることができます。
1. 独特なルールを尊重する
ASDの子どもは、自分の中の「ルール」に沿って行動することがあります。
たとえば、決まった道順でしか歩きたがらない、お風呂に入る順番が決まっている、など。
こうしたルールを無理に変えようとすると、子どもは強い不安を感じ、パニックになってしまうことがあります。まずはそのルールを尊重し、安全な範囲内で見守ってあげましょう。
2. シンプルで明確な言葉を選ぶ
「ちゃんと片付けておいてね」といった抽象的な指示は、ASDの子どもには伝わりにくいことがあります。
「おもちゃをこの箱にしまってね」「脱いだ靴下を洗濯かごに入れてね」のように、具体的で、一つの行動に絞った指示をすることが大切です。
3. 感情を言葉で伝える練習をする
ASDの子どもは、自分の感情をうまく言葉にできないことがあります。
「今、〇〇(嫌なこと)だったんだね」「〇〇(うれしいこと)で笑っているんだね」のように、親が子どもの感情を言葉にしてあげることで、少しずつ自分の気持ちを理解し、表現できるようになっていきます。
4. 褒めることで自己肯定感を育む
うまくいかないことが多く、叱られる経験が多いと、子どもは「自分はダメだ」と感じてしまいます。
たとえ小さなことでも、「できたね!」「すごいね!」と具体的に褒めることで、子どもの自信と自己肯定感を育むことができます。
5. 専門機関や支援を利用する
「うちの子、ASDかな?」と心配になったら、一人で抱え込まずに、まずは専門機関に相談してみましょう。
ASDの特性は、3歳以前に現れることが多いため、1歳半健診や3歳児健診で気づかれることがあります。幼稚園や保育園、小学校での生活で気づくこともあります。
早期に「療育」(障害のある子どもの発達を促し、自立を助ける取り組み)につなげることで、生きるためのスキルを身につけ、社会生活をスムーズに送れるように支援することが可能になります。
アスペルガー症候群との違いは?:概念の移り変わりを理解する
少し前まで「アスペルガー症候群」という名称を耳にすることが多かったかもしれません。現在では、この名称は使われなくなり、すべて「ASD(自閉スペクトラム症)」に含まれるようになりました。
では、アスペルガー症候群とASDは、どう違うのでしょうか?
アスペルガー症候群は、対人関係やコミュニケーションに困難さが見られるものの、言葉の発達や知的な遅れがないことが特徴でした。
そのため、一見すると「少し変わった人」に見えるため、大人になるまで、ご本人も周囲の人も特性に気づかないことがあります。
特性を活かし、自分らしい生き方を輝かせる

「つながり」
「ASD」自閉スペクトラム症であれば、お母さんと話をしていても、この子は世間の子供と比較すると少し違うなぁと思うことがあります。しかし話ができないという訳でもなく、自分の主張などは勿論あるので、そこを上手く理解して受け止めてあげるといいでしょう。
また「ASD」自閉スペクトラム症の子は人の気持ちを考えることが苦手でもあるので、空気を全く読まない行動を起こしてしまう場合なども頻繁に起き、親御さんとしては友人関係などにハラハラドキドキと心配する部分も多くなると思います。
また、ASDの方の中には知的発達の遅れを伴う場合もあります。そのため学習面での困難がみられることもありますが、近年では教育機関や地域での支援体制が徐々に整備されつつあります。必要に応じて支援を受けることで、安心して学びを続けることができます。
「ASD」自閉スペクトラム症は3歳以前に特徴が現れることが多いため、1歳半健診や3歳児健診で発見される場合や幼稚園・保育園での生活、就学前健診、学校での生活場面などで気づくことにより、療育(障害のある子どもの発達を促し、自立して生活できるように援助する取り組み)につなげ、生活する術を早くから身に付けられるように支援することなどもメジャーになってきています。「普通」にならなければならないという重圧、周囲からの理解が得られない苦しみ、自分自身でも受け入れるのが難しい葛藤。ASDの人は、そうした困難を抱えながら日々を暮らしています。
「変わった人だね」と言われ、傷つくことも少なくありません。
しかし、決して「普通の人」になろうと無理をする必要はありません。あなたの特性は、あなたの個性であり、強みにもなりうるからです。
1. 専門機関や支援の活用
まずは、専門機関を受診し、自分の特性を正しく理解することが大切です。行政の支援制度や、同じ特性を持つ人と交流できるデイケアなどを活用することも有効です。
自分の発達には凹凸があることを知り、「苦手なこと」を無理に克服しようとするのではなく、「得意なこと」を伸ばす方向に目を向けてみましょう。
2. 周囲の理解とサポート
ASDの特性への認識は広まりつつありますが、具体的な理解や支援の整備はまだまだ始まったばかりです。
しかし、大掛かりな支援が必要なわけではありません。ほんの少しの周りの配慮や理解があるだけでも、生きづらさは大きく変わります。
自分を抑え込んで苦しむのではなく、家族や友人、職場の仲間など、身近な人に自分の特性について知ってもらうことで、協力を得やすくなります。
3. 得意を伸ばす生き方
ASDの人は、特定の分野に驚くほどの集中力や探究心を発揮することがあります。
例えば、プログラマー、研究者、芸術家など、自分の得意なことを活かして活躍している人はたくさんいます。
人間は誰しも、得意なことと苦手なことがあります。体格も性格も、誰一人として同じ人はいません。
ASDという特性を抱えたままでも、周囲のサポートを得ながら、自分の得意を伸ばし、自分らしく輝いて生活することは十分に可能です。
もう一人で悩まない:疲れた心に寄り添うカウンセリング

「自分らしさ」
わが子の対応に疲れてしまった時、あるいは「自分はASDなのでは?」と不安になった時、一人で抱え込んでいませんか?
「普通の子とは少し違う」と感じ、必要以上に心配してしまう気持ち、とてもよくわかります。
しかし、案外、親御さんが心配しすぎているだけで、一般的な子どもの範囲内であることも多いものです。
「ASDと言われてしまった」「アスペルガーなのでは?」と不安になったら、カウンセラーや気の許せる友人、配偶者など、誰かに話を聞いてもらい、ストレスを溜め込まないようにしましょう。
もちろん、診断が確定している場合でも、一人で頑張る必要はありません。
「どうすれば子どもが生活しやすくなるか」を一緒に考え、行動するお手伝いをさせてください。
大阪聖心こころセラピーでは、発達障害やASDに精通したカウンセラーが、あなたの悩みに寄り添い、解決の道へと導きます。
あなたも、そしてあなたの大切な人も、生き生きと生活できるように、私たちは全力でサポートします。
「自分の特性を理解したい」「子育ての悩みを話したい」
そう思った時は、いつでもお気軽にお問い合わせください。
◆関連記事 親子問題・親子関係 大人の愛着障害 ADHD トラウマ
参考文献・参考資料
- 傳田健三(2017) 自閉スペクトラム症(ASD)の特性理解 心身医学 57巻 1号
- 下山晴彦・黒田美保(監修)・高岡佑壮(著)(2021)『発達障害のある人の「ものの見方・考え方』 ミネルヴァ書房
- アメリカ精神医学会(著),日本精神神経学会(監訳)(2023)『DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル テキスト改訂版』 医学書院


