ADHDカウンセリング
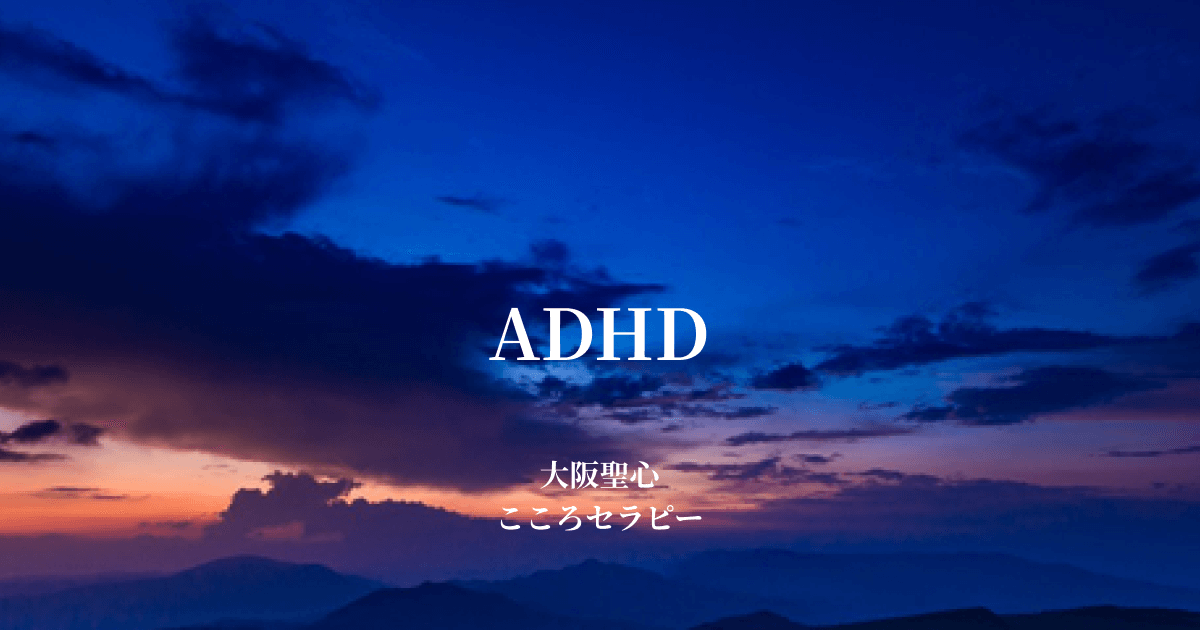
ADHDの専門カウンセリング|臨床心理士・公認心理師が解決に導きます
ADHD専門カウンセリング
臨床心理士・公認心理師
が解決に導きます
ADHD(注意欠如・多動症)とは、「不注意」「多動性」「衝動性」という特徴が現れる神経発達症のひとつです。生まれつきの脳機能の特性に加え、環境要因との相互作用によって日常生活に困難が生じることがあります。心の病ではなく、発達のあり方の違いとして理解されており、本人だけでなく周囲の人の理解や支援が大切です。
関連性のあるテーマ
当カウンセリングは、診断や治療といった医療行為を行うものではありません。臨床心理士や公認心理師といった専門資格を持つカウンセラーが、認知行動療法などの心理療法を用い、様々な問題で悩む方々に対し、ご自身の心と向き合い、不安のメカニズムを理解し、日常生活をより穏やかに過ごすための専門的なサポートを提供します。
本記事は、アメリカ精神医学会(APA)が発行する『DSM-5-TR:精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版 改訂版』に基づき、臨床心理士が専門的知見のもとに執筆・監修しています。本内容は診断や医療行為を目的としたものではなく、カウンセリングにおける理解を深めるための情報提供としてご利用ください。
知っているようで知らないADHD
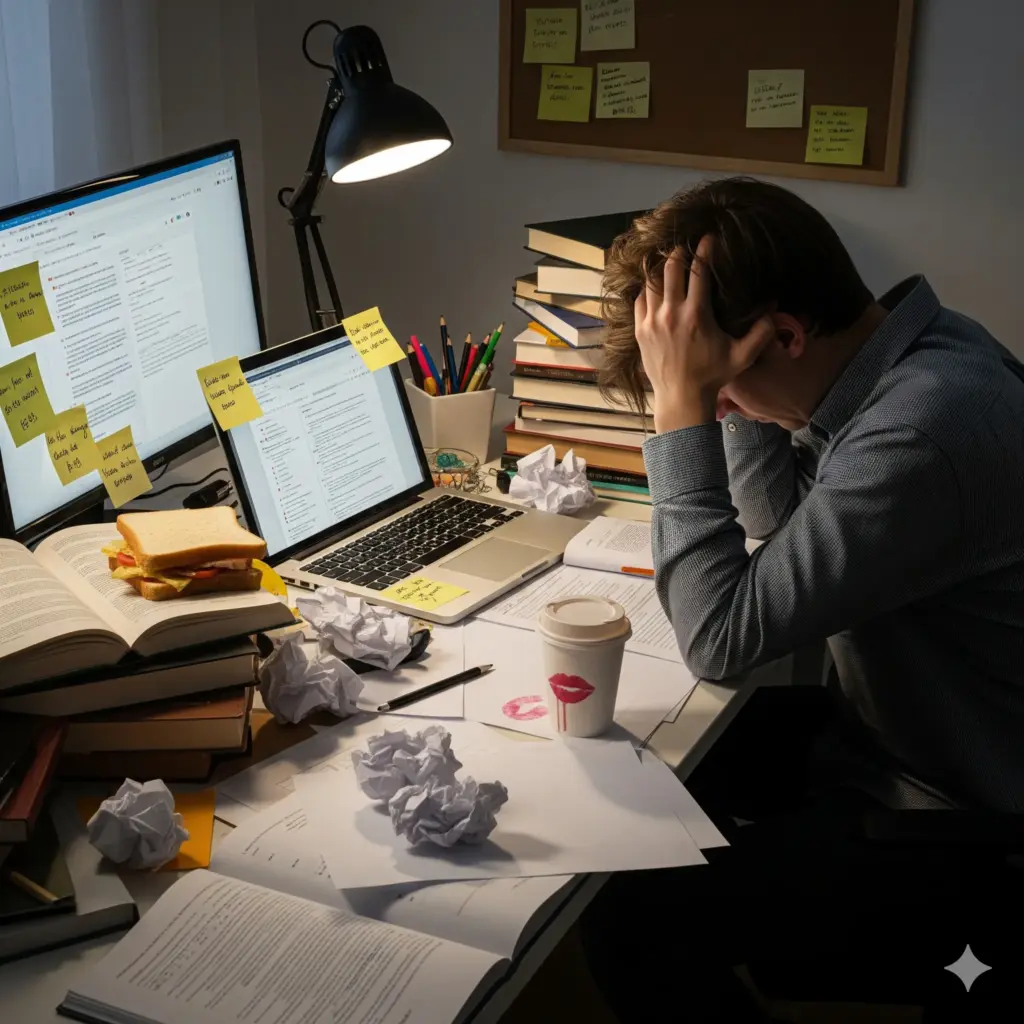
「不注意」
注意欠如・多動症(ADHD)は、「不注意」「多動性」「衝動性」という3つの特性が単独、または重複して現れる発達障害です。以前は「注意欠陥・多動障害」とも呼ばれていましたが、現在はこの呼び方が主流です。
発達障害とは、生まれつきの脳の機能的な特性が原因で、発達の仕方が一般的な人と異なる状態を指します。多くのケースでは、幼少期にその兆候が現れ、保護者が「うちの子は他の子と少し違うな」と感じることで、医療機関の受診をきっかけに判明します。しかし、発達障害にはいくつかのタイプがあり、同じ診断名でも現れる症状や困難は人それぞれです。
近年、「大人の発達障害」という言葉がメディアで取り上げられ、生きづらさやコミュニケーションの難しさが発達障害に起因することに気づく大人が増えています。子どもの頃は「個性」として見過ごされていた特性が、就職や結婚といった人生の節目で強く現れ、診断に至るケースも珍しくありません。
ADHDによる困難は、幼少期の親子関係の影響で増幅する場合があります。関連内容は親子問題・親子関係をご覧ください。
また、集中できない/落ち着けない背景には、愛着の不安定さが影響することがあります。詳しくは大人の愛着障害をご一読ください。
発達障害の正しい知識を持つことは、生きづらさの根本的な原因を理解し、適切な対処法や支援を見つけるための第一歩となります。もしご自身やご家族、身近な人がADHDに悩んでいるなら、その特性を理解し、前向きな解決策を探すことが何よりも重要です。
ADHDの3つの主要な特性を理解する
ADHDは、DSM-5-TRにおいて「12歳以前にいくつかの症状が存在していること」が診断基準の一つとされています。実際には、幼少期に気づかれず、大人になってから診断されるケースもあります。特に集団生活が始まる小学校入学後の6~7歳は、友人や教員といった人と人との関わりの中で困難が生じやすくなります。
ADHDの特徴としては、「不注意」「多動性」「衝動性」の3つが挙げられます。学校や職場などで忘れ物が多く叱られている様子や、席を立ちふらふらと歩きまわる姿、思いついたことをすぐに口に出してしまうクラスメイトや職場仲間がいたことはないでしょうか。
幼稚園、保育園、学校、職場では集団生活や対人関係は避けて通れません。周囲の人は急に話し出したり、動き回ったり、順番が守れないことが続くと、驚き戸惑ってしまいます。しかし、物事にまったく集中できない訳ではありませんし、勉強や仕事もこなすことができ、友達と元気よく遊ぶこともできます。
家族や周りの人がADHDの特徴を理解し、難なく過ごせる環境や関係を作ることで、お互いに気持ちよく生活することができます。人であれば誰しも個性があるのは当然です。ADHDでも同じことです。子供であれ伴侶であれ同僚であれ、周囲の理解や受容があれば、社会の一員として力を発揮できる能力は十分にあります。
不注意優勢型ADHD:うっかりミスは日常茶飯事

「多動性・衝動性」
多動・衝動性優勢型は、「多動性」と「衝動性」の特性が強く現れるタイプです。常に落ち着きがなく、突発的な行動を起こしてしまうため、周囲を驚かせることも少なくありません。
- 多動性: じっと座っているのが困難で、授業中や会議中に席を離れたり、そわそわと身体を動かしたりします。
- 衝動性: 考えずにすぐ行動してしまうため、相手の話が終わる前に話し出してしまったり、急に走り出したりすることがあります。
このタイプの特性は、幼少期に顕著に現れることが多く、「落ち着きのない子」として周囲から注目されやすい傾向があります。
多動・衝動性の特性を持つ人へのサポートにおいては、叱って罰するよりも、ポジティブな声かけと環境調整が効果的です。
- 運動を取り入れる: 身体を動かす活動を積極的に取り入れることで、溜まったエネルギーを発散させることができます。
- 良い行動を褒める: 望ましくない行動を叱るのではなく、望ましい行動ができたときに具体的に褒めることが大切です。
- ゲーム感覚で目標達成: 達成できたことを可視化するために、ポイントカードやシールを活用するのも良い方法です。
ADHDは親のしつけや育て方の問題ではない
ADHDを含む発達障害は、親のしつけや育て方が原因で起こるものでは決してありません。これは、脳の機能的な特性であり、生まれつきのものです。
かつては「親の育て方が悪いから」と心ないことを言われる時代もありましたが、医学的な研究が進んだ現在では、この認識は完全に否定されています。しかし、見た目には分かりにくい障害であるため、誤解や偏見から親が周囲から非難されるケースは依然として存在します。
もちろん、子どもの発達をサポートするために、家族や周りの大人の関わり方は非常に重要です。ADHDの特性を理解し、その子に合ったサポート方法を一緒に考えていく必要があります。
本人も困っている:自己肯定感の低下と二次障害
ADHDの特性は、周囲だけでなく、何よりも本人を苦しめます。
子どもの頃から「どうして自分はみんなと同じようにできないんだろう」「いつも叱られてばかりだ」という経験を繰り返すと、自己肯定感が著しく低下してしまいます。このような状態は、心理的な虐待と似た環境を作り出し、子どもの心に深い傷を残します。
自己肯定感が低いまま成長すると、「二次障害」を引き起こすリスクが高まります。
- うつ病や不安障害: 精神的なストレスが蓄積し、精神疾患を発症することがあります。
- 非行: 「どうせ自分なんて」という投げやりな気持ちから、非行に走ってしまうケースもあります。
- 対人関係の悪化: 特性が原因で、友人や家族との関係がうまくいかず、孤立してしまうことがあります。
二次障害を予防するためには、早期にADHDの特性を理解し、適切な支援を始めることが非常に重要です。
大人になって直面する生きづらさ

「生きづらさ」
子どもの頃は周囲のサポートで生活できたとしても、大人になり、自立した社会生活を送るようになると、新たな生きづらさを感じるようになります。
職場や家庭では、より複雑な協調性やコミュニケーション能力が求められます。不注意の特性から仕事のミスが多かったり、衝動的な言動で人間関係が悪化したりすることがあります。
しかし、ADHDの特性は見方を変えれば長所にもなり得ます。フットワークの軽さや行動力は、新しいプロジェクトを立ち上げる際に大きな力となります。また、一つのことに集中できない特性は、複数のタスクを切り替えながらこなすマルチタスク能力として活かせるかもしれません。
ADHDの生きづらさを乗り越えるヒント:理解と支援の活用

「強みや希望」
ADHDの特性は、必ずしもマイナス面だけではありません。状況や工夫次第で強みとして活かせる可能性もあります。自分の特性を理解し、周囲と協力しながら適切な環境を整えることで、持ち味を発揮しやすくなります。
- 多動性:
→ フットワークが軽く、行動力がある
- 衝動性:
→ 物怖じせず、新しいことに挑戦できる
- 不注意:
→ 複数のことに興味を持ち、物事の切り替えが早い
社会全体が「誰一人として取り残されない」ことを目指し、発達障害への理解や支援制度は年々進んでいます。発達障害は、その人が生まれつき持っている「個性」の一つと捉えることが大切です。
ADHDの特性を抱える人が、生きづらさを感じずに生活するためには、周囲の理解と、社会的な支援の活用が欠かせません。
- 支援制度の活用: 学校では通級指導教室などを利用し、専門のカウンセリング機関で具体的な対処法を学ぶこともできます。
- 環境調整: 集中しやすい環境を整えることが大切です。
- 家庭での工夫: 物の定位置を決めたり、物を少なくしたりして、忘れ物や紛失を防ぎます。
もしも生きづらさを感じたら:カウンセリングという選択肢

「理解とサポート」
子どものADHDへの対応に疲れ果ててしまった保護者の方、あるいはご自身がADHDの特性で生きづらさを抱えている方、一人で悩みを抱え込まないでください。
聖心こころセラピーは、そうした方々の心の支えとなる存在でありたいと考えています。
カウンセリングは、あなたの悩みを安心して話せる場所です。日々の心労を吐き出し、気持ちを軽くすることができます。また、これまでの生きづらさの原因を専門家と一緒に探り、これからの人生をより良くするための具体的な方法を見つけることができます。
「うちの子はADHDかもしれない」「大人のADHDかも?」と不安に思っている方も、ぜひお気軽にご相談ください。当セラピーには、発達障害やADHDに関する深い知識を持ったカウンセラーが在籍しており、あなたの悩みに寄り添い、解決への道筋を共に探していきます。
ADHDの特性は病気のように「治す」ものではありませんが、自分に合った工夫や支援を取り入れることで、生きづらさを大きく軽減することができます。その付き合い方を学ぶ場所として、カウンセリングは非常に有効な手段です。
大阪で発達障害やADHDの悩みに関するカウンセリングをお探しでしたら、ぜひ聖心こころセラピーにお越しください。私たちは、あなたが自分らしい人生を歩んでいくためのサポートをいたします。
◆関連記事 親子問題・親子関係 大人の愛着障害 ASD 不安症
参考文献・参考資料
- 小野次朗・上野一彦・藤田継道(編)(2007)『よくわかる発達障害[第2版]LD・ADHD・高機能自閉症・アスペルガー症候群』 ミネルヴァ書房
- 齊藤卓弥(2018) 注意欠如・多動症(ADHD)の子どもから成人への連続性 精神神経学雑誌 120巻 11号
- アメリカ精神医学会(著),日本精神神経学会(監訳)(2023)『DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル テキスト改訂版』 医学書院


