解離性障害カウンセリング
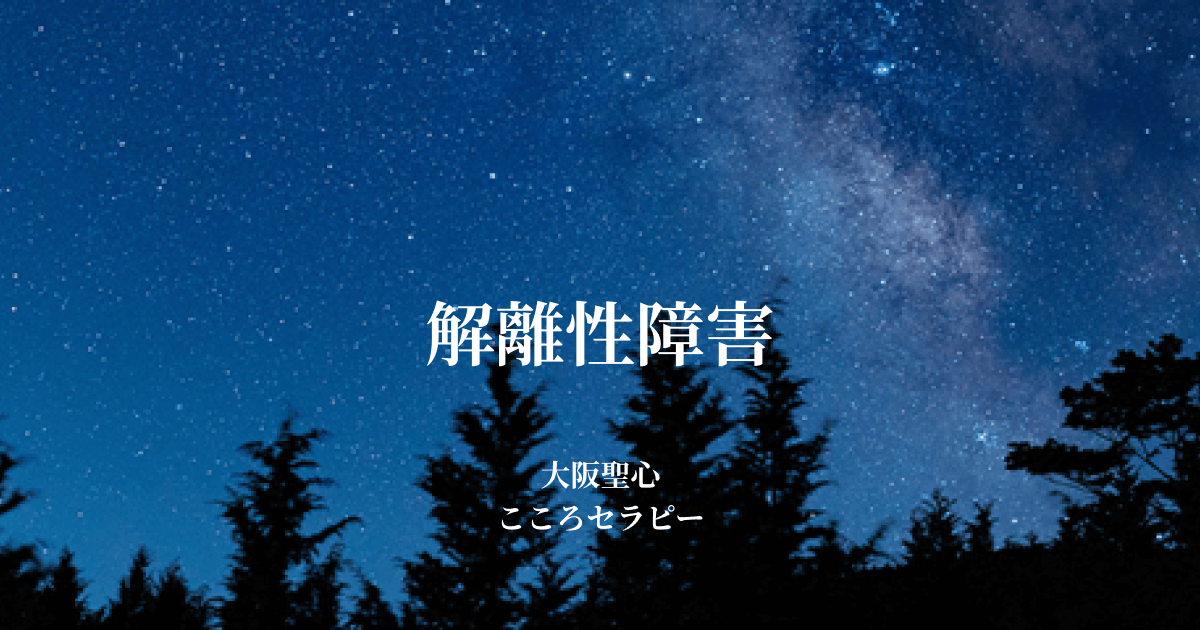
解離性障害の専門カウンセリング|臨床心理士・公認心理師が解決に導きます
解離性障害専門カウンセリング
臨床心理士・公認心理師
が解決に導きます
解離性障害とは、強いストレスやトラウマ体験などをきっかけに、意識・記憶・感情・自己感覚などが一時的に分離してしまう心の障害です。記憶が抜け落ちたり、自分が自分でないように感じたり、現実感が失われたりすることがあり、日常生活に支障をきたす場合に診断されます。
関連性のあるテーマ
当カウンセリングは、診断や治療といった医療行為を行うものではありません。臨床心理士や公認心理師といった専門資格を持つカウンセラーが、認知行動療法などの心理療法を用い、様々な問題で悩む方々に対し、ご自身の心と向き合い、不安のメカニズムを理解し、日常生活をより穏やかに過ごすための専門的なサポートを提供します。
本記事は、アメリカ精神医学会(APA)が発行する『DSM-5-TR:精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版 改訂版』に基づき、臨床心理士が専門的知見のもとに執筆・監修しています。本内容は診断や医療行為を目的としたものではなく、カウンセリングにおける理解を深めるための情報提供としてご利用ください。
解離性障害とは?症状や原因、克服への道筋を詳しく解説

「内面と外面の乖離」
「自分が自分でないみたい」「記憶が抜け落ちている」「知らないうちに全く違う場所にいる」――もし、そんな不可思議な体験をしていたら、それはもしかしたら「解離性障害」かもしれません。
解離性障害は、精神的なショックやストレスから自分自身を守ろうとする心の働きが、過剰に働いてしまうことで起こると考えられています。その症状は多岐にわたり、周囲の理解を得られにくいことから、一人で苦しんでいる方も少なくありません。
この記事では、解離性障害とは何か、その種類や原因、そして克服に向けて何ができるのかを、専門的な知識を交えつつも、できる限り分かりやすく解説します。
つらい体験から心を守るために“感覚を切り離す”反応は、愛着不安と関連することがあります。詳しくは大人の愛着障害をご覧ください。
また、解離は、過去のショック体験が大きな影響を与えている場合があります。トラウマもご一読いただくことで解離性障害への理解が深まります。
そもそも「解離」とは?意外と身近な心のメカニズム

「記憶の断片」
「解離」という言葉は、私たちの日常にも意外と深く関わっています。例えば、何かに夢中になっていて、声をかけられても気づかなかった経験はありませんか?あるいは、授業や会議中にぼんやりと空想にふけってしまい、話の内容が全く頭に入ってこなかった、ということもあるでしょう。
これらも、実は「解離状態」の一種です。このように、本来一つの意識としてまとまっているはずの「思考」「感情」「記憶」「行動」「自己感覚」などが、一時的に切り離されたり、統合されなくなったりすることを、心理学では「解離」と呼びます。
強いストレスや精神的なショックを受けた時に、この解離が著しく強くなると、記憶がすっぽり抜け落ちたり、「まるで他人事のように自分を外から見ている感覚」になったりすることがあります。この状態が慢性的に続き、日常生活に支障をきたすようになった場合、「解離性障害」と診断されるのです。
解離性障害の4つの主要なタイプとそれぞれの特徴

「心のトンネル」
解離性障害は、その症状によって主に4つのタイプに分類されます。それぞれの特徴を見ていきましょう。
1. 離人症性障害と現実感喪失症
「自分が生きているという実感が持てない」「まるで映画の中にいるようだ」といった感覚に悩まされるのが、このタイプの特徴です。離人症性障害はさらに、自身の体や心から自分が切り離されたように感じる「離人症」と、周囲の風景や環境が非現実的に感じられる「現実感喪失症」に分かれます。
この感覚は、他の解離性障害と併発しやすい症状であり、不安や抑うつに次いで多くの人が経験する精神症状の一つとも言われています。以下のような感覚が繰り返し起こり、日常生活に支障をきたしている場合は、この障害の可能性を考える必要があります。
- 自分の感情や考え、体から自分が離れて、外から傍観している感じがする
- まるで夢の中や霧の中にいるように、周囲が非現実的に見える
- 上記の感覚が何度も起こる、あるいは継続している
- この状態によって、自分自身が著しい苦痛を感じ、仕事や学業、人間関係に支障が出ている
2. 解離性健忘と解離性遁走
解離性健忘は、大きなショックやトラウマとなる出来事、あるいはその周辺の出来事に関する重要な記憶が、全く思い出せなくなってしまう症状です。単なる「物忘れ」とは異なり、自分の名前や年齢、家族に関する情報など、絶対に忘れるはずのない個人情報が抜け落ちてしまうことがあります。
この健忘が原因で、無意識のうちに家や職場から突然姿を消してしまうのが「解離性遁走(とんそう)」です。本人は自分がどこから来たのか、なぜここにいるのかを覚えておらず、新しい場所で全く別の人生を始めてしまうケースもあります。
周囲の人は、本人が普通に生活を送っているように見えるため、この障害に気づくことは非常に困難です。そして、ある日突然、失踪する前の記憶を取り戻し、逆に失踪後の記憶がなくなってしまう、という不可思議な現象が起こることもあります。
3. 解離性同一性障害(多重人格)
かつて「多重人格障害」と呼ばれていたのが、この解離性同一性障害です。この障害では、まるで別人格が自分の中に複数存在しているかのように、それぞれが交代で行動を支配します。
それぞれの「人格」は、固有の思考や感情、記憶、行動パターンを持っており、交代するたびに名前や話し方、趣味やクセまで全く違うものになることもあります。この交代は本人の意思とは関係なく起こり、交代している間の記憶は、別の人格にはほとんどありません。
解離性同一性障害は、離人症や健忘といった他の解離性障害の症状も複合的に含む、より複雑なタイプです。この障害は、「境界性パーソナリティ障害」と間違われやすいことがあります。両者の大きな違いは、「誰が主体となって行動しているか」にあります。
- 境界性パーソナリティ障害: 他者に対する評価や感情が極端に変わり、それによって態度が豹変します。しかし、あくまでも「自分」という意識は一貫しています。
- 解離性同一性障害: 「自分」という意識そのものが入れ替わり、別人格が行動を支配します。
解離性同一性障害で複数の「人格」が表れるのは、辛い体験を一つにまとまった自分として受け止めきれないため、「痛み」や「悲しみ」をそれぞれの人格に分散させて、心の安定を保とうとする無意識の防衛手段だと考えられています。

4. 特定不能の解離性障害
上記に挙げた3つの診断基準には当てはまらないものの、解離性障害の症状が認められる場合に診断されるのが、この「特定不能の解離性障害」です。これは、必ずしも「軽症」という意味ではありません。症状が複合的で分類が難しい場合や、診断基準に満たないものの、明らかな解離症状が見られる場合に用いられます。
なぜ解離性障害は起こるのか?その原因と向き合い方

「心の風景」
解離性障害は主に心理社会的ストレスやトラウマ体験と関連して生じると考えられています。ただし、発症には個人の脆弱性や環境要因、発達的背景など複数の要因が関わり合っています。
一般的に、解離性障害を発症する人の多くは、幼い頃に以下のような強い精神的ストレスを経験しているという共通点があります。
- 虐待: 身体的・精神的な暴力、性的虐待
- ネグレクト: 育児放棄や無関心
- いじめ: 継続的な身体的・精神的苦痛
- 衝撃的な出来事: 目の前で起きた事故や事件、大切な人の死
幼少期は、まだ自分を守る力が未熟なため、衝撃的な出来事や逃げ場のない辛い環境に直面すると、脳は自分自身を守るために「その出来事と自分を切り離す」という防衛反応を起こします。
「この出来事は私に起こったことではない」「これは夢だ」と、現実を認識しないことで、耐え難い苦痛から逃れようとするのです。この防衛反応が慢性化することで、解離性障害へと発展していくと考えられています。
もちろん、大人になってから、事故や災害、犯罪被害といった極めて強いショックを経験することで発症する場合もあります。しかし、解離性障害は単一の原因で起こるわけではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発症することがほとんどです。


周囲から見ると「演技」?解離性障害の誤解と真実
解離性障害の症状は、周囲の人からすると不可解で、「まるで演技をしているのではないか?」と疑われやすいものです。特に、別人格が現れて行動や態度がガラリと変わったり、それまでの記憶が抜け落ちていたりする様子は、理解が難しいでしょう。
しかし、解離性障害の人が経験しているのは「意識が途切れている」状態です。
例えば、解離性同一性障害の場合、主導権を握っている人格が交代した時、それまでの人格の記憶はほとんどありません。そのため、昨日の自分の行動や言動を覚えていなかったり、周囲の人が困惑するような言動をとったりしてしまうのです。
この「記憶の途切れ」こそが、単なる演技や気まぐれな態度ではない、解離性障害の大きな特徴です。本人も「自分が何をしたのかわからない」という状況に苦しんでいることが少なくありません。
解離性障害の人が安定した社会生活を送るためには、まず本人、そして周囲の人がこの障害について正しく理解することが非常に重要です。
解離性障害の克服へ向けて―治療の鍵は信頼関係にあり

「信頼とつながり」
解離性障害には、根本的な治療薬は存在しないと言われていますが、それは決して治らないということではありません。適切なカウンセリングや心理療法を通じて、症状を改善し、自分らしい人生を取り戻すことは十分に可能です。
1. 治療者との信頼関係を築く
解離性障害の克服において、最も重要となるのが、治療者との間に揺るぎない信頼関係を築くことです。
解離性障害の根底には、過去に「自分の身に起こったつらい出来事」を無意識に封じ込めてきた歴史があります。その「封印された記憶」に触れることは、とても大きな苦痛を伴います。
そのため、安全だと感じられる治療環境と、心から信頼できる治療者の存在が不可欠なのです。安心して「本当の自分」をさらけ出せる関係性を築くことが、改善への第一歩となります。
2. 認知行動療法や潜在意識療法
解離性障害の治療では、さまざまな心理療法が組み合わされます。
認知行動療法やトラウマに焦点を当てた心理療法、安定化のための技法(潜在意識療法)など
これらの療法を通じて、なぜ強い解離が起きてしまうのか、その原因となっている「自分の気持ち」を少しずつ探っていきます。
3. 無理に記憶を呼び戻す必要はない
解離性障害の治療の過程では、無理に辛い記憶を呼び戻す必要はありません。むしろ安全な環境で少しずつ自己理解を深めることが重視され、治療の進め方は本人の状態や準備性に応じて調整されます。
「自分を自分でないように感じてしまう」という孤独感や、記憶が定まらないことへの混乱は、非常に辛いものです。しかし、一歩一歩、自分の人生を取り戻していくことで、生きていることの喜びや幸せを再び感じられるようになります。
4. 幸せな人生を取り戻すためのカウンセリング
解離性障害は、決して「特別な人」にだけ起こる病気ではありません。辛い環境の中で、自分の心を必死に守ろうとしてきた結果なのです。
大阪聖心こころセラピーでは、解離性障害に関する深い理解と豊富な経験を持った専門家が、お一人おひとりに合わせたカウンセリングを行っています。
- 「自分を覆い隠そうとする仮の自分」との決別
- 「自分が誰であるか分からない」という不安の解消
- 「人生を幸せに生きたい」という願いの実現
これらを目指し、共に歩んでいくことが、解離性障害の克服への一番の近道だと考えています。もし、自分自身や大切なご家族のことでお悩みであれば、一人で抱え込まず、私たちに一度ご相談ください。あなたの本来の輝きを取り戻すためのお手伝いをいたします。
参考文献・参考資料
- 岡野憲一郎(2015) 解離性障害をいかに臨床的に扱うか 精神神経学雑誌 第117巻 第6号
- アメリカ精神医学会(著),日本精神神経学会(監訳)(2023)『DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル テキスト改訂版』 医学書院



