大阪のパニック障害|また起きる恐怖へ 発作が来ても崩れない自分へ整えていく
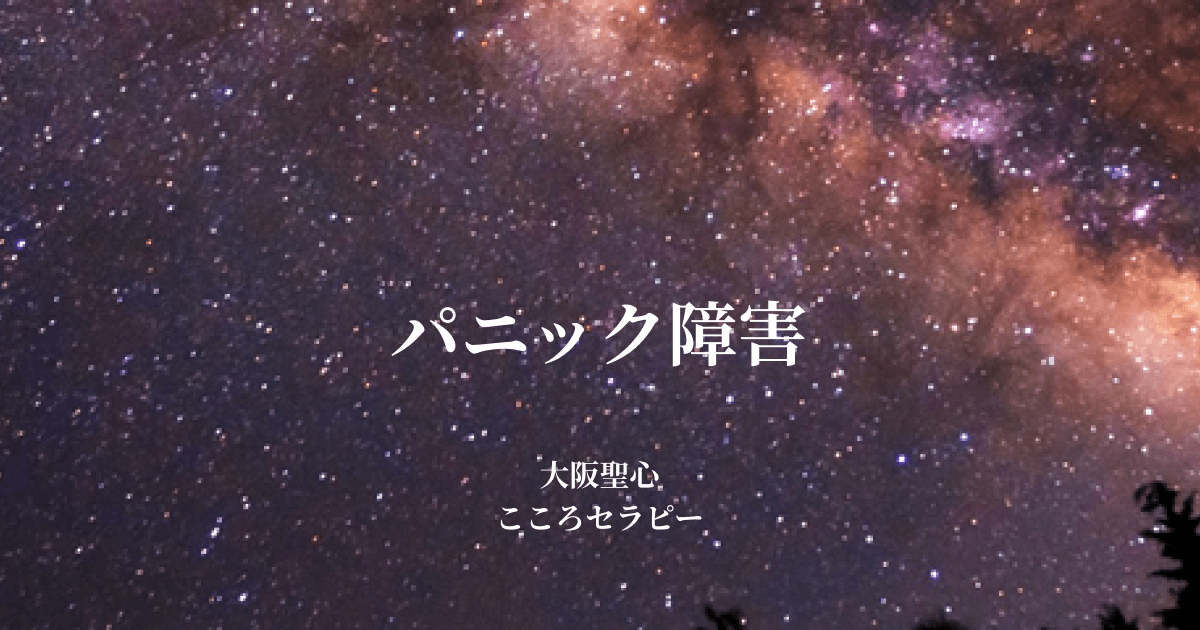
パニック障害の専門カウンセリング|臨床心理士・公認心理師が解決に導きます
パニック障害
専門カウンセリング
臨床心理士・公認心理師
が解決に導きます
パニック障害とは、突然の激しい不安や身体症状(動悸、息苦しさ、めまいなど)を伴う「パニック発作」を繰り返す状態であり、その発作が再び起きるのではないかという「予期不安」や、発作が起きた場所・状況を避ける「広場恐怖」を伴うことが多い不安障害の一つです。
関連性のあるテーマ
当カウンセリングは、診断や治療といった医療行為を行うものではありません。臨床心理士や公認心理師といった専門資格を持つカウンセラーが、認知行動療法などの心理療法を用い、様々な問題で悩む方々に対し、ご自身の心と向き合い、不安のメカニズムを理解し、日常生活をより穏やかに過ごすための専門的なサポートを提供します。
本記事は、アメリカ精神医学会(APA)が発行する『DSM-5-TR:精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版 改訂版』に基づき、臨床心理士が専門的知見のもとに執筆・監修しています。本内容は診断や医療行為を目的としたものではなく、カウンセリングにおける理解を深めるための情報提供としてご利用ください。
パニック障害「死んでしまうのではないか」

「パニック発作の恐怖と混乱」
「突然、心臓がバクバクして、息が苦しくなる」「めまいがして、このまま倒れてしまうかもしれない」──。もしあなたが、このような強烈な恐怖に突然襲われた経験があるなら、それはパニック障害かもしれません。
パニック障害は、まるで予期せぬ津波のように、私たちの心と体を一瞬で飲み込みます。突然、胸がドキドキと高鳴り、全身に冷や汗が流れ、手足が震える。まるで心臓発作でも起こしたかのような身体症状に襲われ、「このまま死んでしまうのではないか」という強烈な不安感に駆られます。
この体験が一度でもあれば、「また同じことが起こるのでは?」という恐怖に縛られ、次第にその場所や状況を避けるようになります。ひどい場合は、外出そのものが怖くなり、家から一歩も出られなくなることもあります。もし、このような恐怖があなたの日常生活や社会生活に支障をきたしているなら、それは紛れもなくパニック障害です。
急なパニック発作の背景には、幼少期の過緊張や家庭環境が影響している場合があります。詳しくは親子問題・親子関係をご一読ください。
さらに、突然の不安発作には、愛着不安が影響していることがあります。関連する内容は大人の愛着障害をご覧ください。
パニック障害は「不安症」の一つ
最近では「パニクった」という言葉を、少し慌てた状況を表す日常的な表現としてよく耳にします。しかし、本当のパニック障害は、そんな気軽なものではありません。それは、私たちの心に深く根ざした「不安」が、身体症状となって爆発する、れっきとした「不安症」の一つです。
パニック障害という言葉が日本で広く知られるようになったのは比較的最近のことですが、世界的にも約25年前に正式に不安障害の一種として認定されました。日本の調査では、およそ100人に1人がこの症状を経験すると言われています。ただし、これは医療機関で診断を受けた人の数に過ぎません。実際には、適切な治療を受けずに苦しんでいる人は、その数倍も存在すると考えられています。また、パニック障害は、男性よりも女性の方が圧倒的にかかりやすいという特徴があります。
パニック障害は、主に「パニック発作」「予期不安」「広場恐怖症」という3つの症状が組み合わさることで、まるで負のスパイラルのように悪化していきます。これらの症状を放置すれば、やがてあなたの生活はどんどん狭められ、身動きが取れなくなってしまうでしょう。
パニック発作の正体と誤解
パニック発作とは、強いストレスを感じる環境や状況に置かれたときに、突然、身体的な異常を感じ、わけのわからない恐怖や不安に襲われ、混乱してしまう症状です。
その症状は多岐にわたります。
- 胸がドキドキと高鳴る
- 息が苦しくなる、過呼吸になる
- めまいがする、ふらつく
- 手足が震える、しびれる
- 大量の汗をかく
- 吐き気がする
- 死んでしまうのではないかという恐怖に襲われる
- 気がおかしくなるのではないかと心配になる
- 自分が自分ではないような感覚(離人感)
このような症状が、理由もなく突然起こります。そして、パニック発作のやっかいな点は、これらの症状が身体的な病気によるものではないことです。病院で精密検査をしても、心臓や脳などに異常は見つからないことがほとんどです。そのため、「気にしないように」と軽いアドバイスで済まされてしまうことも少なくありません。また、発作は通常10分から1時間以内に治まるため、病院にたどり着いた頃には症状が消えていることも、誤解を招く一因となっています。
予期不安という心の呪縛

「予期不安と孤立」
一度でもパニック発作を経験すると、あなたの心には「予期不安」という新たな恐怖が生まれます。
予期不安とは、文字通り「まだ起こっていない出来事に対して、あらかじめ悪いイメージを作り上げてしまう」ことです。
「また、あの発作が起こったらどうしよう」 「次は本当に死んでしまうかもしれない」 「もし外出中に倒れたら、周りに迷惑をかけてしまう」
こうした発作への強い不安感が、あなたの心を支配し始めます。発作がなぜ起きたのか分からないからこそ、あれこれとマイナスの想像を巡らせてしまうのは、ごく自然なことです。この予期不安は、発作を繰り返すたびにどんどん強くなり、あなたの行動を制限する大きな要因となります。
広場恐怖症による生活の制限

「広場恐怖」
予期不安が強くなると、次に現れるのが「広場恐怖症」です。これは、不安を軽くするために、特定の場所や状況を避けるようになる状態です。
例えば、
- 電車やバス、エレベーターなど、すぐに逃げられない閉鎖空間
- 高速道路や人混みなど、助けを求めにくい場所
- 発作を起こしている姿を人に見られたくないため、人が多く集まる場所
これらの場所や状況を避けるようになり、次第にあなたの生活圏は狭まっていきます。広場恐怖症は、特定の場所だけを避ける人もいれば、付き添いがいれば外出できる人、完全に家から出られなくなる人まで、その症状には個人差があります。予期不安があるからといって、必ずしも広場恐怖症を発症するわけではありませんが、パニック障害の負のサイクルを加速させる大きな要因です。
パニック障害の根本にある原因とは
パニック障害の原因は、まだ完全には解明されていません。しかし、単に「気の持ちよう」や「性格の問題」だけではなく、脳内環境の変化が大きく関わっていると考えられています。
脳内の神経伝達物質(セロトニン、ノルアドレナリンなど)のバランスが崩れると、不安を感じやすい状態になり、パニック発作が起こりやすくなります。だからこそ、パニック障害は心の問題だけでなく、脳の機能に働きかける「薬物療法」と、心の状態を整える「精神療法・心理療法」を併用することが、根本的な改善に繋がるのです。
パニック障害に効果的な改善療法
薬物療法
パニック発作や予期不安を抑えるために、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)などが用いられます。薬物療法によって症状が徐々に軽減されてきたら、医師の指示に従い、少しずつ薬の量を減らしていきます。この段階で、大阪聖心こころセラピーのような専門機関と連携し、心の側面からアプローチする心理療法を並行して行うことが大切です。
精神療法・心理療法
パニック障害は、正しい知識と適切な対処法を身につけることで克服できる病気です。精神療法では、認知行動療法や催眠療法などを通じて、パニック障害への不安や恐怖を和らげていきます。
- パニック障害の正体を知る: 「なぜ発作が起きるのか」「どんな状態なのか」を正しく理解することで、漠然とした恐怖を具体的な対処可能なものとして捉えられるようになります。
- 考え方のクセを修正する: 「もし発作が起きたら…」というマイナスの思考パターンを修正し、「これは発作の症状だ。深呼吸すれば大丈夫」と、冷静に自己を観察するメンタルトレーニングを行います。
認知行動療法
パニック障害の認知行動療法では、主に以下の手法を用います。
1. 認知再構成法
パニック発作が起きるような状況で、あなたがどのような考え(認知)を持つかを明らかにし、その考え方が発作を悪化させている可能性を認識します。「このまま死んでしまう」という極端な考えを、「発作はつらいけど、命にかかわるものではない」という合理的な考えに変えていく訓練です。
2. 暴露療法
あなたが避けている場所や状況にあえて身を置き、その環境に慣れていくことで恐怖を克服する行動療法です。例えば、電車に乗るのが怖いなら、まずは1駅だけ乗ってみる、次の日は2駅と、少しずつ行動範囲を広げていきます。
「怖い」という気持ちを克服するには、相当な勇気と覚悟が必要です。しかし、カウンセラーと二人三脚で、安全な環境で少しずつステップアップすることで、あなたは再び自由に行動できるようになるでしょう。
パニック障害になりやすい人の特徴
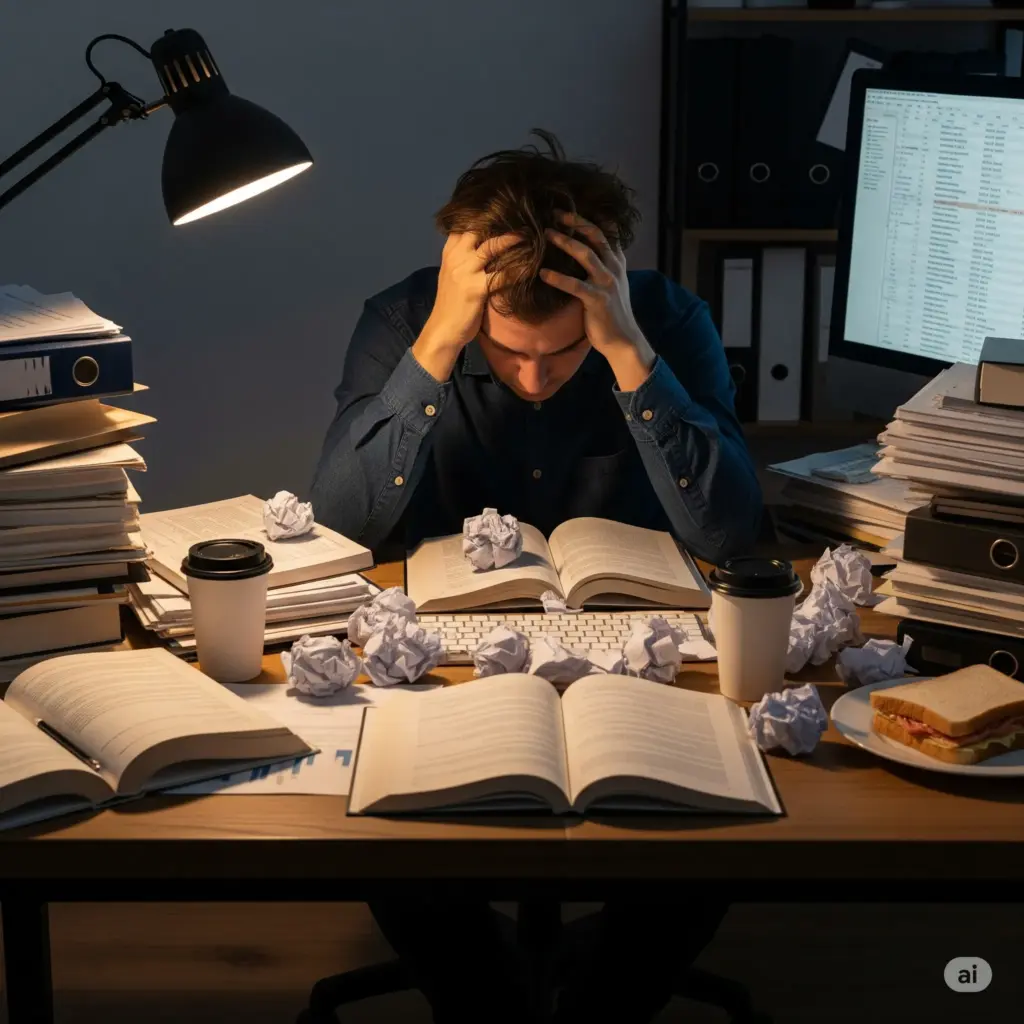
「ストレスと疲労」
気づかないストレスを抱え込む人
パニック障害に苦しむ人の多くは、家事や仕事に真面目に取り組み、責任感が強い傾向があります。そのため、無理を重ねて心身ともに疲れ果てているにもかかわらず、そのストレスに気づいていないケースが少なくありません。日々の忙しさに追われ、自分を労わる時間もなく、知らず知らずのうちにストレスを蓄積させてしまいます。
完璧主義者
「何事も完璧にこなさなければ」と考える完璧主義な人も、パニック障害に陥りやすい傾向があります。自分の基準が高すぎるため、少しでもうまくいかないと自分を責めてしまい、それが大きなストレスとなります。また、他人の顔色をうかがい、常に緊張した状態で過ごしている人も、パニック発作を起こしやすい環境にあると言えます。
繊細で優しい人
「他人に迷惑をかけてはいけない」と、自分のことよりも他人のことを優先する、繊細で優しい人もパニック障害になりやすい傾向があります。このような人は、自分の感情を押し殺してしまいがちです。パニック障害を発症すると、他人との接触を避けるようになり、対人恐怖症やうつ病を併発することもあります。
悲しい出来事を経験した人
パニック障害の引き金となる原因として、近親者の死や大切な人との別れなど、喪失体験が挙げられることもあります。深い悲しみや不安を一人で抱え込み、それが限界に達したときに、パニック発作として現れることがあります。
日常生活でできるパニック障害への対処法
適切な休息と睡眠
身体的な疲労は、パニック発作の引き金となりやすいです。毎日忙しい日々を送っている人は、意識して休息を取り、最低でも7時間以上の睡眠を確保するように努めましょう。身体の疲れをしっかりと癒すことが、パニック発作を和らげる効果が期待できます。
嗜好品との付き合い方
タバコやお酒、コーヒーなどを習慣的に摂取している人も注意が必要です。カフェインは脳を刺激し、心拍数を高める作用があるため、パニック発作を誘発する可能性があります。摂取量に気をつけ、体調がすぐれないときは控えるようにしましょう。
呼吸法で心を落ち着かせる
パニック発作が起きたら、まずは落ち着いてゆっくりと深呼吸をしましょう。ベンチなどに座り、パニック発作が過ぎ去るのを待ちます。発作は数十分程度で収まります。パニック発作で死ぬことはありませんので、「大丈夫、死なない」と自分に言い聞かせ、呼吸に意識を集中させましょう。
ストレスをため込まない
ストレスの対象から距離を置いたり、ストレスの原因となる人間関係を見直したりすることも大切です。また、つらい気持ちや怒りの感情を一人で抱え込まず、信頼できる誰かに話すことで、心にたまった重荷を軽くすることができます。
パニック障害とカウンセリング

「カウンセリングと心の安定」
パニック障害は、「心の病」でありながら、身体的な症状を伴う複雑なものです。一人で悩みを抱え込んでいると、「いつまた発作が起こるだろう」という予期不安に囚われ、どんどん行動範囲が狭まってしまいます。
そんなときは、大阪聖心こころセラピーのような専門的なカウンセリングの力を借りてみませんか。カウンセリングでは、あなたの心に漠然と存在する不安や恐怖の正体を一緒に探り、それを克服するための具体的な方法を一緒に見つけていきます。
カウンセリングでできること
- パニック障害の正しい理解: 発作が起きるメカニズムや、心の状態との関係性を理解することで、「自分は変な病気ではない」という安心感を得られます。
- ストレスの原因を特定: 自分では気づいていないストレスの根源を、カウンセラーとの対話を通して見つけ出し、対処法を検討します。
- 思考パターンの修正: ネガティブな感情に支配されやすい思考を、前向きなものに変えていくための具体的な訓練を行います。
- 行動範囲を広げるサポート: 暴露療法などを通して、一人で外に出るのが怖いという気持ちを乗り越え、少しずつ行動範囲を広げられるよう、段階的にサポートします。
パニック障害は、決して治らない病気ではありません。正しい知識を持ち、適切な治療とカウンセリングを継続すれば、必ず改善に向かいます。一人で怖いと悩まず、心の重荷を専門家に預けてみてください。
大阪聖心こころセラピーでは、あなたの苦しみに寄り添い、パニック障害に精通したカウンセラーが、あなたのペースに合わせて改善・克服を目指すお手伝いをします。安心してお気軽にご相談ください。
◆関連記事 親子問題・親子関係 大人の愛着障害 不安症 全般性不安症
参考文献・参考資料
- 熊野宏昭(2014) パニック障害の認知行動療法 不安症研究 第6巻 第1号
- 関陽一(執筆・編集),清水栄司(監修)(2016)『パニック障害(パニック症) の認知行動療法マニュアル(治療者用)』 厚生労働省
- アメリカ精神医学会(著),日本精神神経学会(監訳)(2023)『DSM-5-TR 精神 疾患の診断・統計マニュアル テキスト改訂版』 医学書院


