薬物依存症カウンセリング

薬物依存症の専門カウンセリング|臨床心理士・公認心理師が解決に導きます
薬物依存症専門カウンセリング
臨床心理士・公認心理師
が解決に導きます
薬物依存症とは、抗不安薬や睡眠薬、抗うつ薬などの向精神薬を、自分の意思ではコントロールできずに使用を続けてしまい、日常生活や健康に支障をきたす状態を指します。薬を飲み続けないと不安になる状態も薬物依存症に含まれます。依存症からの回復には、薬だけに頼らず、心理的サポートや生活習慣の調整を組み合わせて取り組むことが大切です。
関連性のあるテーマ
当カウンセリングは、診断や治療といった医療行為を行うものではありません。臨床心理士や公認心理師といった専門資格を持つカウンセラーが、認知行動療法などの心理療法を用い、様々な問題で悩む方々に対し、ご自身の心と向き合い、不安のメカニズムを理解し、日常生活をより穏やかに過ごすための専門的なサポートを提供します。
本記事は、アメリカ精神医学会(APA)が発行する『DSM-5-TR:精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版 改訂版』に基づき、臨床心理士が専門的知見のもとに執筆・監修しています。本内容は診断や医療行為を目的としたものではなく、カウンセリングにおけ
心の奥に潜む「薬物依存症・くすり依存症」の正体

「薬への囚われ」
「薬物依存症」と聞くと、多くの人が覚せい剤やヘロインといった違法な薬物を思い浮かべるかもしれません。しかし、私たちの身近な生活の中に、誰もが陥る可能性のあるもう一つの「依存症」が存在します。それが、病院で処方される睡眠薬や抗不安薬、抗うつ剤といった向精神薬による「くすりへの依存症」です。
これらの薬は、不眠や不安といった辛い症状を和らげるために、医師から適切に処方されるものです。しかし、知らず知らずのうちに薬なしではいられない状態に陥り、生活の中心が薬になってしまうことがあります。
薬物依存の背景には、幼少期に抱えた孤独や不安が大きく影響している場合があります。詳しくはアダルトチルドレンをご覧ください。
また、薬物に頼る行動は、“安心感の欠如”を埋めようとする愛着の問題と深くかかわっていることもあります。大人の愛着障害をご一読いただくことで、薬物依存症への理解が深まる一助となります。
薬物依存症は、個人の意思が弱いからなるものではありません。脳の働きや心の状態が深く関わる、医学的・心理的な問題です。この記事では、薬物依存症・くすり依存症のメカニズムや、そこから抜け出すためのヒントを、専門的な知見を交えながらわかりやすくお伝えします。
医師から処方された薬でも依存する理由

「薬に頼らざるを得ない日常」
「医師が出してくれた薬だから大丈夫」と考えている方も多いでしょう。確かに、精神科や心療内科で処方される向精神薬は、不眠症やうつ病、パニック障害といった病気の治療に欠かせないものです。しかし、特定の向精神薬には、依存症を引き起こしやすい性質があることを理解しておく必要があります。
特に、ベンゾジアゼピン系と呼ばれる抗不安薬や睡眠薬は、高い即効性がある一方で、依存性が高いことが知られています。これらの薬は、脳内のGABAという神経伝達物質の働きを強め、神経の興奮を抑えることで、不安を和らげたり眠気を引き起こしたりします。薬を服用すると、辛かった症状が一時的に軽減され、安心感や多幸感を得られます。
脳は、この「楽になる」という感覚を強く記憶します。すると、薬が切れて再び不安になったり眠れなくなったりしたときに、「またあの楽な状態になりたい」と強く求めるようになります。これが、「精神依存」の始まりです。
さらに、薬を繰り返し使用するうちに、同じ量では同じ効果が得られなくなる「耐性」が形成されます。効果を得るために薬の量が増えていき、薬なしでは身体が正常な状態を保てなくなる「身体依存」へと進行します。
依存症は、意志の力だけで克服できるものではありません。薬を求める気持ちが強まり、自分でコントロールできなくなる状態は、脳の機能が変化してしまっていることの表れなのです。
あなたの生活は薬が中心になっていませんか?
自分の状態を客観的に見つめ直すことは、薬物依存症・くすり依存症克服の第一歩です。以下のチェックリストを参考に、あなたの状況を自己診断してみましょう。
- 夜眠るためには必ず薬が必要だと感じる
- 薬が手元にないと強い不安感に襲われる
- 薬を手に入れることや服用することが常に頭から離れない
- 薬のせいで、仕事や学業、人間関係に支障が出ている
- 複数の医療機関を受診し、たくさんの種類の薬をもらっている
- 医師に症状を大げさに伝えて、薬の量を増やしてもらおうとしたことがある
- 薬を服用すると一時的に不安が和らぎ、人と会うのが楽に感じる
- 副作用が出ているのに、薬をやめることができない
- もしもの備えとして、必要以上に薬をため込んでいる
- 以前より薬が効かなくなり、服用量が増えている
一つでも当てはまる項目があるなら、薬物依存症・くすり依存症の可能性があるかもしれません。安易に自己判断せず、専門家に相談することが大切です。
薬に頼ることで失う心の自由
睡眠薬への依存
「眠れない夜」は、心身の不調を招き、大きなストレスとなります。不眠症の相談に行けば、多くの場合は睡眠薬が処方されるでしょう。服用すれば、久々に訪れる深い眠りに安堵し、薬の効果を実感します。しかし、この安堵感が依存症のきっかけとなることがあります。
「薬を飲まなければ眠れない」という強迫観念が生まれると、次第に薬なしでは眠れない状態になります。薬に慣れて効果が薄れてくると、自己判断で服用量を増やしてしまうケースも少なくありません。
最終的には、体が薬なしではいられない状態になり、薬が生活の中心となってしまいます。本来、睡眠薬は一時的な使用を目的としていますが、長期にわたって使用することで、睡眠を司る脳の機能が薬に頼りきりになり、自力での睡眠が困難になります。
抗不安薬への依存
現代社会はストレスに満ちています。不安やストレスを和らげるために、抗不安薬を服用する人もいるでしょう。薬を飲めば、張り詰めていた心がゆるみ、一時的な安心感が得られます。しかし、この「安心感」こそが依存症の落とし穴となります。
「今日は薬を飲んだから大丈夫」と安心できる一方で、服用していない日は「また嫌な気分になったらどうしよう」と、以前よりも強い不安に襲われることがあります。
このように、薬がなければ安心できない状態は、心が薬に依存している証拠です。本来の自分らしい感情の起伏を薬が抑え込んでしまい、自分の感情をコントロールする力が失われてしまうのです。
薬を絶つことで現れる心身の苦痛
薬物依存症の恐ろしさは、単に「薬を止められない」という点だけではありません。薬の使用を中断したり、量を減らしたりした際に現れる「離脱症状」こそが、依存症から抜け出すことを困難にしている最大の要因です。
離脱症状は、使用していた薬の種類や服用量、期間によって様々ですが、一般的に以下のような症状が現れます。
- 精神症状:強い不安感、イライラ、焦燥感、うつ状態、不眠、幻聴、幻覚、妄想
- 身体症状:手の震え、発汗、吐き気、頭痛、筋肉の痙攣、けいれん発作、不整脈
これらの症状は、薬によって調整されていた脳や神経が、急激な薬の減少に対応できず、バランスを崩すことで起こります。あまりに苦しいため、多くの人は離脱症状から逃れるために、再び薬に手を伸ばしてしまいます。この繰り返しが、依存症の悪循環を強固なものにしてしまうのです。
薬に頼らざるを得ない心の背景
「どうして私は薬に頼ってしまうのだろう」と自問したことはありませんか?薬物依存症は、単にその人の性格や意志の問題ではありません。その背景には、幼少期の家庭環境や社会生活における「生きづらさ」が深く関わっていることが多いのです。
- 幼少期のトラウマ:親からの愛情不足、家庭内の不和、虐待やDVといった経験は、心に深い傷を残します。慢性的な不安や孤独感を抱え、他人を信じることが難しくなり、社会生活に馴染めないといった生きづらさにつながることがあります。
- 自己肯定感の低さ:物事を深く考えすぎる、完璧主義、他人と比べて自分を責めるなど、自己否定的な思考パターンを持っている人は、心のバランスを崩しやすくなります。
- ストレスへの対処法がない:現実の辛い出来事や感情から逃れたいと強く願うとき、薬は一時的な避難場所となります。しかし、それは根本的な解決にはなりません。
薬物は、寂しさや心の痛み、不安を一時的に忘れさせてくれる「手段」となってしまいます。しかし、これはあくまでも対処療法です。薬でごまかしている限り、根本的な問題は解決されず、いつまでも薬に頼り続けることになります。


薬物依存症が招く健康被害

「身体への負担」
処方薬の長期服用は、心身に様々な影響を及ぼします。
- 身体への負担:肝臓や腎臓といった臓器に大きな負担をかけ、機能障害を引き起こす可能性があります。また、便秘や体重増加、ふらつきといった副作用も現れることがあります。
- 認知機能の低下:長期にわたる向精神薬の服用は、思考力や記憶力、集中力の低下を招くことがあります。特に高齢者の場合、認知症のような症状を引き起こすケースも報告されています。
- 精神的な影響:薬で感情をコントロールし続けることで、感情の起伏が鈍くなり、無気力や意欲の低下を招くことがあります。
医師の中には、患者さんの訴えを聞いて、とにかく薬を出すことを優先する人も少なくありません。しかし、それは症状を一時的に抑えているだけで、根本的な解決にはつながっていないのです。
薬に頼らない生き方へ
気持ちのコントロールで未来を切り拓く
統合失調症や双極性障害など、薬物治療が不可欠な病気もあります。しかし、うつ状態や不安感が主な症状である場合は、薬物だけに頼らず、「自分の考え方の癖」を見つめ直すことが、根本的な解決への鍵となります。
「不安だから薬を飲む」というパターンから抜け出し、不安の根底にある思考や感情のパターンを変えていくことが、依存症からの脱却につながります。
薬物依存症克服への道のり

「専門的なサポート」
1. 専門家への相談
まず、一人で悩まずに、専門家に相談しましょう。薬物依存症は、個人の努力だけで克服するのは非常に困難です。大阪聖心こころセラピーでは、薬に頼らずに心の状態を改善するための様々なアプローチを提供しています。
2. 認知行動療法の導入
自分の考え方の癖や行動パターンを見つめ直し、それを変えていく認知行動療法は、薬物依存症克服に非常に有効です。不安やネガティブな感情が湧き上がったときに、薬に頼るのではなく、「どうしてそう感じるのか」「どうすればこの状況を乗り越えられるのか」を客観的に見つめ、建設的な思考パターンを身につけます。
3. 環境の調整と自己受容
依存症の背景には、過酷な環境や人間関係の問題が潜んでいることがあります。もし、現在の環境がストレスの原因となっているのであれば、その環境から離れる、あるいは、その環境を「仕方ないこと」として受け止める練習をすることも重要です。
また、「自分が悪い」と自分を責めすぎないことも大切です。「自分は自分だ」という考え方を持ち、自己肯定感を高めていくことで、薬に頼らずとも心の平穏を保つことができるようになります。
4. 薬は「補助」と考える
薬は、あくまでも症状を緩和するための補助的なものです。薬に頼りきりになるのではなく、自分の力で心の状態をコントロールできるようになることが最終的な目標です。
あなたの「変わりたい」を全力で応援します
大阪聖心こころセラピーには、「薬を飲んでいるのに一向に良くならない」「薬の副作用で頭がぼんやりしてしまう」といった悩みを持つ方が多く来られます。
私たちは、単に症状を抑えるだけの対処療法ではなく、あなたの心の根本的な問題に向き合い、「物事の捉え方、考え方」を修正していくことに主眼を置いています。
カウンセリング、コーチング、そして認知行動療法やヒプノセラピーといった専門的な手法を組み合わせることで、薬に頼らない生き方を実現するためのプログラムを提供しています。
カウンセリング・コーチング
まずは、あなたの心に耳を傾け、抱えている問題や悩みを丁寧に掘り下げていきます。その上で、目標設定や行動計画を立て、薬に頼らない生活を送るための具体的なアドバイスを行います。
認知行動療法
不安やネガティブな感情を生み出す思考パターンを特定し、より建設的な思考パターンに書き換えていく練習をします。
ヒプノセラピー(催眠療法)
心の奥底にある無意識の部分に働きかけ、トラウマやネガティブな感情の根源を癒すことで、薬に頼る必要のない心身の状態を作り上げていきます。
違法薬物依存症への対応について
覚せい剤や大麻などの違法薬物への依存症は、合法的な処方薬への依存症とは異なる深刻な問題です。身体的な害だけでなく、犯罪や人間関係の破綻といった悲劇を招く可能性が非常に高いからです。
当セラピーは、合法的な処方薬による依存症を専門としており、違法薬物関連の断薬や後遺症に関するご相談は、専門外のためお受けすることができません。 違法薬物依存症でお悩みの方は、精神保健福祉センターや専門の依存治療施設にご相談されることを強くお勧めします。
薬を手放し、自分らしい人生を取り戻すために
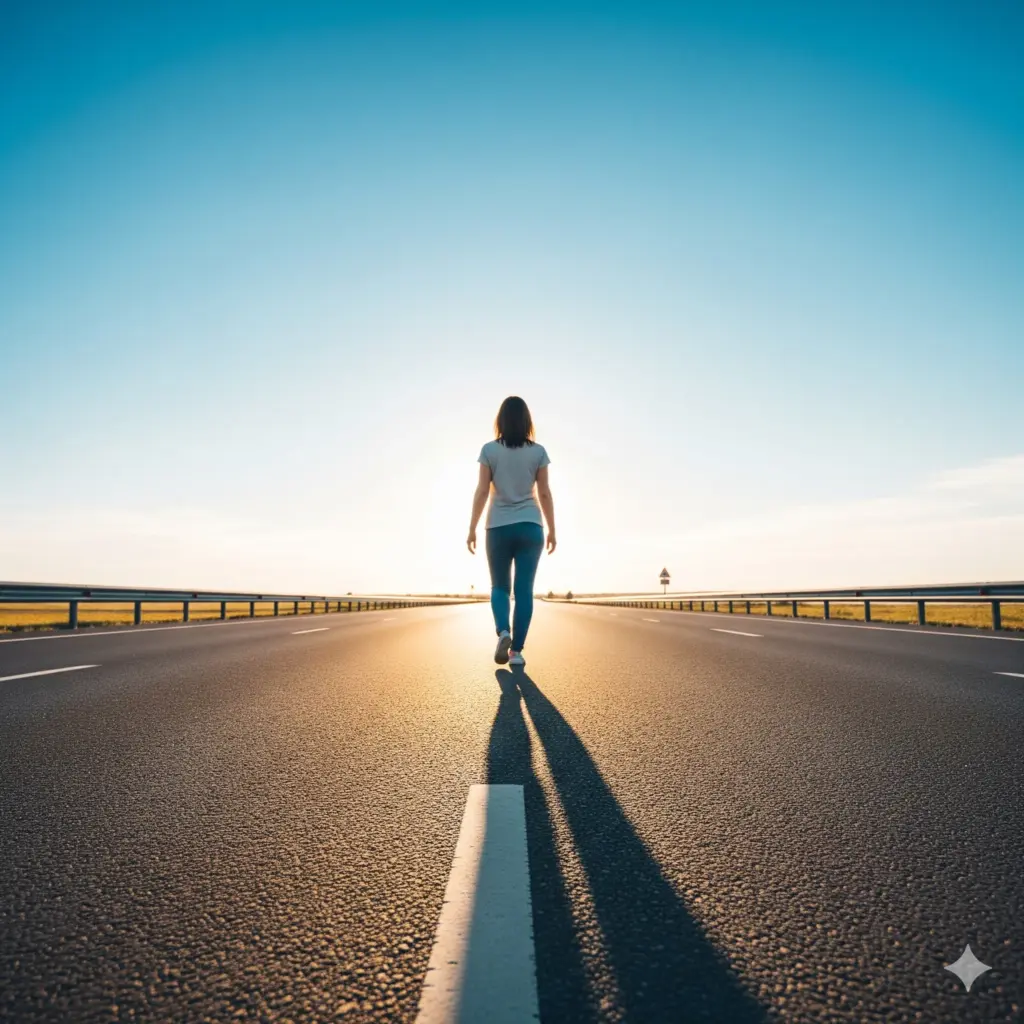
「回復への希望」
薬物依存症は、決して恥ずかしいことではありません。誰もが陥る可能性のある心の病気です。大切なのは、一人で抱え込まずに、専門家の力を借りて、一歩踏み出すことです。
薬は、あなたの心を一時的に助けてくれますが、根本的な解決は、あなたの心の中にあります。大阪聖心こころセラピーは、あなたの心の奥に潜む「生きづらさ」の根源と向き合い、薬に頼らない、あなたらしい人生を取り戻すための道筋を一緒に探していきます。
「薬に頼りたくない」「自分を変えたい」と思ったら、いつでもご相談ください。私たちは、あなたが穏やかで楽しい毎日を送れるよう、全力でサポートします。
◆関連記事 アダルトチルドレン 大人の愛着障害 依存症 ギャンブル依存症
参考文献・参考資料
- 渡辺登(2007) 『依存症のすべてがわかる本』 講談社
- 松本俊彦(2016)『薬物依存臨床の焦点』 金剛出版


