大阪のネット・スマホ依存|心理相談 画面の向こうではなく今ここにある現実
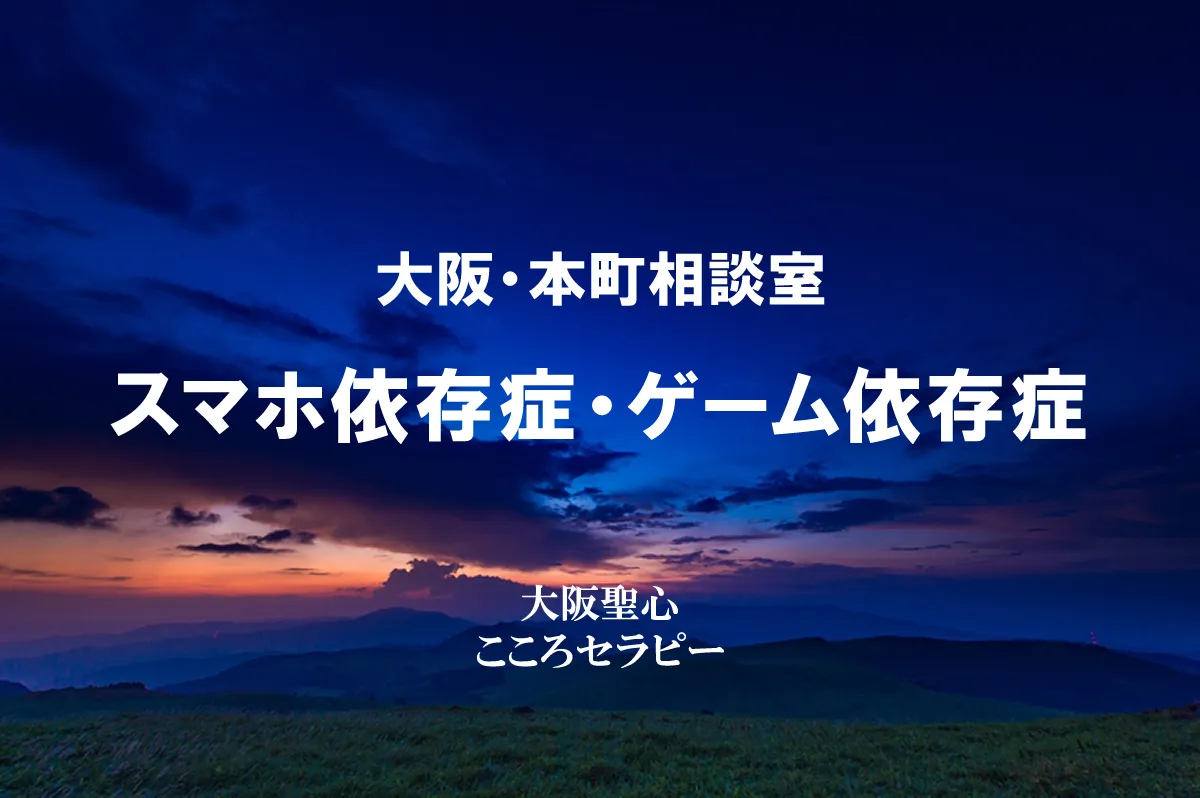
スマホ依存症・ゲーム依存症の専門カウンセリング
臨床心理士・公認心理師が解決に導きます
スマホ依存症・ゲーム依存症
専門カウンセリング
臨床心理士・公認心理師
が解決に導きます
スマホ・ゲーム依存症は、家族との会話不足、昼夜逆転、成績不振、不登校、ひきこもりなど、社会生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。その背景には、ストレスや孤独感、自己肯定感の低下、対人関係の不安、家庭環境、さらにはデジタル機器が身近にある社会的要因など、複数の要素が複雑に関わっています。一つの原因に限定されるものではなく、包括的に理解することが重要です。
関連性のあるスレッド
当カウンセリングは、診断や治療といった医療行為を行うものではありません。臨床心理士や公認心理師といった専門資格を持つカウンセラーが、認知行動療法などの心理療法を用い、様々な問題で悩む方々に対し、ご自身の心と向き合い、不安のメカニズムを理解し、日常生活をより穏やかに過ごすための専門的なサポートを提供します。
本記事は、アメリカ精神医学会(APA)が発行する『DSM-5-TR:精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版 改訂版』に基づき、臨床心理士が専門的知見のもとに執筆・監修しています。本内容は診断や医療行為を目的としたものではなく、カウンセリングにおける理解を深めるための情報提供としてご利用ください。
そのスマホ、本当に必要ですか?デジタルに蝕まれる現代人の心と脳

「孤独と社会からの断絶」
現代社会において、スマートフォンやインターネット、ゲームは私たちの生活に不可欠な存在となりました。しかし、その利便性の裏側で、デジタルデバイスに過度に依存し、日常生活に支障をきたす人が急増しています。
「朝起きたらまずスマホをチェック」「食事中もスマホが手放せない」「ゲームをしていないと落ち着かない」—もし、これらがあなたの日常に当てはまるなら、それは単なる習慣ではなく、デジタル依存症の始まりかもしれません。
大阪聖心こころセラピーでは、このようなデジタル依存症に悩む多くの方々が相談に訪れます。その多くは、自分自身に問題があると感じていながらも、どうすればいいか分からず、あるいは、家族や恋人に連れられてくるケースが少なくありません。なぜなら、デジタル依存症の特徴の一つに、本人が依存している自覚がないという点があるからです。
この依存症は、単に時間を浪費するだけでなく、家族関係の悪化、学業や仕事の停滞、そして心身の健康を損なうなど、人生全体に深刻な影響を及ぼします。この記事では、デジタル依存症の様々な側面を掘り下げ、その克服に向けた具体的な道筋を探っていきます。
スマホやゲームに依存してしまう背景には、幼少期の孤独感や満たされなさが関係することがあります。詳しくはアダルトチルドレンをご覧ください。
また、スマホへの没頭は、“安心感を求める行動”として、愛着不安と関連する場合もあります。そのような場合には、大人の愛着障害をご一読ください。
あなたはどのタイプ?デジタル依存症の多様な顔
デジタル依存症は、ひとつの症状に限定されるものではありません。その依存対象や行動パターンによって、様々なタイプに分けられます。ご自身の行動を振り返り、どのタイプに当てはまるか考えてみましょう。
ゲーム依存症:現実逃避のバーチャルワールド
オンラインゲームに没頭し、学業や仕事、家庭生活といった現実の役割を後回しにしてしまう状態です。日夜を問わずゲームにログインし、クリアするまでやめられない。ゲームをすることが生活の最優先事項になっていませんか?
特に若い世代に多く見られ、ゲームによる脳の興奮状態が続くと、寝つきが悪くなり、不眠から昼夜逆転の生活に陥ることがあります。この状態が続けば、不登校や引きこもり、そしてニートへと進行する危険性をはらんでいます。
ネットサーフィン依存症:目的のない情報探求
特に目的もなく、長時間にわたってウェブサイトをさまよい続けるのがこのタイプです。「暇だから」「他にやることがないから」と、人生を積極的に楽しめていないと感じている人に多く見られます。心の奥底にある「何かいいことないかな?」という枯渇感が、際限のないネットサーフィンを誘発します。
これは、心の問題と深く結びついています。ただ画面をじっと見つめ、何時間も座り込んでいる姿は、周りの人から見れば不気味に映るかもしれません。
メール・SNS依存症:常に誰かと繋がっていたいという渇望
メールやSNSでのやり取りに多くの時間を費やし、返信が来ないとソワソワしたり、イライラしたり、落ち着きがなくなってしまう状態です。目の前のことに集中できなくなり、学業や仕事に影響が出ます。
「いつも誰かと繋がっていたい」という強い欲求がこの依存症の特徴です。また、LINEなどでの「既読スルー」が原因でいじめに発展するなど、特に中高生の間で深刻な問題となっています。大人でも、ママ友との関係など、人間関係のしがらみから抜け出せず、SNSに振り回されるケースは少なくありません。
スマホ依存症:手放せない小型デバイス
常にスマホを手にしている、あるいはスマホが手元にないと不安になるのがこのタイプです。人との会話の最中や、食事中、お風呂、トイレに至るまで、常にスマホをいじっていませんか?
移動中などにスマホを操作している人はたくさんいますが、そのうちの何割かは、常に手放せない状態に陥っています。枕元に電源を入れたままのスマホを置き、メールや電話を待機している状態は、まるで非常事態に備えているかのようです。これでは心から安心して眠ることができず、不眠や無気力、身体的な倦怠感といった症状を引き起こす原因となります。
見過ごせないデジタル依存症の弊害とリスク

「家庭内の亀裂と無言の食卓」
デジタル依存症は、個人の生活だけでなく、家族や周囲の人々にも深刻な影響を及ぼします。
孤立と現実社会からの乖離
デジタル依存症が進行すると、自分の世界に閉じこもりがちになります。ネットに接続している時間が長くなるほど、家族と過ごす時間は減り、現実の友人関係も希薄になっていきます。結果的に、孤立感や孤独感から、うつ状態に陥るなど、精神面への影響も無視できません。
引きこもりやニートの多くは、この悪循環に陥り、現実社会との関わりを持つことが億劫になっていると言えるでしょう。
家庭内の亀裂と関係性の悪化
「ゲームを注意したら発狂する子ども」「ネットサーフィンを指摘したら不機嫌になる夫」—このような状況が続けば、家庭内の会話は減り、亀裂が生じます。食事中もスマホを手放さなかったり、家族との会話がないまま過ごしたりする時間が増え、最も大切な家族との関係がおろそかになります。
また、親がデジタルに依存していると、子どももそれを真似てしまい、家庭全体がデジタルに蝕まれる危険性があります。
身体的・精神的健康の悪化
不規則な生活や睡眠不足は、身体的な健康を損なう大きな要因となります。また、ネットを利用していない時に強い不安や欲求を感じ、ストレスが急激に高まることもあります。これは「それがないと生きていけない」という感覚に陥るほど深刻な状態です。
危険な兆候を見逃さないで!依存症は自然には治らない

「身体的・精神的な疲弊」
「放っておけばそのうち飽きるだろう」—そう考えるのは大きな間違いです。デジタル依存症は、本人が依存症している自覚がないことが多く、自然に軽快するよりも長期化・悪化するケースが多いため、注意が必要です。
家族や周囲が注意しても、「何がいけないの?」「みんなもやっている」と自分を正当化し、防御線を張ってしまいます。この頑なな姿勢が、問題をさらに複雑にしているのです。
特に、以下のような兆候が見られる場合は、専門家への相談を検討すべきです。
- 食事や睡眠を削ってまで、ネットやゲームに没頭する
- 学業や仕事、家事などのやるべきことが手につかない
- ネットをしていないと、イライラしたり、落ち着かなくなる
- 家族や友人との会話が減り、部屋に閉じこもりがちになる
- 注意されると、激しく反発したり、嘘をついたりする
依存症の背景にある心理と心の枯渇

「バーチャルと現実の境界線」
なぜ、私たちはこれほどまでにデジタルに依存してしまうのでしょうか。そこには、現代人が抱える様々な心理的要因が隠されています。
現実世界から逃れたい心理
ネット依存症の背景には、「現実の世界を直視したくない」という心理が隠れています。現実生活や仕事、人間関係がうまくいかない時ほど、バーチャルな世界への依存が高まります。ネットを通して人と交流したり、ゲームに没頭したりすることで、現実の寂しさや不安を紛らわすことができるからです。
「他の人を信頼できない」「傷つけられるのが怖い」という思いから、安心感のある自分だけのバーチャル世界に浸ってしまうのです。メール依存症も、「メールでなら自分を表現できる」という、直接的なコミュニケーションを恐れている心理が根底にあると考えられます。
成長を阻害するバーチャルな世界
本来、人間は外部とのコミュニケーションを通じて、傷ついたり、癒されたりしながら心を成長させていきます。しかし、バーチャルな世界に閉じこもり続けていると、現実での成長機会を失ってしまいます。いつまでたっても寂しさや不安を満たせないまま、自分の世界に閉じこもる人生を送ることになるでしょう。
ネットやゲームは、新しい刺激や達成感を瞬時に得られるため、ドーパミンという快楽物質が分泌されます。しかし、それは一時的なものです。現実世界での努力や挑戦から得られる真の達成感や喜びとは異なり、心の奥底にある「心の枯渇感」は満たされません。
子どもたちのデジタル依存症:親が知っておくべきこと
デジタル依存症は、大人だけの問題ではありません。現代では、小学生にも見られるほど深刻な問題になっています。特にゲームに熱中しすぎるケースがほとんどで、いつでもどこでもゲームができてしまうため、親が気づきにくいのが現状です。
健全な成長を阻害する危険性
ゲームや動画にはまり、友達と外で遊んだり、習い事に行ったりする時間がなくなっていませんか?スマホやタブレットは、子どもを静かにさせるための便利なツールとして与えられがちですが、それが引きこもりの第一歩となることもあります。
家庭に父親が不在がちだったり、両親ともに忙しく子どもと向き合う時間がない場合など、家庭環境が影響しているケースも少なくありません。子どもが退屈を紛らわすために、ゲームや動画に楽しみを見出してしまうことがあります。
孤独な夫のデジタル依存症:家族のサインを見逃さないで
スマホやパソコンは、多くの情報を手軽に得られるため、趣味や副業、出会い系サイトなどにはまり、何時間も画面に向かう夫も増えています。食事中もスマホを手放さず、家族との会話がない、といった状態は、立派なデジタル依存症の兆候です。
家族との絆を再構築するために
最初は暇つぶしだったものが、いつの間にか一日中パソコンの前にいる、といった状態になっていませんか?家族を大切に思うのであれば、デジタルに費やしている時間を少し減らし、家族との交流時間を増やす努力が必要です。
父親がデジタルに依存している姿を子どもが見れば、それを真似てしまう可能性も高まります。最も大切な家族との絆に亀裂が入る前に、まずあなた自身が行動を起こすことが重要です。
デジタル依存症の克服へ:大阪聖心こころセラピーのサポート
「分かってはいるけれど、自分一人ではどうにもできない」—そう感じているなら、まずは専門家の力を借りてみませんか?
デジタル依存症を克服するには、まず「なんとかしたい」と本人が決心することが第一歩です。そして、「今の生活を続けると未来はどうなるのか」「自分はどれくらいの時間をネットに費やしているのか」を正確に把握し、現状を自覚することが大切です。
心の本質に目を向けるセラピー
大阪聖心こころセラピーでは、あなた自身が心の奥底にある「なぜ依存してしまうのか」という本質的な問題に目を向けられるよう、専門的なサポートを提供しています。
認知行動療法や潜在意識療法を通じて、あなた自身の心をコントロールできるよう誘導します。そして、バーチャルな世界やネットへの依存傾向を改善し、現実の社会の中で、人との温かい交流や信頼関係を再び築いていけるようにお手伝いします。
あなたの悩みに寄り添う専門家
私たちは、デジタル依存症に陥る心の状態を改善し、適度な使用に留められるよう、心をコントロールしていくお手伝いをしています。孤独や不安を埋めるためにデジタルに逃げているなら、その心の状態を改善し、現実世界で充実した人生を送るためのサポートを一緒に考えていきましょう。
依存症は、放置すればするほど進行します。そして、それはあなた自身の人生だけでなく、あなたを大切に思っている家族や友人たちの人生にも大きな影響を及ぼします。
一歩踏み出し、専門家の扉を叩くことは、未来の自分自身を救うための第一歩です。大阪聖心こころセラピーでは、あなたの悩みに真摯に向き合い、新しい人生を歩み出すためのお手伝いをいたします。
よくある質問と答え
- 1. スマホ依存症は病気ですか?
-
スマホ依存症は、現在、精神疾患の正式な診断基準には含まれていませんが、ゲーム依存症と同様に、日常生活に深刻な支障をきたす場合には、依存症として治療の対象となります。
- 2. 家族が依存しているかもしれないのですが、どうすればいいですか?
-
まずは、依存している本人を責めるのではなく、心配している気持ちを伝え、一緒に専門家へ相談に行くことを提案してみましょう。本人が自覚していないことが多いので、いきなり「病気だ」と決めつけるのではなく、まずは「あなたのことが心配だ」という姿勢で接することが大切です。
- 3. セラピーではどのようなことをするのですか?
-
主に、デジタルに依存してしまう根本的な原因を探るためのカウンセリングを行います。そして、認知行動療法や潜在意識療法などを用いて、依存行動をコントロールするスキルを身につけ、心の状態を改善していくことを目指します。
- 4. 子どもがゲームばかりしていますが、どうすればいいですか?
-
まずは、ルールを一緒に決めることから始めてみましょう。使用時間を制限したり、宿題や家事を終えてからにしたりするなど、子どもと話し合ってルールを定めます。そして、ゲーム以外の楽しいこと(外遊びやスポーツ、習い事など)を見つけられるよう、積極的に働きかけることも重要です。
デジタルデトックスを始めよう:日常生活でできる小さなステップ

「依存症からの解放と新しい一歩」
専門家の助けを借りる前に、まずは自分自身でできることから始めてみましょう。デジタルデトックスは、デジタル依存症から抜け出すための有効な手段です。
- スマホを置く時間を決める: 食事中や寝る前の1時間は、スマホを別の部屋に置くなど、物理的に離れる時間を作りましょう。
- 通知をオフにする: SNSやメールの通知をオフにすることで、無意識にスマホを触ってしまう衝動を抑えられます。
- 趣味や運動に時間を費やす: ネット以外の趣味(読書、料理、絵を描くなど)や運動を見つけ、現実世界での楽しみを増やしましょう。
- 「何もしない時間」を作る: 意識的にボーっとする時間や、自分自身と向き合う時間を作りましょう。常に情報に触れていないと不安になる状態から抜け出すことが目標です。
- 家族や友人と直接会って話す: 電話やメールではなく、直接顔を合わせて会話することで、温かい人間関係を再構築できます。
これらの小さな積み重ねが、デジタル依存症から抜け出し、現実世界で充実した人生を送るための第一歩となります。
しかし、もし「自分一人では難しい」「何から始めていいか分からない」と感じたら、いつでも大阪聖心こころセラピーにご相談ください。あなたの心の声に耳を傾け、より良い未来を築くためのサポートを全力でさせていただきます。
◆関連記事 アダルトチルドレン 大人の愛着障害 性格改善 依存症
参考文献・参考資料
- 信田さよ子(2015年)『アディクション臨床入門:家族支援は終わらない』 金剛出版
- ダニエル・キング,ポール・デルファブロ(著),樋口進(監訳),成田啓行(訳)(2020) 『ゲーム障害』 福村出版


