統合失調症カウンセリング
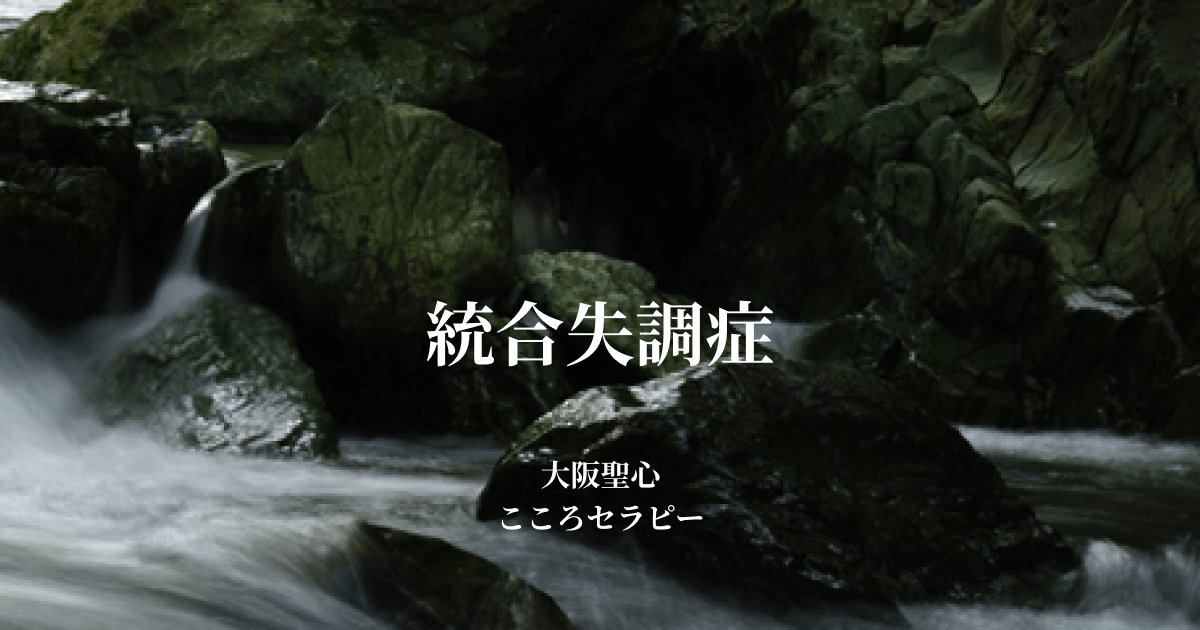
統合失調症の専門カウンセリング|臨床心理士・公認心理師が解決に導きます
統合失調症専門カウンセリング
臨床心理士・公認心理師
が解決に導きます
統合失調症は、かつて「精神分裂病」と呼ばれていましたが、現在は「統合失調症」という名称で広く使われています。症状は多岐にわたり、代表的なものに「幻聴」「幻覚」「妄想」などがあります。これらの症状は当事者にとって非常に現実的に感じられるため、本人には「病気の症状」と自覚しにくいこともあります。
関連性のあるテーマ
当カウンセリングは、診断や治療といった医療行為を行うものではありません。臨床心理士や公認心理師といった専門資格を持つカウンセラーが、認知行動療法などの心理療法を用い、様々な問題で悩む方々に対し、ご自身の心と向き合い、不安のメカニズムを理解し、日常生活をより穏やかに過ごすための専門的なサポートを提供します。
本記事は、アメリカ精神医学会(APA)が発行する『DSM-5-TR:精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版 改訂版』に基づき、臨床心理士が専門的知見のもとに執筆・監修しています。本内容は診断や医療行為を目的としたものではなく、カウンセリングにおける理解を深めるための情報提供としてご利用ください。
統合失調症ってどんな病気?

「統合失調症の世界」
統合失調症は、約100人に1人の割合で発症するといわれる、決して珍しくない精神疾患です。ストレスなどが引き金となり、誰にでも起こりうる病気です。この病気の最も大きな特徴は、現実と非現実の区別がつきにくくなることです。そのため、幻覚や妄想といった独特な症状が現れます。
例えば、普通の人には聞こえない声が聞こえたり(幻聴)、ありもしないことを現実だと信じ込んだり(妄想)します。しかし、当事者はその幻覚や妄想を「特別な能力だ」と感じたり、「これは現実だ」と強く信じているため、病気だと自覚することが難しい場合が多いのです。
もし、身近な人が統合失調症かもしれないと感じても、焦る必要はありません。適切な治療とサポートがあれば、症状は改善し、普通の生活を送れるようになるケースも多いです。早期に精神科や心療内科、カウンセリングなどの専門機関を訪れることが、回復への第一歩となります。
幼少期の親子関係が緊張に満ちていた場合、心の安定に影響を与えることがあります。関連内容は親子問題・親子関係をご覧ください。
また、人への不信感や孤独感が強まる背景には、愛着の不安定さが関係していることもあります。詳しくは大人の愛着障害をご一読ください。
統合失調症の症状を深く理解する

「断片化された風景」
統合失調症の症状は、大きく「陽性症状」「陰性症状」「その他の症状」の3つに分けられます。それぞれが異なる特徴を持ち、病気の進行度合いによって現れ方が変わってきます。
陽性症状:世界が歪む急性期
統合失調症の症状が最も激しく現れる時期を「急性期」と呼びます。この時期は、心が非常に不安定になり、些細なことにも過敏に反応してしまいます。
主な陽性症状は以下の通りです。
- 妄想:現実にはありえないことを強く信じ込んでしまいます。
- 被害妄想:誰かに嫌がらせを受けている、自分は嫌われていると思い込む。
- 関係妄想:周囲で起きるすべての出来事が自分に関係していると思い込む。
- 監視妄想:常に誰かに監視されていると感じる。
- 追跡妄想:誰かに追われているように感じる。
- 誇大妄想:自分は特別な人間だ、偉大だと思い込む。
- 恋愛妄想:見ず知らずの人から愛されていると信じ込む。
- 毒薬妄想:食べ物や飲み物に毒が盛られていると疑う。
- 世界崩壊妄想:世界がもうすぐ終わる、崩壊すると信じ込む。
これらの妄想は一つだけでなく、複数組み合わさって現れることが多く、当事者は極度の恐怖や不安に苛まれています。
- 幻覚:五感を通じて、実際には存在しないものを知覚します。
- 幻聴:誰もいないのに声が聞こえる。自分を罵倒する声、命令する声などが聞こえ続ける。
- 幻視:存在しないものが見える。
- 体感幻覚:体に何も触れていないのに、触られているように感じる。
幻覚を体験している当事者は、それが現実だと信じているため、「霊が見える」「神のお告げが聞こえる」といった形で解釈することが多いです。
- 自我意識の障害:自分の思考と他人の思考の区別がつきにくくなります。
- 思考奪取:自分の考えが他人に盗まれていると感じる。
- 思考伝播:自分の考えが周囲の人に筒抜けになっていると感じる。
- 思考察知:他人の考えが自分に伝わってきていると感じる。
このような自我意識の障害は、当事者を極度の不安に陥れ、社会生活を困難にさせます。
陰性症状:エネルギーが枯渇する消耗期
急性期を経て、症状が少し落ち着いてきた時期を「消耗期」と呼びます。この時期には、心身のエネルギーが大きく失われ、意欲や感情が低下する「陰性症状」が現れます。陽性症状が「プラス」の症状だとすれば、陰性症状は「マイナス」の症状だと言えます。
主な陰性症状は以下の通りです。
- 意欲の低下:何もする気が起きず、一日中寝て過ごしたり、食事や入浴といった基本的な生活習慣すら億劫になる。
- 感情の平板化:喜怒哀楽の感情が乏しくなり、表情や声のトーンが単調になる。
- 集中力の低下:物事に集中できず、すぐに疲れてしまう。
- 引きこもり:人と会うのを避け、自宅に閉じこもりがちになる。
これらの陰性症状は、一見すると「怠けている」「やる気がない」と見られがちですが、当事者はエネルギーが枯渇して動けない状態にあります。
その他の症状:いつ現れるかわからない症状
陽性症状や陰性症状とは関係なく、病気のどの時期にも現れる可能性がある症状もあります。
支離滅裂な言動:考えがまとまらず、話が飛んだり、意味不明な言葉を羅列したりする。
不安感、焦燥感、緊張感:常に漠然とした不安や焦りを感じ、落ち着かない。
パニック発作:突然の強い不安や恐怖に襲われ、動悸や息苦しさを感じる。
統合失調症の原因と背景
統合失調症の明確な原因はまだ特定されていませんが、複数の要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。
脳の機能異常と神経伝達物質
最も有力な仮説の一つが、脳内の神経伝達物質、特にドーパミンのバランスが崩れることで発症するというものです。脳内の一部でドーパミンが過剰に放出されることが、幻覚や妄想といった陽性症状を引き起こすと考えられています。
また、グルタミン酸という神経伝達物質の機能異常も関係しているという仮説もあります。これらの仮説に基づいた研究が進められており、現在の治療法にも生かされています。
発達段階での脳の障害
脳が十分に成熟する段階で何らかの問題が生じ、統合失調症が発症するという仮説もあります。脳の構造に変化が見られるケースも存在し、今後の研究が期待されています。
遺伝的要素と環境要因
統合失調症には遺伝的な要素も関係しているとされています。しかし、遺伝子だけで発症するわけではなく、ストレスや幼少期のトラウマ、いじめといった環境要因が引き金となり、発症するケースが多いと考えられています。
特に、新しい環境(進学、就職など)での人間関係のトラブルやストレスが、発症のきっかけになることも少なくありません。
統合失調症の治療とカウンセリング

「サポートとつながり」
統合失調症の治療は、主に「薬物療法」と「心理社会的療法」を組み合わせて行います。
薬物療法:症状をコントロールする第一歩
統合失調症の治療において、薬物療法は非常に重要です。抗精神病薬を服用することで、脳内の神経伝達物質のバランスを整え、幻覚や妄想といった陽性症状を軽減させます。
薬を飲むことで症状が落ち着き、心に余裕が生まれてくると、心理的なケアが受けやすくなります。当事者自身が病気と向き合い、回復に向けて前向きな姿勢を築くための土台作りとなります。
心理社会的療法:社会生活を取り戻すためのケア
薬物療法で症状が落ち着いた後は、社会生活を送るためのリハビリテーションが重要になります。
- 心理教育:病気や症状、治療法について正しく理解することで、不安を減らし、病気と向き合う力をつけます。
- 認知行動療法:認知の歪みを修正し、より建設的な考え方や行動を身につけるための療法です。幻覚や妄想にどう対処すればいいか、具体的な方法を学びます。
- 社会生活技能訓練(SST):人とのコミュニケーションや生活に必要なスキルを練習し、社会に適応するための力を養います。
大阪聖心こころセラピーでは、これらの心理療法を組み合わせ、一人ひとりの状態に合わせたサポートを行っています。
統合失調症との向き合い方:家族と本人の連携
統合失調症は、本人だけでなく、家族や周囲の人にも大きな影響を与えます。適切なサポートを行うためには、病気について正しく理解し、冷静に対応することが大切です。
家族の役割と注意点
- 過保護・過干渉を避ける:良かれと思って何でも手伝ってしまうと、当事者の自立を妨げてしまうことがあります。当事者の能力を信じ、できることは自分でやってもらうように促しましょう。
- 病気を理解する:幻覚や妄想は、当事者にとっては現実です。「そんなことはない」と否定するのではなく、「そういう風に聞こえるんだね」と、まずは本人の苦しみに寄り添うことが重要です。
- 専門家と連携する:当事者の症状や治療について疑問があれば、医師やカウンセラーに相談しましょう。一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが、家族自身の負担を減らすことにもつながります。
当事者自身が病気と向き合う
病識がないことが多いため、治療へのモチベーションを保つのが難しい場合もあります。しかし、幻聴や幻覚に苦しむ当事者の多くは、「この苦しみから解放されたい」という思いを心のどこかで持っています。
まずは、薬を飲むことやカウンセリングに通うことで、その苦しみが少しでも軽くなることを実感してもらうことが大切です。小さな成功体験を積み重ねることで、「自分も良くなれる」という希望を持つことができるようになります。
合失調症と合併しやすい病気や症状

「専門性と安心感」
統合失調症は、他の精神疾患と症状が似ていたり、合併して発症したりすることがあります。
強迫性障害との関連
統合失調症の症状は、強迫性障害と似ている部分もあります。強迫性障害は、手洗いを何度も繰り返すなど、本人が「おかしい」とわかっているのにやめられない行動(強迫行為)が特徴です。
しかし、統合失調症の場合、本人はその行為が「おかしい」とは思わず、「誰かに毒を盛られないために必要な行動だ」と強く信じ込んでいる点が異なります。
青年期に発症する統合失調症
青年期に発症する統合失調症は、特に意欲低下や感情の平板化といった陰性症状が目立つことがあり、学業や日常生活に大きな影響を及ぼす場合があります。以前は「破瓜型」と呼ばれることもありました。
一見すると、思春期特有の「反抗期」や「引きこもり」と勘違いされがちですが、早期に適切な治療を受ければ、回復して社会生活を送れるようになるケースも多いです。
いじめが引き金となるケース
学校や職場でのいじめや強いストレスが、統合失調症の症状が表面化するきっかけになることもあります。ただし、いじめ自体が直接の原因というわけではなく、もともとの脆弱性や複数の要因が重なって発症するものと理解されています。
いじめを受けている間は、実際に自分を非難する声が聞こえていたとしても、いじめが終わった後も幻聴が続く場合があります。このような場合、現実と非現実の区別がつかなくなり、家から出られなくなってしまうこともあります。
まとめ:諦めないで、希望はあります

「穏やかな日常」
統合失調症は、非常に苦しい病気です。しかし、適切な治療と周りのサポートがあれば、症状は改善し、自分らしい生活を取り戻すことができます。
幻覚や幻聴は薬でコントロールできることが多く、カウンセリングを通じて、社会生活を営むためのスキルを身につけることも可能です。
もし、ご自身やご家族が統合失調症かもしれないと感じたら、まずは専門機関に相談してください。大阪聖心こころセラピーでは、統合失調症を抱える方とそのご家族に対し、豊富な経験と知識に基づいたカウンセリングとサポートを提供しています。
一人で悩まず、一緒に病気と向き合っていきましょう。あなたの心の声に、私たちが耳を傾けます。
◆関連記事 親子問題・親子関係 大人の愛着障害 不安症 PTSD
参考文献・参考資料
- 横田正夫・丹野義彦・石垣琢麿(編)(2003)『統合失調症の臨床心理学』 東京大学出版会
- 松井三枝(2017) 統合失調症の理解と心理学:神経心理学からの紹介 心理学評論 60巻 4号
- アメリカ精神医学会(著),日本精神神経学会(監訳)(2023)『DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル テキスト改訂版』 医学書院


