大阪の拒食症カウンセリング

拒食症の専門カウンセリング|臨床心理士・公認心理師が解決に導きます
拒食症専門カウンセリング
臨床心理士・公認心理師
が解決に導きます
拒食症(神経性やせ症)は、しばしば「痩せたい」という思いをきっかけに始まります。しかしその背景には、体型や容姿への強いこだわり、自己肯定感の低さ、完璧主義的な傾向、家族関係や社会的なプレッシャーなど、さまざまな要因が複雑に関与しています。単に「スリムへの憧れ」だけで説明できるものではなく、心理的・社会的・生物学的な要因が重なって発症すると考えられています。
関連性のあるテーマ
当カウンセリングは、診断や治療といった医療行為を行うものではありません。臨床心理士や公認心理師といった専門資格を持つカウンセラーが、認知行動療法などの心理療法を用い、様々な問題で悩む方々に対し、ご自身の心と向き合い、不安のメカニズムを理解し、日常生活をより穏やかに過ごすための専門的なサポートを提供します。
本記事は、アメリカ精神医学会(APA)が発行する『DSM-5-TR:精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版 改訂版』に基づき、臨床心理士が専門的知見のもとに執筆・監修しています。本内容は診断や医療行為を目的としたものではなく、カウンセリングにおける理解を深めるための情報提供としてご利用ください。
痩せたい気持ちが止まらない…拒食症を乗り越えるために知ってほしいこと

「歪んだ自己認識」
拒食症は、正式には神経性やせ症と呼ばれる摂食症(障害)の一種です。ただ単に「食を拒む症状」という言葉だけでは片付けられないほど、その背景には非常に複雑な心理的な要因が絡み合っています。
「もっと痩せたい」「太りたくない」といった気持ちから食事を極端に制限し、やがて健康を損なうほどに体重が減少していきます。しかし、本人は自分が痩せすぎているという自覚を持てず、周囲の心配にも耳を傾けられない状態に陥ることも少なくありません。
特に、思春期から20代の若い女性に多く見られ、無理なダイエットやモデルのようなスリムな体型への憧れがきっかけになることが増えています。しかし、その根底にあるのは、単なる容姿へのこだわりだけではなく、心の問題や家族、友人関係、社会的なストレスなど、さまざまな要素が複雑に絡み合っていることが多いのです。
拒食の背景には、幼少期の親子関係からくる“自己抑圧”や“過度な緊張”が影響しています。関連内容は親子問題・親子関係をご覧ください。
また、食べることに罪悪感を感じる傾向は、愛着不安と関連している場合があります。大人の愛着障害をご一読いただくことで、拒食症への理解が深まる一助となります。
この症状は、適切な対処をしないと命にかかわる危険性もあるため、決して軽視してはならない病気です。このコラムでは、拒食症のメカニズムから、心と体に与える深刻な影響、そして克服に向けての第一歩について詳しく解説します。
あなたは大丈夫?拒食症のサインを知るセルフチェック

「食べ物への恐怖や罪悪感」
自分では気づきにくい拒食症のサイン。次の項目に3つ以上当てはまる場合、注意が必要です。
- 生理不順や生理が止まってしまった
- 立ちくらみやめまいが頻繁にある
- 食後の体重増加がとても気になる
- 食事をした後に強い罪悪感に襲われる
- 食事のあと、吐かずにはいられない衝動に駆られる
- 身体が冷えやすく、寒さに弱いと感じる
- 食べ物のカロリーをいつも計算してしまう
- 食べ物を見ただけで嫌な気持ちになることがある
- 人の食事を見て「おぞましい」と感じることがある
- 体重が減るたびに嬉しく、達成感を感じる
- ほんの少しの量でも「多すぎる」と感じ、食事を完食できない
- 周囲から「痩せすぎ」と言われるが、自分ではそう思わない
- 痩せるために、過剰な運動をしたり、落ち着きなく動き回ってしまう
- 他人のスタイルが気になり、常に自分と比較してしまう
- 「痩せること」が人生において最も重要なテーマになっている
5つ以上当てはまる場合は、摂食障害のリスクが高まっている可能性があります。あくまで目安であり、診断を行うものではありません。不安を感じた場合は、一人で抱え込まず、医療機関や専門家に相談することをおすすめします。
拒食症が心身にもたらす深刻な影響

「孤独や心の葛藤」
拒食症は、単に体重が減るだけでなく、心と体の両方に非常に深刻なダメージを与えます。その影響は多岐にわたり、日々の生活を脅かすだけでなく、将来にわたる健康にも大きなリスクをもたらします。
身体に現れる危険なサイン
極度の体重減少と栄養不足は、身体のあらゆる機能に支障をきたします。
- 貧血や骨粗鬆症: 栄養が足りないことで血液や骨が十分に作られず、貧血や骨がスカスカになる骨粗鬆症を引き起こします。骨粗鬆症は将来の骨折リスクを高め、回復も困難になることがあります。
- 脳の萎縮と機能低下: 栄養不足は脳にも影響し、脳が委縮してしまうことがあります。その結果、集中力や記憶力の低下、意欲の喪失などが起こります。
- 無月経と不妊: 女性ホルモンの分泌が低下し、生理が止まってしまいます。若くして生理が止まると、将来の妊娠にも影響を及ぼす可能性があります。
- 循環器系のトラブル: 低栄養状態は、心臓の機能に負担をかけ、不整脈などを引き起こすことがあります。最悪の場合、心不全で命を落とす危険性もゼロではありません。
- 肌や髪のトラブル、むくみ: 栄養不足は肌の潤いを奪い、髪はパサついて抜けやすくなります。また、体温を保つために身体にうぶ毛が生えたり、逆にむくみがひどくなることもあります。
これらは、本来の美しさを求めて始めたはずのダイエットが、かえって容姿を損なう結果となってしまうことを示しています。
心に現れる危険なサイン
栄養不足は、心の安定にも大きな影響を与えます。
- うつ病や気分障害: 栄養が不足すると、心を安定させる神経伝達物質のバランスが崩れ、うつ病を合併するリスクが高まります。気分が落ち込み、何もやる気が起きなくなり、「自分はダメな人間だ」と自己否定を繰り返してしまいます。
- パニック障害や対人恐怖: 「痩せすぎた自分を見られたくない」という気持ちから人と会うのを避けるようになり、対人恐怖やパニック障害を引き起こすこともあります。
- 自傷行為や依存症: 精神的に不安定な状態が続くと、自傷行為に走ったり、アルコールや買い物など、別の依存症に陥るケースもあります。
このように、拒食症は心身に深刻な影響を及ぼし、生活や人間関係に大きな困難をもたらすことがあります。

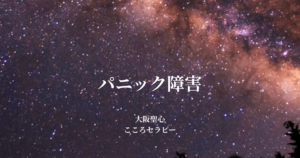
拒食症の根底にある「心の声」

「体重への執着」
拒食症は、単なる食の好みの問題やわがままな性格からくるものではありません。その行動の裏側には、とても複雑で深い心理的な要因が隠されています。
完璧主義と「〇〇でなければ愛されない」という思い
拒食症に陥る人は、完璧主義で真面目な努力家であるケースが非常に多いです。常に「良い子」であろうとし、周りの期待に応えようと頑張り続けます。しかし、心の中では「完璧でなければ、誰からも愛されないのではないか」という強い不安を抱えています。
その不安は、「もっと痩せれば褒めてもらえる」「スリムになればもっと愛される」という考えへとつながり、過度なダイエットに自分を追い込んでしまうのです。体重をコントロールすることで、自分の人生や周りの人間関係をコントロールしているような感覚を覚え、それが唯一の安心材料となってしまうこともあります。
親子関係の歪みが引き起こす心の叫び
本人は無自覚なことが多いのですが、拒食症の背景には、親子関係や家庭環境が影響する場合もあります。ただしそれが唯一の原因ではなく、個人の性格特性やストレス、社会文化的要因など、複数の要素が重なって発症すると理解されています。
例えば、幼い頃に親に十分に甘えることができなかったり、親の愛情を十分に感じられなかったりした場合、その愛情不足を埋めるために「良い子でいる」ことを自分に課してしまいます。その結果、「人に愛されるためには、何か条件を満たさなければならない」という極端な考えが生まれ、それが「痩せること」に結びついてしまうのです。
また、両親が不仲であったり、母親が苦労する姿を見て育った場合、無意識のうちに「大人になること」「女性として成熟すること」に恐怖心を抱くことがあります。女性らしい丸みを帯びた体になることを拒否することで、「私は母親のようにはならない」という心の抵抗を示している場合もあるのです。
「痩せること」への執着と自己肯定感の低さ
拒食症の人にとって、体重を減らすことは何よりも大きな達成感であり、自分の存在価値を高めるための唯一の手段になってしまいます。「あと〇kg痩せないと」と、目標はどんどんエスカレートしていき、自分で決めた食事のルールやカロリー計算に固執するようになります。
痩せることで周囲から褒められたり、注目されたりすると、その承認欲求が満たされ、ますます痩せることに固執してしまうという悪循環に陥ります。体重という数字に支配され、健康を害していても、その習慣を止めることができなくなるのです。



拒食症を乗り越えるためのヒントと専門家との協働
拒食症は、決して一人で解決できる問題ではありません。専門家の力を借りながら、少しずつ前に進んでいくことが大切です。
心理カウンセリングの重要性
拒食症は、単に「食べれば治る」という単純な病気ではありません。その背景にある複雑な心の状態を理解し、根本的な原因に向き合うことが不可欠です。
大阪聖心こころセラピーでは、拒食症を克服するために、まず心の状態を丁寧に紐解き、「親子問題の整理整頓」から始めます。これは、摂食障害の根底にある、自分に合っていない考え方や、親との関係によって生じた心の歪みを、自分に合ったものに修正していくプロセスです。
カウンセリングでは、「なぜ痩せることに固執してしまうのか」「なぜ自分を愛せないのか」といった心の奥底にある問題と向き合い、少しずつ自己肯定感を育んでいきます。症状に直接アプローチするのではなく、根本的な問題に取り組むことで、結果として摂食障害の症状が自然と穏やかになっていくのです。
家族や周囲のサポートの役割
本人は、拒食症を病気と認識できていないことが多いため、家族や周囲のサポートが非常に重要です。
- 否定しない、責めない: 「どうして食べないの?」「痩せすぎだよ」といった言葉は、かえって本人を追い詰めてしまいます。まずは、本人の気持ちを理解しようと寄り添い、決して否定したり責めたりしないことが大切です。
- 食事のプレッシャーをかけない: 家族で食事をする際に、無理に食べさせようとしたり、監視したりすることは逆効果です。本人が安心して食事ができる環境を整え、焦らずに少しずつ見守ることが重要です。
- 専門家への相談を促す: 「自分一人で解決しようとしないで、一緒に専門家に相談してみよう」と声をかけ、カウンセリングを受けることを促しましょう。
克服への第一歩は「自覚」と「向き合う勇気」
拒食症からの脱出は、本人が「このままではいけない」と自覚し、自分の心と向き合う強い意欲を持つことから始まります。それは、決して簡単な道のりではありませんが、適切なサポートを受けることで必ず解決の道は開けます。
大阪聖心こころセラピーは、拒食症を専門とするカウンセラーが、あなたの心に寄り添い、根本的な問題解決へと導きます。一人で悩まず、まずは一歩踏み出してご相談ください。
拒食症の誤解を解く Q&A
- 1. 拒食症はただの精神的な問題ですか?
-
いいえ、拒食症は精神的な問題だけでなく、身体にも深刻な影響を与える心身症です。栄養不足により、うつ病やパニック障害などの精神疾患を合併しやすいだけでなく、無月経、骨粗鬆症、循環器系の異常など、生命に関わる身体的な合併症を引き起こすこともあります。
- 2. 痩せれば治るという人もいますが…
-
拒食症の根本的な原因は、「痩せたい」という気持ちの裏にある心の状態です。単に体重を増やすだけでは根本的な解決にはなりません。むしろ、無理に体重を増やすことで、本人の精神的なストレスが増し、症状が悪化することもあります。適切な心理療法を通じて、心の状態を安定させることが重要です。
- 3. 拒食症は治るものですか?
-
回復は可能です。ただし、短期間で劇的に改善するものではなく、時間をかけて少しずつ取り組む必要があります。再発を防ぐためにも、継続的な支援や周囲の理解が大切です。拒食症は、その人のこれまでの生き方や考え方、育った環境など、さまざまな要因が複雑に絡み合って発症しています。それらを一つひとつ丁寧に紐解いていくことで、必ず克服へと向かうことができます。
- 4. 家族の接し方で気をつけることは?
-
家族が一番気をつけるべきは、「どうして食べないの?」と食事を巡って口論にならないことです。本人は、自分の体形への歪んだ認識や、食べることへの強い恐怖を抱えています。まずは、その気持ちを理解しようと努め、「ありのままのあなたでいいんだよ」というメッセージを言葉だけでなく、態度でも示してあげることが大切です。
痩せたい気持ちの裏にある本当の自分と向き合う

「回復と希望」
「痩せて綺麗になりたい」という気持ちは、多くの人が抱く自然な感情です。しかし、その気持ちが度を越え、自分自身を苦しめるようになってしまったら、それは危険なサインです。
拒食症は、単なる食の病気ではなく、「ありのままの自分」を愛せない心の病気です。痩せることでしか自分の価値を見出せない状態は、とても苦しいものです。
あなたは、太っていても痩せていても、あなたのままで十分に価値のある存在です。そのことを心の底から実感できたとき、あなたはきっと、食べることへの恐怖から解放され、健康的で豊かな人生を取り戻すことができるでしょう。
大阪聖心こころセラピーでは、拒食症の悩みや相談に精通したカウンセラーが、あなたの問題解決に向かうよう丁寧にサポートします。一人で悩まず、どうぞお気軽にお問い合わせください。
◆関連記事 親子問題・親子関係 大人の愛着障害 摂食症 自己否定・自己嫌悪
参考文献・参考資料
- 西園マーハ文(2017) 摂食障害における病識と治療 精神経誌 119巻 12号
- アメリカ精神医学会(著),日本精神神経学会(監訳)(2023)『DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル テキスト改訂版』 医学書院


