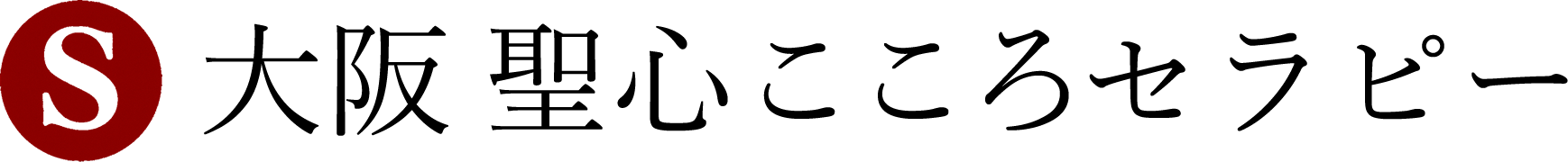夏の思い出


灼熱の太陽の下、暑さを逃れる電車の中から、きらきらひかる海が見えた。
今は海で泳ごうとは思わないが、見るのは季節問わず好きだ。
広い視界の中、波の一定のリズムを聞くと安心する。
見ているだけで飽きない不思議な時間。
夕方から夜にかけての紅い空は、とてもいい。
ふと、幼少期の夏休みを思い出す。
父は毎年変わる会社の保養施設を利用して、兄と私を海辺や湖畔に連れて行ってくれた。
小学校が終わるまで毎年当たり前のように1泊か2泊でどこかへ連れて行ってくれた。
母親は家でお留守番をして3人で出かける年も何度かあった。
夏をきちんと過ごす、儀式のような、それぞれの役割をちゃんとこなすような非日常。
細かいことははっきりとは覚えていないし、記憶も曖昧だが、でも楽しかった。
居心地がよかった。
日常では味わえない経験や、景色、色、においを存分に体中に浴びる。
無茶をしない子供だった私は、きちんと言うことを聞いて、ただそのままでいればよかった。
そういうことを許される、ちょっと甘えられる非日常だった。
兄と私は4歳から水泳教室に通っており、泳ぐことは好きだったが、プールとは違う壮大な海に、小さい私はおののいていたように思う。
兄は、きらきらした太陽の光を浴びながら、大胆に泳いで、全力で波と戯れていた。
すごく楽しそうだった。
好きや嫌いをはっきり言える兄がいつもうらやましかった。
私ははっきり言いたいことがなかった。
どれも嫌じゃなかったし、それなりにいいと思っていた。
いつでもどこでも、後々問題が起きないように気を配ってしまい、無心になったり、思いきった行動ができない。
そんな自分が好きではなかったが、何も起こらなければ、それはそれでよかったと思っていた。
自分が何を望んでるかはよくわからなかった。
自分の本音と人前での姿にはズレがあり、ずっと違和感があった。
どちらも偽りではなかったが、なんとなく苦しかった。
そんな自分は嘘つきで、ちょっと変なのだと思っていた。
今では、自分の好みは変化しつつも、その時、一瞬一瞬の思いを大切にしている。
大人になっていく過程で様々なことを知ったが、自分が自分の声と想いをきちんと聞くことを心がけている。
人に伝えるか、伝わるかはどちらでもいい。
自分だけはちゃんとわかってあげていれば、それでいい。
非日常を味わった後、疲れて帰ると、家では母が、日焼けした赤い肌や鼻の頭がやけている顔の私を兄を普通に迎えてくれて、また日常に戻る。
ちゃんと私たちに夏を魅せてくれたこと、心からありがたいと思う。